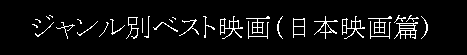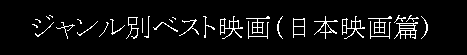恋愛には様々な形がある。幸せな恋もあれば悲しい恋もあり、純愛もあれば成熟した大人の恋もある。また祝福された恋もあれば道ならぬ恋もある。
身を滅ぼすような激しい恋もあるし、穏やかで慎ましい恋もある。
そうした様々な恋の物語を描いた映画の名作を選んでみる。
まずはじめは戦後すぐに作られた今井正監督の「また逢う日まで」である。
この映画は今井正監督の代表作であると同時に、純愛映画の名作であり、また日本映画の名作としてもかならず上位にあげられる作品である。
ロマン・ロランの小説「ピエールとリュイス」をもとに水木洋子が書きあげた美しいドラマを今井正監督が格調高く描いている。戦争によって引き裂かれていく若い男女の悲劇を謳いあげることで戦争の無惨さを浮き彫りにしており、戦争映画の名作でもある。
古今の有名な恋愛物語のほとんどはその背景になんらかの障害があり、それを乗り越えようとするところに熱い物語が生まれてくる。そしてその障害が大きければ大きいほど熱情も大きくなり、大恋愛劇が生まれるわけで
それはある時は因習による障害であったり、身分の違いであったり、またある時には時代の大きなうねりといった形で立ちはだかってくる。
そしてその時代のうねりのなかでも戦争という波は最大の障害といえる。
このことは戦争を背景にした物語に多くの名作があることでも明らかである。
「戦争と平和」「武器よさらば」「誰がために鐘は鳴る」「ドクトル・ジバゴ」とたちどころに何本もの名作を並べることができる。
明日さえ知れぬ暗い時代であるからこそ自らの生命を燃え立たせようと男と女は愛し合う。そしてその一瞬の輝きにすべてをかけようとする。残された時間がわずかであることを敏感に感じているからこそ、その時間は濃密なものとなり、生気に満ちたものになる。そんな絶望的な状況のなかでもわずかな可能性を信じながら愛し合う。いやだからこそ愛し合わずにはいられないのだ。
しかしそんな彼らのわずかな願いさえも裏切ってしまうような悲劇的な結末が訪れる。
「また逢う日まで」においても同様で、若い男女の純愛は結ばれることなくふたりの死という形で終わってしまう。
そしてこの無情な悲劇性がわれわれに鮮烈な感動を呼び起こす。それと同時にこの不条理な結末を生み出した戦争に強い憤りをおぼえてしまうのである。
成瀬巳喜男監督の名作「浮雲」も戦争のなかから生まれた物語である。
この映画は成瀬巳喜男監督が原作としてとりあげることが多かった林芙美子の小説を「また逢う日まで」と同じ水木洋子が脚色した作品である。
これは男女の情熱的な恋愛が成就した後の物語である。
戦時中、農林省の技官としてインドシナに赴任した男(森雅之)が妻ある身にもかかわらず部下の女性(高峰秀子)と愛し合う。
そして終戦後、身ひとつで引き揚げてきた女が先に帰国していた男を頼って訪ねてくる。
戦時中の恵まれた生活から一転した戦後の厳しい生活の中では、もうすでにふたりには甘い幻想も真剣に愛し合う情熱もなく、ただなぜか別れられない放埒な関係があるだけである。
夢がさめ、自堕落になっている男は女との関係を続けながらも別な女とも関係を持ったりする。
一方、女は生きるために米兵相手の娼婦にまで身を落とす。
そんな状態になっても別れられない男と女がもう一度人生をやり直そうと男の赴任先の屋久島へと旅立っていく。
しかしその旅の途中、女はそれまでの無理がたたって身体をこわしてしまい、ようやくの思いで島にたどり着くが、結局は男に見守られながらひとり寂しく死んでいく。
息をひきとった女のそばで男は慟哭する。
やりきれない幕切れである。自堕落で中途半端な生き方がどんどんふたりを追い込んで、ついには女の死という幕切れで決着がつく。ずるく愚かな男と、そんな男を見捨てられない哀れな女。こんなふたりの行き着く先はおそらくふたりには見えていたのかもしれないが、それでも別れることができない男と女の愛情の悲しさ、切なさ、そうした矛盾を孕んだ男と女の関係があるいは恋愛というものが持つひとつの側面なのかもしれない。また人と人との結びつきも、こうした矛盾や葛藤の上に成立しているものであり、ある種不合理な関係によって築かれるという一面があるものなのかもしれない。
成瀬巳喜男はそうしたことのすべてを含ませながらこの作品を作り上げ、真に生きる男と女の本物の人生を描ききったのである。
「浮雲」におけるぬきさしならない男と女の関係の対極にある純真な愛情を描いた名作に木下恵介監督の「野菊の如き君なりき」がある。
伊藤左千夫の小説「野菊の墓」の最初の映画化作品である。
小説では「矢切の渡し」で知られた千葉県松戸市近郊の農村が舞台だが、映画ではこれを信州に移し、その美しい自然を背景にいとこ同士である少年政夫(田中晋二)と少女民子(有田紀子)の悲しい純愛をこれ以上なく美しく描きあげている。
何十年ぶりかで故郷を訪れた老人(笠智衆)が若かりし日を回想するという形で物語が語られていく。
そしてその遠い歳月を表すために回想場面は白地の楕円のふちどりを施して、まるで古いアルバム写真を思わせるような画面にしており、それによって懐かしさに彩られた詩情あふれる映像を作り上げている。
無垢な物語同様に、映像もまたこれ以上なく純粋で無垢なものになっており、まるで宝石の結晶を思わせるような美しい輝きに満ちている。
若いふたりの純真な初恋が封建的で世間をはばかる大人たちによって引き裂かれ、やがて政夫から引き離された民子は意に染まぬ相手となかば無理矢理に結婚をさせられる。
嫁ぐ夜、人力車に乗り込んだ民子は政夫への未練を断ち切って、これからの運命に立ち向かおうとするかのように強い視線で前方を見つめ続けている。
その悲しくも健気な民子の心情に気づいた祖母(浦辺粂子)は「嫁に行くときはうつむいて行くもんじゃ」と涙ながらに優しく諭す。
それに従って民子は諦めたように下を向く。
そして嫁入りの行列が月明かりの中をまるで葬列を思わせるような悲しみを漂わせながら静かに進んでいく。
まさに前途に悲劇を予感させるような冷たく澄んだ美しい場面である。
そして数年の後、民子は胸を病んで帰らぬ人となる。
中学校に通うため故郷を離れていた政夫が急遽呼び戻される。
不審がる政夫に民子の死が告げられる。
呆然とする政夫に母親(杉村春子)は「おっ母さんが悪かった」と涙ながらに詫びる。「民やは嫁に行ってからも、お前のことばかり思っていたんだろう。行った先でもな、嫌がられてしまって、可愛そうに、家に帰されて寝てたんじゃ」そう言うと母親は激しく慟哭する。
その話を受けて若いふたりに終始同情的だった祖母が民子の最期を切々と語り始める。
「民子はな、お前の名前を一言も言わなんだ。だもんでな、諦めきってることと思って一目も会わさんで・・・。許してくれや。だけどな、息を引き取った後で、枕を直そうと思ったら、左の手にな、切れに包んだ物をしっかりと握って、その手を胸に乗せていたんじゃ。可愛そうな気もするけど、見ずにおくのも気にかかるので、皆で相談してそれを開いてみたらな、政夫、民子は嫁に行って、お前に会わす顔がないので、それでお前の名前は一言も言わなんだんじゃ。切れに包んであったのはのう、お前の手紙と竜胆の花じゃった」
かって民子が政夫をそれに例えた竜胆の花と政夫からの手紙を肌身はなさず隠し持っていた少女の密かな愛、その美しくも悲しい一途な愛を知ったとき、われわれは政夫とともに声をあげて涙を流すことになる。
技巧を越えた深い感動が胸に迫ってくる。
今は老いた主人公が静かに墓前に野菊を手向ける。それは少女の霊を慰めるとともに自らの純愛への鎮魂と過ぎ去った美しい時間への深い愛着を捧げたものでもある。
こうして無垢なアルバムの最後のページを閉じるかのようにして映画は終わるのである。
それはあたかも至純の愛を永遠に封印するかのようである。
「絶唱」も「野菊のごとき君なりき」と似た設定の純愛映画である。
大江賢次の同名小説を映画化したこの作品で、アクションスターとして売り出す前の小林旭と浅丘ルリ子が主役を演じている。
映画が製作されたのが昭和三十三年ということだから、私がこの映画を観た時は十歳だったということになる。
その年齢でどの程度のことが理解できたのかはなはだ怪しいものだが、不思議と強い印象を受たことを憶えている。
そしてその内容の印象とともにこの映画を観ていた時の劇場の様子を断片的だがかなりはっきりと記憶している。
古い芝居小屋を映画館にした劇場の二階右手の桟敷席で、柵に顎を乗せた格好でじっとスクリーンを凝視していたことを鮮明に思い出す。
そして古い大地主の息子と山番の娘の身分違いの恋が悲恋に終わる経緯に子供ごころにも無情なものを感じていた。
また周囲の頑迷な反対にあい、駆け落ちをした後のつかの間の幸せも戦争による召集によって断たれてしまい、戦地から復員してきた時にはもはや娘が息を引き取る寸前といった悲運には子供ながらに胸を痛めたものである。
そして死んだ娘に白無垢の花嫁衣装を着せて結婚式を挙げるラスト・シーンに至ると、子供ながらにも一気に感傷の極みへと登り詰めてしまった。
まさにメロドラマには不可欠な甘美なシーンであり、心地よい詩情とカタルシスを感じる場面であった。
この物語はその後二度にわたって映画化されている。
同じ日活で、「絶唱」を歌謡曲で歌った歌手舟木一夫が和泉雅子と共演して映画化されている。
二度目は三浦友和と山口百恵のコンビによる再映画化である。
この二本はどちらも西河克己監督によるもので、長年プログラムピクチャーを作り続けているベテラン監督らしい上質でウェルメイドな作品に仕上がっている。
だが、やはり最初に観た印象が鮮やかだったことから、小林旭、浅丘ルリ子主演のものがもっとも印象に残っている。
そして後にふたりのコンビで量産されたアクション映画と違った異質な映画ということでも印象に残る作品なのである。
「秋津温泉」
松竹ヌーベルバーグの旗手のひとり、吉田喜重監督の代表作であり、後に彼と結婚することになる岡田茉莉子の企画、主演によって作られた。
戦争末期、岡山県の山奥にある秋津温泉の一軒の宿に胸を病んで行き場のない青年(長門裕之)が行き倒れのような形で転がり込む。
生きる意欲をなくし、絶望的な青年を宿の娘(岡田茉莉子)がかいがいしく看病する。
その健康的で屈託のない娘の姿に打たれた青年は、もう一度強く生きることを決意する。
戦争が終わり、健康を取り戻した青年は温泉宿を離れ、すべてをやりなおそうと新しい生活を始める。
そしてその後も、たびたびこの温泉地を訪れることで十数年にわたる娘との長い交流が続いていく。
そんな男と女が時代の流れの中で次第に変質していく姿をカメラは的確にとらえていく。
強く生きることを決意した青年もいつしか自堕落で退屈な中年男になり変わっていく。
売れない小説家である主人公は常に迷いと苦しみの中にあり、自らの才能への不信とその裏返しともいえる自分を認めない世間への八つ当たりに終始している。
その矛盾に満ちた混迷の中で何とか出口を探し求めようと試みるが、結局出口は見つからず、シニカルな態度をとるだけに終わる。
そしてそんな世間との闘いに疲れたとき、彼は再び秋津温泉へと向かう。
しかし旅館の女将となった女もかつての輝くような生命力は失ってしまい、世俗のわずらわしさとそんな男への失望からついには自殺をしてしまう。
愛し合うことをさけ、深みに落ちることもない半端な関係が却ってふたりを離れ難く結びつける。
そんな男と女の実りのない関係が一方の死によって終わりを告げることになる。
残された男はいわば貴重な逃げ場を失ってしまったわけで、孤独はさらに深いものになり、ますます迷路へと踏み込んでいくことになる。
そして確かなことはその孤独と悲しみは自らが引き受けて生き続けていかなければならないということである。
エンド・マーク以後の男の人生は重い。
「憎いあんちくしょう」では男と女のそんな日常の倦怠を打ち破ろうとする新しい愛の形を描いている。
石原裕次郎と浅丘ルリ子の共演によるこの映画は、蔵原惟繕監督とシナリオライター山田信夫のコンビによる作品で、この四人の組み合わせによって「何か面白いことないか」と「銀座の恋の物語」が連続して作られている。
いずれの作品も現代の新しい愛の形を追求しようとしたもであり、このコンビによる愛の三部作といえるものである。
どれも良質な作品で、当時の日活作品のなかでも強く印象に残る作品であった。
「憎いあんちくしょう」の主人公、北大作(石原裕次郎)は売れっ子のニュースキャスターである。
そして彼のマネージャーである榊典子(浅丘ルリ子)は彼の恋人である。
しかし超多忙なふたりの仲は少々倦怠気味であり、あやうい状態のなかにある。
ある時、新聞に恋人の医師が働く九州の無医村に無料でジープを陸送してくれる人を求めるという投書があり、これに興味を持った大作はその投書をしてきた女性(芦川いずみ)にインタビューを申し込む。
この女性と恋人(小池朝雄)は文通で知り合った仲で、長く時間をかけてふたりの愛情を育てており、互いに強い信頼で結ばれているのだと彼女は答える。
そしてその愛情が本物であることを確かめるためにもジープを恋人のもとに届けたいのだと告白する。
典子との愛に迷っていた大作はその愛が本物かどうかということに興味を惹かれ、それを確かめるために車を陸送する役をとっさに引き受ける。
そして恋人の典子が止めるのも聞かず番組に穴をあけたまま出発してしまう。
そんな大作を典子はなんとか自分の愛情で引き留め連れ戻そうと後を追う。
マスコミも突然起きたハプニングを恰好の取材ネタとしてふたりを追いかけ報道合戦を繰り広げていく。
次第に取材が加熱していき、それに煽られた物見高い大勢の視聴者がことの顛末を見ようとふたりの行く先々に殺到し始める。
こうしたなか様々な出来事によって大作と典子が次第に孤立化していくが、逆にそうした状況がふたりの愛情を再生していくという展開がスピーディーな語り口によって描かれていく。
マスコミと大衆の関係やマスコミによって個人が圧殺されていくというテーマを男女の愛情にうまく絡めてシャープな映像で表現している。
そして石原裕次郎と浅丘ルリ子の都会的な魅力がそれを補完して余りある。
時代の先端をゆくニュースキャスター役の裕次郎の格好良さはいわずもがなであるが、その彼を必死で引き留めようとする浅丘ルリ子の汗まみれの熱演は生気にあふれている。
自立した現代の女性を先取りしてはつらつと演じている。
「何か面白いことないか」における役柄も同様に現代性あふれる女性であり、裕次郎に反発しながらも強く惹かれていくという引き裂かれた女の複雑さを好演している。
女としての強さと弱さを頑ななまでに演じて、健気で美しい。
国際線の一流パイロットの職をなげうって多額の生命保険を掛け、それを担保に典子(浅丘ルリ子)が所有する中古セスナ機を買い取り、新しい生き方を模索しようとする男、早坂次郎(石原裕次郎)。
突然現れたそんな早坂に典子は強い興味を感じる。
しかし一方では世間の常識に逆らうような彼の生き方に胡散臭さを感じ、その欺瞞を暴こうと男の行動の前に立ちはだかり何かと妨害をしようとする。
だがそんな典子の思惑とは反対に早坂は思いもよらない斬新な行動で次々と現れる難問をクリアしていく。
その爽やかな生き方にマスコミや世間が俄然注目し始め、ついには「現代のドンキホーテ」として喝采を送るようになる。
しかしそんな世間の喝采とは逆に次第に反発を強めていく典子。
次第に追いつめられた典子は嵐の夜、セスナ機を繋ぎ止めていたワイヤーを自らの手で切ってしまう。
こうしたアンビバレンツな感情に揺れ動く微妙な心理の女性を「憎いあんちくしょう」同様、浅丘ルリ子が魅力的に演じている。
この頃から浅丘ルリ子は女優として一気に華開いていった印象が強い。
日活映画における女優の存在はとかく添え物的な要素が強く、彼女の場合も小林旭の「渡り鳥」シリーズ等を中心にもっぱら可憐で可愛いだけの役柄が多かった。
だが「憎いあんちくしょう」以降は俄然輝きを放つようになる。
それは明確なキャラクターを持った一個の自立した人間を演じることで獲得したものであり、彼女の現代的な個性が自我の強い役柄にうまくはまったということである。
また石原裕次郎という得難い相手役との相性のよさも大きな要素になっている。
以後このコンビによる数多くの秀作が生まれていく。
なかでも「銀座の恋の物語」はその代表作といえる作品である。
この映画は蔵原惟繕監督のバタくさくモダンな感覚が効果的に発揮された秀作である。
蔵原監督はデビュー作「俺は待ってるぜ」を都会的な感性でハリウッド映画を思わせるような作品に作り上げており、以来その感覚の路線が彼の持ち味となっている。
そして、山田信夫という良きパートナーを得ることでその路線をさらに研きのかかったものにしていく。
銀座を舞台に若く貧しい画家志望の青年、伴次郎(石原裕次郎)とその恋人(浅丘ルリ子)の物語が彼らを取り巻く善意の人々を絡ませながら下町人情話風に描かれる。
そして、それがパリやニューヨークの下町を思わせるような洗練されたタッチで描かれることで現代的センスにあふれた映画になっている。
いま見直しても十分新しく、登場する風俗が幾分古めかしいところもあるが、それを意識することなく一気に観せられる力強さがある。
銀座は画廊の多い街である。昭和初期に日動画廊が開設されたのをきっかけに増え続け、現在ではその数は大小合わせて100はくだらないのではなかろうか。
そんな銀座独特の文化的な香りを上手に織り込むことで、この作品を上品で洗練されたものにしている。
その銀座の裏町に画家志望の青年、伴次郎が友人の音楽家志望の青年、宮本(ジェリー藤尾)と共同生活をしている。彼らはお互いを励ましながらいつか世に出る日を夢見ている。
そして若く貧しい彼らを近隣の善良な人たちが陰ながら応援している。
次郎の恋人久子もそんなひとりである。
彼女は次郎の住む屋根裏部屋と窓を接したビルの洋装店のお針子で、いつか次郎とふたりでささやかな家庭を持つことを夢見ている。
だが、貧しさと世間に認められない焦りから次第に彼らは挫けそうになっていく。
そして自棄になった宮本はとうとう夢を捨て、金のために悪の道に染まっていく。
また次郎と久子も将来の見えない生活に不安を感じ、意見の食い違いから衝突をしてしまう。
しかし冷静になったふたりはお互いの立場を思いやり、身動きならなくなった現実を打開するために新しい生活を始めることを決意する。
そしてその再出発のためにふたりで信州に住む次郎の母親に会いにいくことにする。
ふたりは駅で待ち合わせるがなぜか久子は現れず、そのまま忽然と次郎の前から姿を消してしまう。
次郎は必死に捜索するがどうしても捜しだすことができない。
そして数年後、デパートのアナウンス嬢として働く彼女を偶然見つけだすのだが、彼女は交通事故がもとで記憶を失っていた。
再会したふたりの記憶を取り戻すための懸命な悪戦苦闘が始まることになる。
思い出をひとつひとつたどりながら過去を追体験することで記憶を蘇らそうと試みる。
試行錯誤を繰り返すなかでふたりが新たな愛を獲得し、ふとしたきっかけから記憶を取り戻すまでがサスペンスあふれる展開で描かれていく。
それはメロドラマの名匠マービン・ルロイの「心の旅路」を思わせるような展開であり、またそれに負けず劣らず見応えのあるスリリングな展開になっている。
ここでは主題歌が記憶を取り戻す際の重要な鍵として巧みに使われており、その哀調なメロディーとともに強く印象に残っている。
そして今やスタンダードになったこの主題歌を聞くたびにこの映画を鮮やかに思い出すのである。
「湖の琴」
田坂具隆監督晩年の名作である。この映画に先だって作られた「五番町夕霧楼」同様水上勉の原作で、主役も同じ佐久間良子が演じている。
琵琶湖の陰に隠れるようにして余呉湖という名の小さな湖がある。
その湖を臨む寒村を舞台に、農家の若い男(中村賀津雄)と女(佐久間良子)の悲恋を晩年の田坂監督が情感豊かに描いている。
この村では昔から琴や三味線の糸づくりが盛んで、主人公ふたりはその労働にいそしんでいる。
その糸づくりの工程が繭を育てるところから糸が出来上がるまでを端正な映像によって工芸品のような美しさで描かれる。
そして作業に汗を流す人々に交じって働く若い主人公のふたりの素朴な恋がそれと歩調を合わせるように美しく謳いあげられていく。
そのままであればおそらく大勢の人たちに祝福され、貧しいながらも純朴な百姓夫婦として一生を終えただろうが、人並みはずれて美しい娘の美貌が悲劇を生み出すことになってしまう。
いつの世も女性の美しさが悲劇を生むというストーリーがくりかえし語られるが、ここでもそのパターンが踏襲されることになる。
糸づくりを見学に村を訪れた京都の高名な三味線の名手、桐屋紋左衛門(中村鴈次郎)が一目で娘に惚れてしまったことから運命の糸がもつれ始める。
紋左衛門はこの娘を何とか自分のものにしようと三味線の才能もない娘を無理矢理自分の弟子にしてしまう。
そして京都に連れ帰るや様々な手段を労して娘に言い寄るが、ことごとく娘にはね返されてしまう。
この老いらくの恋に狂う男を鴈次郎が絶妙に演じている。
生っ白く淫靡でいかにも好色そうな京男を見事に演じており、こういう役を演じさせると鴈次郎にかなう役者はいない。
歌舞伎の和事で鍛えた柔らかな色気が老いた肉体から匂い立ってくるとき、それは粘着質ないやらしさに変質する。
それでいて下品にならず、高名な三味線の名手という体裁を崩さないのはさすがである。
「炎上」や「雁の寺」の女色に溺れた住職や「鍵」の主人公もそうした種類の男たちであり、まさに鴈次郎の至芸といえる。(「炎上」で住職が隠れてオーデコロンを塗るところなどは生理的な嫌らしさを感じてしまう。しかしそれだからこそ、くりかえし見たくなる。)
道理の見えなくなった桐屋紋左衛門はとうとう力づくで娘の体を奪いとってしまう。
悲嘆にくれた娘は村に逃げ帰り、恋人である若者と再会するが翌日理由も告げずに自ら命を絶ってしまう。
娘の死体を発見した若者は誰にもその姿を見せたくないとふたりで余呉の湖に身を投げる。
ふたりが抱き合って入ったつづらが静かに湖の底に沈んでいくラストシーンは水中撮影によって幻想的に描かれる。
最近見たジェーン・カンピオン監督の「ピアノ・レッスン」にもこれとそっくりな場面が登場してきて、ふとこの映画を思い出してしまった。
ここではピアノとともに海の底に沈んでいく女主人公を見事な水中撮影でとらえており、その幻想的な美しさは「湖の琴」を思わせるものであった。
「ピアノ・レッスン」の主人公はピアノにからまったロープをほどいて浮かび上がってきたが「湖の琴」のつづらは2度と浮かび上がることなく、湖の底に張り付いたように動かない。
悲恋の幕はその湖の底の静かさのようにゆっくりと静かに下ろされてしまったのである。
「忍ぶ川」
三浦哲郎の芥川賞受賞作品を映画化したものである。
原作は研ぎ澄まされた文章によって情感豊かに書かれた珠玉の名篇であり、おそらくこれからも長く読み継がれていくに違いない名作中の名作である。
こうした名作の映画化となれば、その味わいを損なわずに撮る事ということは至難の業であり、かなり高い確率で失敗作になりがちなものである。
だが熊井啓監督はその難しさを見事にクリアし、原作に劣らぬ感動的な作品に仕上げており、熊井監督の代表作ともいえるような完成度の高い作品にしている。
この映画が完成するまでにはかなり長い期間に渡っての紆余曲折があった。
原作が芥川賞を受賞したのが昭和三十五年のことで、映画各社からただちに映画化の話が持ち上がり、その獲得競争のなかから日活が映画化権を獲得することになる。
そして吉永小百合主演による映画化が企画され、吉永本人も大いに乗り気であったが、最後のクライマックスの初夜のシーンが問題となり、当時の吉永小百合のマネージメントいっさいを取り仕切っていた父親が清純派のイメージを損なうという理由で強硬にこれに反対をし、結局この時の映画化は頓挫してしまう。
その後十年近くを経て熊井監督の執念が実ってようやくにして撮影にまでこぎ着けたものの、今度は熊井監督が持病の結核で倒れて入院という事態になり、またもや撮影が中断してしまう。
結局この中止寸前の危機も監督が懸命に病気を克服することで何とか乗り越えることができ、ようやく積年の夢を果たして映画が完成されたのである。
苦節十年という言葉通り、映画化の企画が持ち上がってから十数年という難産の末に産み落とされた作品である。
そんなわけでこの映画は様々な困難を乗り越えてきた思いと執念が画面からにじみ出てくるるような緊張感あふれた名作になっているのである。
主人公の私(加藤剛)と志乃(栗原小巻)の出会いから結婚までを描いたこの物語は三浦哲郎の実体験をベースに書かれている。
その体験からできるだけよけいなものを削ぎ落とし、ふたりの愛情の輝きだけを抽出して美しく描きあげた物語である。
そしてその愛情の輝きが様々な死と対比されることでさらに強い光を放射することになる。
主人公の私は六人きょうだいの末っ子である。
兄が二人、姉が三人いたがひとりの姉を残して全員が自殺や失踪による不幸な死に方をしている。
そんな家系の暗さを背負った私が率直でまっすぐな志乃と知り合い、愛し合うようになる。
だが志乃も私と同じように重いものを背負った人間であった。
志乃の両親はかって洲崎遊郭で射的屋を営んでいたことがあり、そんな生い立ちゆえに世間から白い目で見られがちであった。。
そして今はその母親もすでになく、父親は貧しさの中で長く患っており、私との結婚を決意した直後に危篤に陥ってしまう。
志乃は臨終の席に私を呼び寄せ、死のうとする父親に会わせる。
「お父さん見える?」「どう見える?」という志乃の呼びかけに父は「見えるよ。いい男だよ」のひとことを残して翌朝息を引き取る。
こうした暗く悲しい様々な死に囲まれ、その影にかすめ取られそうになるふたりだが、それを振り払うようにして私の故郷八戸へと旅立っていく。
そして雪の降る元日の夜、私の両親と姉だけのささやかな結婚式をあげる。
「世の中に、これ以上ちいさな結婚式はないであろうが、またこれ以上、心がじかにふれあって、汗ばむほどにあたたかい式も他にはないはずであった」という主人公のナレーションがこれに重なって流れる。
六人いた子供がいまは私と姉のふたりだけになり、年老いた両親にとっては初めてあげる息子の結婚式であった。
これまでの子供たちの不幸を思うと、ささやかでもこれは家族の言葉につくせぬ愉悦の一夜なのである。
そして若いふたりの死の影を振り払って懸命に生きようとする門出の儀式でもある。
ふたりは初夜の床で遠く静けさのなかから聞こえてくる馬橇の鈴の音を耳にする。
その音はまるでふたりの門出を祝福するかのような穏やかで美しい響きである。
ふたりは裸のまま一枚の丹前にくるまって、部屋をぬけ、雪のなかを走る馬橇の影を眺める。
それはまるで死の影が遠ざかって行くかのようであり、また若いふたりの生命の讃歌を奏でているかのようでもある。
これはまさに死と再生が美しく結晶した物語である。
この映画を見ながら私は二十三歳の時に初めて津軽を訪れた日のことを思い出す。
当時私たち夫婦はこの映画の主人公と同様にまだ学生の身であったが、すでにいっしょに住んで生活をしていた。
定職はなく、わずかなアルバイトと妻に送られてくる仕送りをあてにするという今考えれば実に手前勝手でいいかげんな生活であった。
親に隠れていつまでも続けられる生活ではなく、この年の冬、そんな生活にけじめをつけようと妻の両親の住む津軽へと旅立った。気の重い旅だった。
急行列車に長時間揺られ、私はいつのまにか眠り込んでいた。
列車のきしむ音に眼を醒ました時、列車はすでに県境を越え東北の田園地帯を軽快に走り続けていた。
暮れなずんだ窓の外に目をやるとそこは一面の銀世界だった。
鉛色の空と白い雪に被われたその荒々しい風景は雪のない温暖な地方に育った私にとっては馴染みのないものであった。
それは映画「忍ぶ川」の車窓から見える景色と同様のものであり、気の重い私の心をいっそう重く滅入らせる風景であった。
前途に何があるのか。夢や希望ばかりではない、むしろ得体の知れない不安な暗い闇が待ちかまえているように思えた。
そしてそんな憂鬱な気分をひきずったまま津軽に降り立ち、再び東京へと戻ってくることになる。
だがこの津軽への短い旅行の後、話し合いが不首尾に終わったにも関わらず不思議なことに前途に対する自信めいたものが突然わいてきた。
何の理由もなく急にそう思い、それでいて確信に近いような感覚であった。
それは追い込まれた末に出てきた居直った感情だったかもしれない。
また新たな局面に一歩を踏み出したことによる気負った感情がそうさせたのかもしれない。
おそらく「忍ぶ川」のふたりの思いもそれに近いものがあったのではなかろうか。
不安と自信の交錯した奇妙な感覚のなかで私の短い津軽への旅は終わったのである。
そしてあれからもうすでに二十七年という歳月が流れた。
あの頃を思い出すと奇妙な感慨にとらわれる。
そしてこの映画を観るたびにあの時の情景が鮮明に蘇ってくるのである。
「藍より青く」
山田太一の原作シナリオでNHK朝の連続テレビ小説として放映されたドラマを森崎東が映画化した作品である。
昭和19年の天草を舞台に網元の息子周一(大和田伸也)と校長(三国連太郎)の娘、真紀(松坂慶子)の恋愛が生き生きと描かれる。
主演の大和田伸也がいかにも若く生きのいい漁師を好演しており、テレビ版で話題になったことが十分うなずける溌剌とした演技である。
正義感の強い硬派の青年という役柄に彼の柄がよくはまっており、それがこの映画の大きな魅力にもなっている。対する恋人役の松坂慶子もいつもの鼻につくおおげさな演技ではなく、まっすぐな青年がいかにも惚れそうな利発で控えめな娘を好演している。
そして彼らを囲むようにして芝居上手な脇役たちが大勢登場し、作品を引き締めている。
三国連太郎が戦前の教育者の典型である中学の校長で、娘の恋に戸惑い、頑固に反対する父親役を好演している。また大和田伸也の両親を佐野浅夫と赤木春恵が演じている。 佐野浅夫は大勢の漁師を差配する網元らしい器の大きさときっぷのよさをみせ、赤木春恵も気が強く人情味のある女房を好演している。
また田中邦衛が若い漁師たちを束ねる気のいい漁師の若頭を喜々として演じている。
この他、大和田伸也の弟に尾藤イサオ、郵便局の局長に財津一郎といった渋い顔ぶれがそろっている。
森崎東監督は大勢の庶民が本音でぶつかり合い、また支えあって生きる世界をひたすら描き続けている。そしてそこに登場するしぶとく生きる様々な人間を個性あふれた造型で描くことを得意としている。
この映画でもそうした人物造型が細部にわたってなされており、彼らによってふたりがしっかりと支えられ、若くたくましい生命力を発散しながら確実に地域の中に根付いていいく様子が爽やかに描かれている。
そうした人間たちのアンサンブルが生き生きとした世界を形作り、生きることの楽しさ、素朴な人間たちの逞しさ、力強さを感じさせられる。
こうした映画を見るにつけ、いつも元気づけられ、前向きな気持ちにさせられる。
「なかなか人生、捨てたもんじゃないんだな」といった気分でいっぱいになるのである。
「伊豆の踊子」
川端康成の名作「伊豆の踊子」は繰り返し映画化されている作品である。
昭和8年に田中絹代が踊子に扮したのを皮切りに美空ひばり、鰐淵晴子、吉永小百合、内藤洋子、山口百恵といった具合に都合6回も映画化されている。
そしてそれぞれに演じた女優がまだ可憐な少女の面影を残した時代の映画である。
まだ女優と呼ばれるにはいささか戸惑うほど映画の世界には不案内な時期の映画であり、演技的にはまだまだ多くを求めることはできない。そこで演技以前の素材の良し悪しというか、生まれ持った素質の魅力が映画の成否に大きく関わってくることになる。
もちろんその素質をどう生かすかは監督の腕にかかってくるわけだが、やはり彼女たちの素材としての魅力が映画の出来を左右する最大の要素になってくる。
これら6本の映画の中で山口百恵版「伊豆の踊子」が最も魅力にあふれていると思われる大きな理由もそうしたことによるものである。
彼女の素材としての魅力、女優として開花する前の可憐で慎ましい魅力が十二分に引き出されており、素質と役柄が幸せな融合を果たした映画になっている。
この映画は山口百恵の映画初主演作品であると同時に、後にシリーズ化されて作られることになった三浦友和との初共演作品でもある。
「伊豆の踊子」以降作られた共演作品としては、「潮騒」「絶唱」「エデンの海」「春琴抄」「霧の旗」などがあり、これらすべてがかってヒットした作品の再映画化作品であり、監督もすべて西河克己監督によるものである。
このように繰り返し何度も映画化される作品というのは、ある程度の興行収入が見込まれる無難な企画であり、アイドル映画を作る場合の常套手段ともいえる企画である。
それだけに新味に乏しく、面白味に欠けるものであり、安易で当たり障りのない安全な企画といえる。
しかし、そうやってつくられた映画であるにもかかわらずこれはなかなか見応えのある作品に仕上がっている。
山口百恵、三浦友和コンビの映画のなかでも代表的な一本になっている。また、この映画がヒットしたことから、ふたりの共演映画がシリーズ化されたわけで、そうした意味でも記念碑的な作品といえる。
よく知られたことだが、山口百恵の生い立ちは幼い頃に両親が離婚をしたことから家庭的に恵まれない貧しいものであった。
そんな家庭環境が彼女の資質のなかに暗い陰を作っており、それが彼女の魅力を複雑でミステリアスなものにしている。
そうした彼女の資質がこの「伊豆の踊子」の複雑な役柄と巧みに重なり合っている。
冒頭、旅芸人一座の社会的に差別された立場をいくつかのエピソードを挟んでさりげなく見せ、その家族のひとりである踊り子の将来の薄幸さをそれとなく予感させている。
そして山口百恵がきわめて自然に演じる踊り子の無邪気さがそれをさらに際だたせたものにしている。
それゆえ学生の娘に対する同情が次第に愛情へと変わっていく過程にわれわれ観客もごく自然に同化していくことができるのである。
この物語の時代背景である大正末期の頃は社会にはまだ厳然とした身分制度が存在していた時代である。
主人公の一高生はエリートの卵であり、片や踊り子は下層に身を置く少女である。本来ならふたりが交わることはなかったはずだが、伊豆の山中を旅するなかでの偶然の出会い、「旅」という俗世間の匂いの少ない場所での出会いが両者の身分の垣根を意識することなく越えさせた。
そして「旅」という解放された空間がこの初恋物語を産み出し、美しい物語へと昇華していくのである。そうした原作の持つ味わいを西河克己監督はまことに手堅く映像化している。
そしてさらにこの初恋物語の裏に流れる時代の悲しさを閑かにすくい取っている。
この映画の印象深いエピソードがひとつある。
踊り子が幼なじみの少女(石川さゆり)を温泉場の遊郭に訪ねるが、そこに少女はおらず誰もその行方を知らない。だがある日温泉場の鄙びた裏屋で偶然病気でふせっている少女を見つける。少女は遊郭で過酷に働かされ続け、その無理がたたって胸を患ってしまったのである。死期の迫った少女に踊り子は「きっとよくなる。よくなっていっしょに島へ帰ろう」と涙ながらに励ますが、数日後少女はひっそりと息をひきとってしまう。
まだ薄暗い早朝、人目を忍ぶように少女の貧しい棺桶が運び出される。
幼なじみの少女の死に形を借りて踊り子の不幸な将来を暗示するかのような悲しいエピソードである。
そしてこの気分はそのまま途切れずにラスト・シーンへとつながっていく。
下田での踊り子と学生の船での別れの後、温泉宿の宴会で踊り子が酔客にしつこく絡まれながら踊りを踊る場面がラスト・シーンとして描かれる。そしてその酔客が踊り子に抱きついた瞬間、画面はストップ・モーションとなって映画は終わる。
一高生との別れの悲しみを隠し、寂しく微笑みながら精一杯踊り続ける踊り子の横顔は悲しく切ない。しかし、それが暗い将来を予感させはするものの、同時に山口百恵の表情にそれだけではない強い意志的な光を感じさせるのも確かである。弱いだけではない、簡単に手折られるだけではない女のしたたかさの芽のようなものをそこに見ることができる。そして、それこそが山口百恵が他の凡百のアイドルと決定的に違う所であり、彼女の持って生まれた素質の希有なところだろう。
そしてそんな彼女の魅力を巧みに引き出し画面に定着させたことでこの作品は厚みを増し、「アイドル映画」というだけではない質の高い作品になりえたのである。
西河克己監督の手堅い手腕に拍手を送りたくなるのである。
こうした映画に遭遇すると、いわゆる「アイドル映画」の類をただ単に「アイドル映画」というだけで軽く見たり、貶めたりする愚を犯さないようにしなければとの思いを強くする。とかく偏見や先入観からこうした映画を敬遠しがちであるが、例えそれがどんな種類の映画であろうと、そうした見方に捕らわれず、とにかく正しく観ることで評価しなければならない。
そんなことは当たり前のことだと言われるかもしれないが、意外と実行できないことのように思う。
心しなければならない。
さて最後に、現代の最も新しいメディアであるパソコンを通して男女が結びつく恋愛映画「ハル」を取り上げることにする。
現代は大恋愛や悲恋の物語が成立しにくい時代である。
先にあげたような大恋愛の前提である大きな障害というものは現代では見つけにくい。
戦争もなければ身分による隔たりもない。道徳的な制約もなく、男女間の垣根はあっさりと壊されお互いが身近に存在し、その気になればいとも簡単に男と女が恋愛関係に入ることができる。また愛情が冷めた時にはあっさりと別れることも可能である。その選択はきわめて自由である。
こうした時代にあって、恋愛とは果たしていかなるものなのか。
このきわめて現代的なテーマが映画「ハル」では時代の先端のテクノロジーであるコンピューターを駆使しながら描かれていく。
コンピューターと「ハル」といえば映画好きならすぐにスタンリー・キューブリックの「2001年・宇宙の旅」を思い出すだろうが、この映画で通信ネーム「ハル」を使ってパソコン通信をやっている主人公(内野聖陽)もやはり映画好きの青年で、映画フォーラムにアクセスをしている。
そしてそこからこの物語が始まっていく。
彼は学生時代からアメフトの選手だったが、今は腰を痛めて選手生活を断念している。
そしてそれに歩調を合わせるように仕事も恋もうまくいかなくなっており、そんな日常の鬱屈をパソコン通信によって慰めようとしている。
きわめて現代的な若者の孤独な日常である。
ある日そんな彼を励ますメールが届けられる。
(ほし)というネームの人物である。そして、ここから(ハル)と(ほし)のお互いを癒し会う日記のようなメールの交換が始まっていく。
(ほし)は男性を名乗っているが、本当は女性(深津絵里)で、お互い相手の正体がわからないままメールによって本音を吐露し合っているうちにそうした事実が次第に明らかになっていく。
パソコンのディスプレイの画面が映画の画面と重なってメールの文章が静かに打ち込まれていく。観客であるわれわれがそれを主人公とともに読むことで次第に物語世界へと引き込まれていく。それはこれまでの映画にはなかった感覚で、例えば読書をする感覚に近いものである。それも日記やエッセイを読む体験に近い。
繰り返し現れるパソコン通信の画面を読みすすんでいくうちに、一見穏やかで何事もないように見えた彼らの生活が、実は目に見えない心の中では起伏に富んだドラマが展開しているのだということに次第に気づかされていく。
劇的な展開や事件が起こるわけでもないのに、いつのまにかそこにダイナミックなドラマを感じている。
そしてふたりがいくつかの行き違いやためらいを経ながら新幹線のプラット・ホームで初めて会うことになるラスト・シーンではわれわれもふたりといっしょに爽やかな感動に包まれることになる。
大きな変化もなく、きわめて自由で何気ないように見える現代の男女の間にも、こうした胸躍るようなドラマが展開されており、それを森田芳光監督は静かで味わいのある映画に仕立て上げた。
森田芳光監督の時代を見る眼の確かさにあらためて感じ入った次第である。
|