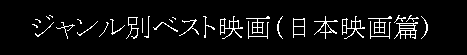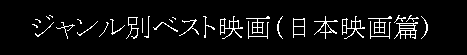われわれ団塊の世代が青春映画といって最初に思い浮かべるのはやはり日活の一群の青春映画であろう。
石原裕次郎が先鞭をつけた日活の青春映画の系譜は、ロマンポルノに移行してもなお形を変えながら続いていった日活得意のジャンルである。
裕次郎以下、小林旭、赤木圭一郎、高橋英樹、浜田光夫、吉永小百合、山内賢、和泉雅子、渡哲也、といった青春スターを輩出し、アクション物とクロスしながら多くの青春映画を量産していった。
当時のこれら青春映画は今日で言うところのテレビのいわゆるトレンディードラマと同様の要素を持っており、当時の若者たちの流行や憧れを担っていた。
東京に代表される都会は今以上に若者たちの憧れの街であり、その憧れを映画が体現し、またさらにそれによって掻き立てられていくという構図である。
当時の地方と都会の格差は現在の日本とアメリカ以上のものといっていいだろう。
そのようななかで情報発信機能としての映画の果たす役割は大きかった。
この時代の中にあって、私たち世代の人間は映画から多かれ少なかれ影響され、刺激を受けてきたのである。
このように量産され続けた日活青春映画の中で特に印象に残る作品をあげるとすれば、石原裕次郎主演の「陽の当たる坂道」(田坂具隆監督)、吉永小百合主演の「キューポラのある街」(浦山桐郎監督)、そして鈴木清順監督の「悪太郎」と「けんかえれじい」といったところがあげられる。
「陽のあたる坂道」は当時の日活が原作として取り上げることが最も多かった石坂洋次郎の小説を映画化した作品である。
これはまさに暖かな春の陽光が射す坂道の上にある瀟洒な洋館が物語の舞台である。
こうした洋館は当時の松竹映画などにはよく登場してくる舞台設定で、思いつくものをあげてみると「大曽根家の朝」「お嬢さん乾杯」「破れ太鼓」(以上 木下恵介監督)「安城家の舞踏会」(吉村公三郎)などがある。
こうした映画の主人公たちは立派な洋館には住んでいるものの「破れ太鼓」の成金社長以外はみな戦争によって没落した家族たちであり、生活に貧窮している。
だが「陽の当たる坂道」の家族の場合はもうすでに戦争は過去のものとなり、今や裕福で恵まれた環境のなかに住んでいる。
そしてそれをリアルに体現しているのが裕次郎の明るくのびやかなキャラクターであった。
彼の育ちの良さと健康的な不良っぽさがこの物語を違和感のない自然なものにしている。
高い教養と経済力を持った父親(千田是也)、いつまでも若く美しい母親(轟夕起子)、若きエリートである医者の兄(小高雄二)、優しい美少女の妹(芦川いずみ)とまさに絵に描いたような理想的な家族である。そして、ただひとり裕次郎演ずる次男だけがはみだし者である。
しかしこのように一見理想的に見える家族にも、それぞれ深い悩みがあることが次第に見えてくる。
結局、それぞれが理想の家族を演じることでかろうじてその均衡が保たれていたのであり、本音で生きる次男の生き方が、壊れそうな家庭の再生を果たす大きな力となっていく。
裕次郎によって演じられたこの陽性の青春は、当時の私たち若い世代にさわやかな印象を残した。
そして、東京にはこんなにも豊かで洗練された生活が存在するのだということに強い憧れと羨望を感じたものである。
一方「キューポラのある街」は、この「陽の当たる坂道」の世界の対極にある家族の物語である。
鋳物の街、川口が舞台のこの映画では鋳物職人(東野英次郎)の子、中学生ジュン(吉永小百合)が主人公である。
不況の影が射す鋳物の街で働くジュンの父親は、永年勤めた町工場をなんの保証もないままある日突然解雇される。
それまで貧しいながらもなんとか生きていた家族は突然苦境に立たされる。
高校進学を夢みていたジュンは、その夢を諦めざるをえない。
そうした貧しい生活のなかで、中学生のジュンが悩み、傷つきながら成長していく姿を浦山桐郎監督は、現実を鋭く見据えた眼で的確に描いていく。
またそれはジュンという少女を中心に据えて、川口という街の人間群像を描こうという試みでもあった。
当時18才の吉永小百合は浦山監督の期待によく応え、多感な中学生の少女を見事に演じきっている。
おそらく彼女の生涯最良の演技ではなかろうか。以後、これを越えた演技を私は知らない。
また浦山桐郎にとっても、この映画はデビュー作であると同時に、生涯最良の作品でもあった。寡作で知られた浦山桐郎は25年の監督生活の間にわずかに10本に満たない作品を残しただけである。「キューポラのある街」につづいて「非行少女」という秀作をつくり、さらに「私が捨てた女」という彼の心情を吐露するような名作もつくっているが、やはり代表作となると、この「キューポラのある街」にとどめを刺す。
女優と監督の作品を通しての幸せな出会いがここにあったといえよう。
「陽の当たる坂道」では羨望と憧れを感じたが、ここでは一転複雑な現実の厳しさを教えられ、しかし同時にそれを乗り越える力強さも教えられ、学校教育では得られない生でリアルな勉強を映画から吸収していたのだということを今にして強く感じるのである。
鈴木清順の「悪太郎」と「けんかえれじい」は私にとって最も印象に残る青春映画の名作である。また鈴木清順の映画のなかでもベストの作品であると考えている。
ここには青春映画が持つエッセンスのすべてがある。
恋があり、けんかがあり、友情がある。悩みがあり、迷いがあり、挫折がある。
喜びがあり、悲しみがあり、笑いがある。
そうした青春のもつ多感な叙情性が旧制中学という戦前のロマンあふれる舞台を背景にして詩情豊かに描かれていく。
直情的で無軌道な男の生き方が、ばかばかしくもおかしいけんか修行の数々によって描かれていくが、一方では暗い世相の影が漂いはじめ、次第に戦争へと突き進んでいく様子も描かれる。
そうした時代背景を巧みに織り込むことによって、単なる青春物語以上の深みが作品に生まれている。
「けんかえれじい」後半部にそうした影を象徴するような印象的なシーンが登場してくる。
主人公たちがたむろする会津の喫茶店に眼光鋭く、しかし一見穏やかな初老の男がひとり閑かにコーヒーを飲んでいる。
店に入ってきた麒六(高橋英樹)は一瞬その男に眼を奪われ、身を堅くする。
けんか修行で身につけた鋭い嗅覚で、なにやら得体の知れない殺気をその男に感じたのである。
だが、その場はそれ以上のこともなく、麒六はいつものようにけんか相手を見つけて去っていく。
そして日記にこう書き残す。
「今まで逢ったこともないような人を見た。一瞬僕は、射すくめられた。彼は笑っていたのに、誰だろう、あの人は」
そしてこの謎がラストの喜多方駅の待合室の号外によって明らかになる。
その男が226事件の思想的指導者である北一輝だったと知るのだ。
「けんかだ、大げんかだ。これを見なきゃ男がすたる」の声に誘われるようにして麒六は敢然と東京へ旅立っていく。
麒六の乗った機関車が猛然と東京目指して走り去っていく。
その映像にかぶさって血潮をたぎらせるような「昭和維新の歌」が流れる。
「果たして麒六の運命やいかに」と思わせる劇的な幕切れである。
そしてうねるように押し寄せてくる時代の波のなかで麒六の次なるロマンを期待させる幕切れでもあった。
果たしてこの先どうなるのだろう、どうしても続きを見てみたいと強く感じたものである。
その期待に応えるように続篇のシナリオが書かれ、シナリオ誌に掲載されたが、残念ながら映画化はされなかった。
翌年、「殺しの烙印」を撮ったことがきっかけで鈴木清順は日活から不当に解雇され、以後10年間、映画を撮ることはなかった。
「けんかえれじい」続編が幻に終わったくやしさと、鈴木清順が作家としての最盛期にまったく映画を作れなかった悲運を考えると、心中まことに苦いものがある。
こうした数々の優れた映画を生み出しはしたが、映画界を襲う斜陽の波は容赦がなく、日活は経営の改善を図るため、昭和四十五年ついに大映と提携して「ダイニチ映配」という会社を設立することになる。
スターは使わず、低予算による寡占化という路線を敷き、この局面を打開しようとする。
このような厳しい状況に陥った時、その混乱の中から不思議と新しい才能や、優れた作品が生まれるということが過去にはしばしばあり、この「ダイニチ映配」時代も同様で、いくつかの傑作、佳作が作られることになった。
そのなかでも特に記憶に残る作品が「八月の濡れた砂」であった。
この映画は、いわゆるシラケ世代の先駆けとなった作品である。
70年安保と学園紛争の終焉によって学生たちの社会変革への熱がさめてしまい、何をやっても満足できない状況が支配的になっていった。
目的を失ったエネルギーは行き場を失って次第に無気力な雰囲気が社会を覆い始めていった。
そうした時代の気分を藤田敏八は、この作品で見事に映像化してみせたのである。
藤田敏八は、デビュー作「非行少年、陽の出の叫び」以来、一貫して若者を主人公にした映画を撮り続けており、青春映画の秀作を数多く作り出している。
「ダイニチ映配」時代のものとしては「八月の濡れた砂」以外にも「野良猫ロック、ワイルドジャンボ」「新宿アウトロー、ぶっ飛ばせ」といったアナーキーな作品を撮っている。
また日活がロマンポルノに移行してからも「赤ちょうちん」「妹」といった歌謡映画の佳作や「帰らざる日々」「十八歳、海へ」「もっとしなやかに もっとしたたかに」などの印象深い作品を作っている。
どの映画も青春の影の部分に眼を向けたものであり、傷つきやすく不安定で、それでいてしたたかな一面もある若者の生き様を独特の醒めた眼で描いている。
そうした意味からも青春映画を考える場合には、どうしてもはずせない監督のひとりなのである。
近年は作品数も減り、監督としてよりもむしろ俳優としての活躍のほうが多くなり、なかには鈴木清順の「チゴイネルワイゼン」の主役のように強く印象に残るものもあった。
だがやはり彼の真骨頂は映画を撮ることであり、俳優として糊口をしのぐ姿はどうしても仮の姿にしか見えなかったのである。
そしていつか監督業を再開することを秘かに待望していたのであるが、過日突然に亡くなってしまった。
まさに虚を突かれたという感じの死であった。
まだまだ新しい作品を観てみたいと思っていただけに残念である。
これらの優れた作品群とともにいつまでも記憶にとどめておきたいと強く思う。
以上が日活の青春映画の系譜であるが、その路線の始まりともいえる「太陽の季節」や「狂った果実」といった太陽族映画、すなわち石原慎太郎が描いた戦後世代の新しい姿を、さらに押し進めた形で追求しようとしたのが大島渚監督の「青春残酷物語」であった。
無軌道に生きることで未来を切り開こうとする若者が、結局は敗北していくしかなかった無残な姿を大島渚は鮮烈な色彩と映像で殴りつけるように描いている。
まさに彼のなかで貯め込んでいたエネルギーをスクリーンというキャンバスに投げつけたような力強さを感じさせる作品であった。
石原慎太郎の「太陽の季節」の出現に衝撃と共感を感じた大島渚は、戦争を自ら体験しなかった「純粋戦後派」ともいうべき世代、すなわち自分自身を含めた戦後世代の大いなる代弁者をそこに見い出したのである。
そしてその反社会的な内容に、自ら「純粋戦後派」と名付けた者たちの栄光を見、それこそが自分たちの進む道だという確信を得たのである。
そうした方向性から生まれた「青春残酷物語」はまさに「価値紊乱者」の一員として同じ戦列に加わることで、その栄光をともに担おうとした作品であった。
そして、目論見通り社会の非難と賞賛を同時に受けることになったのである。
その反倫理的で鮮烈な映像によって大島渚は一躍時代の寵児となり、これに続く数々の問題作を精力的に作り出していくことになるのである。
1960年に作られたこの映画は、そういった意味でも激動の六十年代を先駆ける映画といえるものであり、またこれがきっかけで松竹ヌーベルバーグという新しい流れが生まれることになったわけで、その記念碑的作品としても長く記憶されるべき映画であろうと思う。
さらにこれは後に続く数多くの青春映画に強い影響を与え続けた作品でもある。
1968年からはじまったATG(アート・シアター・ギルド)製作の一千万円映画から数多くの名作が誕生したが、そのなかにも数々の優れた青春映画があった。
まず先陣を切って登場してきたのが羽仁進監督による「初恋・地獄篇」であった。
この作品は羽仁進と寺山修司が共作でシナリオを書いている。
異質とも思えるふたりの組み合わせが逆にお互いを触発し補い合う形となって、見事な青春映画として結実している。
幼い頃に父親を亡くし、母親は再婚して彼のもとを去って行き、今は義理の両親のもとで暮らしているという寺山修司の生い立ちとどこか似た少年が主人公である。この愛情欠損少年シュンとヌード・スタジオで働く少女ナナミのぎこちない初恋が猥雑な都会の風景のなかで描かれていく。
町で知り合ったふたりがホテルに行く場面から映画は始まる。
初めてのシュンは気後れしながらナナミについてホテルに入って行くが、案の定、性的に不覚に終わってしまう。
屈辱的とも思えるこうした出来事が何気ない日常風景として淡々と描かれていく。
こうした出来事は盛り上げようと思えばいくらでもドラマチックに盛り上げられる種類のものだが、この映画ではそうした方法はとらない。
特別な出来事ではなく(主人公シュンにとっては決して軽い出来事ではないにしても)、ごくあたりまえでありふれた日常風景として描かれる。
意外と現実とはそうしたもので、深く傷ついたり動揺したとしても、劇的に悩んだり悲しんだりというような行動をとることなどほとんどないのではなかろうか。
記録映画出身の羽仁進はそうした醒めた眼で現実を見据えている。
そしてオールロケーションによるドキュメンタリーフィルムのような感覚でこの物語を捉えていく。
裸でベットに横たわるふたりは、まるで子供同士のように無邪気であり、性的には不覚に終わったが、深刻ぶることもなく自分たちの身の上を話しあう。
ここからカメラはシュンの過去へと逆のぼっていき、様々な幼児体験が語られていく。
過去と現在のシュンをからませながら、複雑に屈折した現実が浮かび上がっていく。
そしてそこに様々なシークエンスを重ねることで迷宮のような世界が作り上げられていく。例えば性格の暗いシュンを明るくさせようと養父が彼を「笑う会」に入会させたり、さらにその養父がホモで執拗にシュンにいたずらを仕掛けてきたり、またテレビによる東大入学者へのインタビュー場面を登場させたり、「寂しい人たちのためのレコード」という奇妙なレコードを街頭販売する男が出てきたり、シュンの友達の「初恋」という8ミリ映画が上映されたり、さらにシュンが近所の幼女となぞなぞ遊びにふけったり、その遊びの最中に突然母親との不思議な思い出を思い浮かべたりといった寺山好みの世界が挿入されることで複雑怪奇な現実が浮かび上がってくるという仕掛けがなされている。
こうした過去と現在の地獄めぐりによって、次第にシュンのリビドーが明らかにされていき、それとともにシュンは少しづつ大人の世界へと足を踏み入れていくようになるのである。
こうした通過儀礼を経ることで再びシュンとナナミは巡り会うことになるのだが・・・・・・。
男が大人になっていく過程はいわば小さな地獄めぐりの旅でもある。
人知れず思い悩む少年が次第に殻を破って脱皮していく様子が猥雑な背景のなかで描かれることで逆に澄んだ叙情性を強く感じる。
そこにわれわれと共通の青春を見、身近な共感を感じる。
ドキュメンタリー風の映像や一般公募によって選んだ主役ふたりの初々しさがまたよりいっそうこの物語を身近でリアルなものにしているのである。
アートシアター新宿文化でこの映画を見終わった後、映画の熱気を抱えたまま新宿の街をシュンの地獄めぐりのように彷徨ったことを今も鮮やかに思い出す。
「初恋・地獄篇」に続いて、ATG作品での青春映画の名作に黒木和雄監督の「祭りの準備」と東陽一監督の「サード」そして根岸吉太郎監督の「遠雷」がある。
まず黒木和雄監督の「祭りの準備」である。
この映画の原作とシナリオは、中島丈博が書いており、彼の自伝的色彩の濃い作品になっている。
中島丈博の故郷、高知県、四万十川流域の町、中村市を舞台に彼を思わせるシナリオ作家志望の青年、楯男(江藤潤)を主人公に、その悶々とした日常を、彼とその家族、そして身辺のどうしようもないしかし愛すべき人たちをからませながら描いた映画である。
楯男は信用金庫に勤める実直で真面目な青年であるが、彼も青年期特有の様々な悩みを抱えており、その現実と理想のギャップに日々悩まされている。
また父親(ハナ肇)は家庭を顧みず、自分勝手に女をつくり、祖父(浜村純)は隣家の頭の狂った若い娘(桂木梨江)を夫婦のように面倒をみているというふうで、家庭的にも悩される問題が多く、若い彼の手には余る状態である。
そうした現実に我慢がならず、なんとかそこから抜け出したいと思いながらも、母親(馬淵晴子)のことを思うとそれもできず、身動きできない日常にうんざりしている。
そんな彼が唯一真面目に話が出来る相手が恋する幼なじみの涼子(竹下景子)である。
しかし、結局はそれも彼の片想いに終わってしまい、それをきっかけに故郷を出ていく決意をする。
ひとり寂しく旅立つ彼を、犯罪を犯して逃亡中の隣家の遊び人(原田芳雄)が励まし見送るラストシーンにはすがすがしい感動がある。
恥多き青春、悩み多き青春、そしてそこからの旅立ち、そうした青春期特有の物語を青臭いひとりよがりの物語として描くのではなく、あけすけの欲望を持った人間臭い人物たちを配することで厚みのある見事な青春映画に仕上げている。
ここには甘い感傷やうすっぺらな人間描写はない。
多面的で複雑な人間たちが生き生きと動いており、土着の人間のしたたかさが楯男の純情な青春と好対照に描かれており、その対照の妙がこのドラマをよりいっそうダイナミックな色彩のものにしている。
そしてこのうら寂しい旅立ちが、いかにも彼の青春に似つかわしい。
青春に栄光などはなく、惨めで切ない思いがあるばかりである。
「サード」は軒上泊の小説「九月の街」を寺山修司が脚色し、東陽一が監督した映画である。
高校で野球部の三塁手をやっている主人公(永島敏行)はサードというあだ名で呼ばれている。
このサードがクラスメートの数学の得意な男子生徒(吉田次昭)とふたりの女子生徒(森下愛子、志方亜紀子)と組んで秘かに売春を始めようとする。
その理由が「みんなでどこか大きな町へ行こう」という他愛もないもので、そのための資金稼ぎとして選んだのが手っ取り早く金の稼げる売春というわけである。
だからといって彼らが落ちこぼれのどうしようもない不良というわけではなく、スポーツも勉強も人並みにこなすごくありふれた生徒たちなのである。
しかしなにかしら彼らの中に判然とはしない正体不明の鬱屈が巣くっており、目的もないまま住んでいる町からの脱出を夢見ているのである。
しかし、その目論見も客のやくざとトラブルをおこし、サードが誤ってそのやくざを殺してしまったことから頓挫してしまう。
殺人を犯したサードは少年院に入れられる。
そしてそこでの生活が様々な院生たちとの交流を通して克明に描かれていくことになる。
主人公のサードを映画出演2作目の永島敏行が演じているのだが、この映画の成功は彼の存在ぬきにはあり得なかっただろうと思わせる好演である。それほど適役であり、存在感がある。
実際に彼は学生野球の選手であり、映画デビューのきっかけも水島新司の野球漫画「ドカベン」映画化のためのオーデションからというものであった。
けっして演技がうまいわけではないが、他の俳優にはない朴訥で硬質ないい味を持っており、また野球のユニフォーム姿がこれほど見事に似合う俳優もほかにはいないだろう。
さらにサードという若者になりきってグランドを駆けめぐる姿には自分で自分を持て余す青春の得体の知れないエネルギーと哀しみを感じさせるものがある。
これによって70年代を生きる青春のある典型を見事に体現しているのである。
さてここまで書いてきて気づいたことだが、先の「初恋・地獄編」の羽仁進と「祭りの準備」の黒木和雄とこの「サード」の東陽一はともにドキュメンタリー映画の老舗である岩波映画出身者であり、羽仁進が「初恋・地獄編」を寺山修司のシナリオで撮ったように、東陽一も「サード」を寺山修司のシナリオをもとに映画化をしている。
また羽仁進は「不良少年」という少年鑑別所を舞台にした映画で劇映画のデビューを果たしており、東陽一の「サード」との共通性を感じる。
こうした符合がなにを意味するのか、またそこに意味を見いだすことに必然性があるものなのか、私には判断しかねるが、しかし興味深い共通性であることには違いない。
おそらくこうした身近な関係のなかで、お互いの作家精神を触発しあっていたのではないかと想像する。そしてそうした事実に私のような映画ファンはいささかスリリングな興味をおぼえるのである。
さて次は「遠雷」である。
この映画は日活のロマンポルノで、すでに何本かの映画を監督していた若き映画監督根岸吉太郎の初の一般向映画である。
原作は立松和平の小説で、東京近郊の農村でビニールハウスのトマト栽培に精をだす青年の物語である。
この青年を「サード」と同じ永島敏行が演じており、サードに負けない適役であり、生き生きとした演技は強く印象に残る。
先にあげた「祭りの準備」の青年と同様にこの主人公の家庭でも父親(ケーシー高峰)がだらしがなく、女を囲っては家に寄りつかず、永島敏行が一家の中心になって働いている。
しかしそうしたことは少しも意に介せず、ちゃんと地に足をつけた自分流の生き方をしており、「祭りの準備」では家族の問題に悶々として思い悩む主人公であったが、こちらはもっと逞しく、ドライに割り切った考えを持つ青年である。
そして近所の悪友たちとも適当に遊び、時には近くの団地の主婦の浮気の相手をしたり、見合い相手の女性(石田えり)とモーテルに直行したりと奔放な面も持ち合わせている。
まことに現代的な農業青年の造型であり、都会地の農家に意外にいそうな人物である。
そしてこの主人公が見合い相手の女性と結婚式をあげた夜、殺人を犯して逃亡中の遊び仲間の男(ジョニー大倉)が秘かに彼に会いにやってくる。
結婚式を抜け出してビニールハウスで男に会い、彼の殺人へと至る告白を聞くシーンはこの映画のクライマックスであり、数ある青春映画のなかでも出色の名場面となっている。
ジョニー大倉の涙ながらの告白は青春の悲痛さとやるせなさを感じさせ、まことにサスペンスフルである。
彼は、いわば永島敏行の影の部分を担ったような存在であり、もしかしたらふたりの立場が入れ替わっていたかもしれないというような関係である。
青春とはおそらくこうした危うい綱渡りのように不安定なものであり、だからこそいっそう輝いて見えるものなのであろう。
男の告白を彼はまさに自分のことのように悲痛な思いで聞いたにちがいない。
そして男と別れた後、彼は結婚式場に舞い戻り、自らの青春への訣別と感傷を吹っ切るように、桜田淳子の「私の青い鳥」を振り付けをつけながら懸命に歌うのである。
一見コミカルで唐突な行動にこめられた決意と悲しみは胸を打つものがある。
「潮騒」
森谷司郎監督は自然と人間の関わりを描くことがうまい監督である。
そうした作品に「漂流」「八甲田山」「海峡」などがあるが、この「潮騒」でもその手腕をいかんなく発揮して自然のなかで素朴に生きる人々を美しく描いており、過去何度か映画化された「潮騒」のなかでも最も優れた作品になっている。
また原作の味わいをいちばん色濃く表現し得た作品でもある。
三島由紀夫の原作はギリシャ神話におけるような自然と人間の美しく理想的な在りようを若い男女に託して描いており、いわばおおらかな人間讃歌と呼べるものである。
森谷司郎は、この主演の男女をまったくの素人を使うことでその素朴でおおらかなイメージを表現しようとした。そしてその試みは見事に成功している。
過去映画化された作品は、1954年に東宝で谷口千吉監督による久保明、青山京子主演によるもの、1964年に日活で森永健次郎監督、吉永小百合、浜田光夫主演によるもの、さらに1975年には東宝映画2度目の映画化で山口百恵、三浦友和のコンビによるもので、この時は西河克己監督がメガホンをとっている。
1985年にも山口百恵版に引き続きホリプロ企画による堀ちえみ、鶴見辰吾主演で小谷承靖監督によって撮られている。
結局、都合4回の映画化がなされているのだが、森谷司郎監督による「潮騒」はそのどれとも違って素朴で神話的な色彩の濃い作品になっている。
他の作品はいわばアイドルを強力に売り出そうという意図で撮られたものであり、この題材のなかでいかに彼女らの魅力を引き出すことができるかというところに力点が置かれたものである。
そうした作品にも、それなりの魅力があるが、やはり原作の持つ神話的世界からは遠いものがあると言わざるをえない。
しかし、この森谷司郎監督描くところの「潮騒」には明らかに神話的豊饒の世界があり、明るく美しいある種、理想の人間の生活が描かれているのである。
そしてそれをより強く現実のものとして納得させられるのは、若いふたりの初々しさであり、本物の島の漁師といってもおかしくないような陽に焼けた健康的な肉体なのである。
プロの俳優にはとうてい出せない新鮮な情感が若いふたりの手垢のついていない素朴な演技によって十二分に表現されているのである。
若く健康的な理想の恋愛が美しい島の自然のなかでなんの衒いもなく繰り広げられる。
それはまぶしいほどの輝きに満ちており、わたしたちの心を豊かで幸せな気分にしてくれる。
これは隠れた名作といえる作品である。
「Aサインデイズ」(崔洋一監督)
沖縄のロック歌手、喜屋武マリーをモデルに、ベトナム戦争当時の沖縄のロック・バンドのメンバーたちの青春を描いた作品である。
「Aサイン」というのは沖縄での米軍相手の酒場の許可証のことで、ベトナムの前線で戦う若い米軍兵士たちを相手に、その殺伐とした雰囲気のなかで彼らはロックを演奏していた。
そこで鍛えられた彼らのロックは生半可なものではなく、深くアメリカと結びついた本物のロックであった。
この時代、日本国内ではアメリカのベトナム戦争遂行に強く反対をし、各地で反戦運動が過激に繰り広げられており、また全国の大学は学園紛争で大揺れに揺れていた。
この騒然とした時代のなかにあって私もひとりの学生としていた大学に通っていた。
そして毎日のように繰り広げられる反戦デモや学生集会に時たま参加することがあるというごく一般的な学生のひとりであった。
そんな時代に一方ではそうした学生たちとは遠く離れたこの映画のような青春も確実にあったということである。
たしか1970年の秋だったと思うが、私は沖縄を訪れている。
紛争で荒れた大学はロックアウトによって閉鎖されており、期間の定まらない長い休校が続いていた。
突然もらった長期の休暇を私は割りのいいアルバイトをして過ごしていた。そして当時の私にとっては思わぬ大金を手にしたのである。
私はその金で当てのない旅行にでかけることにした。そしてその旅行先のひとつが沖縄だったのである。
返還前の沖縄はまだアメリカの匂いが充満し、加手納基地にはB52の巨体が黒く不気味に横たわっていた。
また那覇の歓楽街にも足を踏み入れてみたが、壁を原色のペンキに塗られた酒場の強烈な佇まいに一瞬恐れをなした。
まったく馴染みのない異境ともいえる風景であった。
今思うとそこがこの映画の舞台であり、彼らの青春もここで息づいていたのである。
そう考えると不思議な感慨が湧いてくる。
また、そうしたことからもこの映画を特別の親しみをこめて観ることになったのである。
青春映画と云えば今や青春教の教祖のような存在である大林宣彦監督をあげなければならない。
自らを「ヴェテランの少年」と呼ぶ大林宣彦監督は、初期のプライベート・フィルムの時代から自らの青春への回帰とノスタルジーを大きなテーマとして作品を撮り続けている。
大学時代に、あるプライベート・フィルム・フェスティバルで彼の作品「EMOTION=伝説の午後=いつか見たドラキュラ」を観る機会があった。
映画の名場面をコラージュ風にちりばめた詩的な作品であった。映画へのオマージュを自らの青春とつなぎ合わせて抒情的に表現したもので、私は初めて観るプライベート・フィルムなるものの存在をある種の驚きと感動をもって受けとめたことを思い出す。
この当時、彼はすでにプライベート・フィルムの世界では高い評価を受けており、その世界では知る人ぞ知るといった人物であった。
しかしそうした動きもごく一部のマニアだけの世界であって、次第にその情報も訊かれなくなっていった。
大林宣彦監督は、その後コマーシャル・フィルムの世界に活動の場を移し、後年数々の話題性のあるコマーシャルフィルムを作り続けている。
そして10年の後、1977年に初の劇場用映画「HOUSE ハウス」を撮って商業映画の世界に登場してくる。
そして引き続き「ねらわれた学園」「転校生」「時をかける少女」「さびしんぼう」「ふたり」「青春デンデケデケデケ」「はるかノスタルジィ」といった数々の青春映画の秀作を撮っていくのである。
どの作品も青春前期にある少年、少女たちの微妙な心理を描いた作品である。
そしてそれをプライベート・フィルム出身の作家らしい独特の映像感覚と現代的感性で描くことで叙情性あふれた素晴らしい作品になっている。
なかでも私がとくに好きな作品ということになると「転校生」と「青春デンデケデケデケ」ということになろうか。
まずはじめは「転校生」である。
この映画は「時をかける少女」「さびしんぼう」とともに尾道三部作としてよく知られた作品である。
なぜ尾道かといえば、そこは大林監督の生まれ育った故郷であり、青春の回帰とノスタルジィをテーマとして映画を撮る大林監督としてはどうしてもこだわらざるをえない場所になっている。
また、海と山に恵まれた坂の多いこの町は古い町並みがたくさん残っており映像的にも恰好の被写体になっている。
そんな味わいのある町で尾美としのり演じる普通の高校生がごく普通の高校生活を送っているが、不思議なことにある時、同級生の少女(小林聡美)と突然身体が入れかわってしまうという事件が起きる。
このSF的な事件をきっかけに起こる騒動の顛末が喜劇的な味付けを加えられながら描かれる。
美しい海と山に囲まれた尾道の風景のなかで、どこにでもいそうな高校生の青春の1ページがこうしてみずみずしく描かれるのだ。
実際にはあり得ないことがもし現実に起これば、人はどういう反応を示すだろうかといったふうなファンタジックな設定の物語はハリウッド映画ではしばしば登場してくる路線である。
例えば、思いつくところをあげてみれば、自殺しようとする主人公の前に天使が登場し、それを思いとどまらせようとする「素晴らしきかな人生」や、事故死したフットボールの選手が別な人物の身体を借りて蘇り、痛快な活躍をする「天国から来たチャンピオン」、またこれと同様のパターンで、死んだ夫が若者の身体を借りて蘇る「ワン・モア・タイム」そして「ルーク」では犬の身体を借りて蘇り、「ゴースト ニューヨークの幻」では霊媒師にとりついて蘇ってくる。
さらに「愛が微笑む時」ではバスに乗り合わせて事故死した乗客全員が幽霊となり、ひとりの青年を介してそれぞれの家族に会いにいく。
こうしたSF的荒唐無稽な状況設定の物語は日本映画ではあまり馴染みのないものであり、思い浮かぶ作品は少ない。
しかしエンターテインメント性を重要な要素と考えるハリウッドにおいては、こうした荒唐無稽な物語も違和感なく受け入れられるようで(おもしろく興業的に当たりそうとなればどんな物語でもOKといった明快な伝統)数多くの作品がある。
ハリウッド映画の影響を強く受け続けてきた大林監督にとっては、従来の日本映画よりもこうした傾向の映画に親しみをおぼえるようで、自らの作品でも自然とこうした設定を施したものが多くなるようだ。
先にあげた作品のなかでも「青春デンデケデケデケ」以外はすべてそうした種類の物語であり、この他にも例えば「HOUSE ハウス」「漂流教室」「異人たちの夏」「水の旅人 侍KIDS」「あした」など、ほとんどの作品が異次元や幽霊と交感するSF的物語になっている。
しかしSF作品というわけではなく、あくまでも基本はリアルな日常の物語であり、そこに潜む人生の喜びや悲しみをあぶり出すための手段として、非日常的設定をするという手法である。
そしてその設定が物語の流れのなかにごくあたりまえのものとして溶け込んでおり、不自然さは感じない。
むしろそのあり得ない話によって日常を越えた物語世界へと導かれてゆき、映画的な魅力に酔わされるのである。
「転校生」においてもそれは同様で、身体が入れ替わるという事件さえ起きなければあたりまえの生活の中であたりまえのままで終わったかもしれない主人公の少年と少女がその身にふりかかってくる難問に悪戦苦闘することになる。
そしてその騒動によって少しだけ人生の扉が開きはじめ、それまで無縁であった人生の醍醐味をほんのわずかだけ味わうことになるのである。
誰にも知られずふたりだけで密かに味わった奇妙な人生の瞬間。
その時間への熱い想いを胸にもとの身体に戻った少年がトラックに乗って転校していく。
それを同じ思いを抱えた少女がただひとり追いかけていく。
そして遠ざかっていくふたりがそれぞれに向かって熱い別れの言葉を交わし合う。
「さよなら、おれ」「さよなら、わたし」
それはお互いの身体がひとときの間入れ替わってしまったことへの親しみを込めた別れであると同時に、少年と少女の自らの青春前期への別れでもあり、二度と帰らない時間への苦く切ない惜別でもある。
トラックに乗った少年が回す8ミリカメラのなかの次第に小さくなっていく少女の姿がスクリーンに映し出されて映画は終わる。
その粒子の粗い白黒画面が二度と戻らない時間の懐かしい切なさを見事に表現している。
これは映画史に残るにちがいない素晴らしいラストシーンのひとつである。
「青春デンデケデケデケ」は芦原すなおの直木賞受賞作の映画化作品である。
香川県出身の芦原すなおは、自身の青春回想記ともいうべきこの小説の会話文をすべて讃岐弁で書いており、それによって作品に独特の味わいをもたせており、登場人物たちも生き生きとしたリアリティあふれたものになっている。
大林監督も映画化に際して、そうした味わいを大切にするために出来るだけ讃岐弁のセリフを使って撮影することを考えた。
そこで出演者たちをロケ地の観音寺市に先発させ、そこでの生活はすべて讃岐弁を使うことにして、できるだけ地元の生活に溶け込ませようとした。
そして頃合いを見計らってさりげなくカメラを廻すという撮影をするのである。
まるで出演者たちがそこで長年住んでいるような自然さがこうした撮影法によって実現できたのである。
町の住人になりきった俳優たちとカメラが廻っていることに気づかず普段の姿のままで登場してくる町の人々が画面の中で違和感なく共存しており、観音寺という町の日常を巧みに切り取ることに成功している。
こうした撮影法は、「廃市」の撮影でも使われた手法であり、ロケ地柳川の古く落ち着いた情緒がそれによって自然に美しく表現されている。
この時の経験が「青春デンデケデケデケ」でも十二分に生かされたわけで、町の微妙な肌合いを画面に見事に定着することができたのである。
そして単なるロケ地というだけではないその土地ならではの味わいが生まれている。
こうして作られた映画「青春デンデケデケデケ」は、香川県出身の私にとっても人一倍強い思い入れを感じさせるものになっている。
また芦原すなおが私と同年齢ということも、この映画を身近なものに感じさせる大きな要素になっている。
共通の時代を共通の場所で過ごしたシンパシーである。
わが青春とだぶらせて深く共感することになった。
ひととき高校時代にひきもどされ、幸福な時間を味わえたのである。
さて最後に今の時代を代表する青春映画の秀作2本をあげることにする。
岩井俊二監督の「Love Letter」と北野武監督の「キッズ・リターン」である。
この二人の監督はいまや時代を代表する映画監督といっていいだろう。
MTV作りからテレビ映画の世界に足を踏み入れた岩井俊二監督は、フジテレビで撮った「打ち上げ花火、下からみるか?横からみるか?」でテレビドラマにも関わらず日本映画監督協会新人賞を受賞し、早くからその才気が注目されていた。
その岩井俊二監督が劇場用映画として撮った第1作目の作品がこの「Love
Letter」である。
この映画によってその才能が本物であることを証明し、一気にファンを獲得することになる。そしてこの後、「FRIED
DORAGON FISH」「PICNIC」を経て、「スワロウ・テイル」を作ることで熱狂的な支持を集めるようになった。
いま最も注目を浴びている若手監督のひとりであり、映画の世界のみならず現代のビジュアル文化の旗手ともいえる存在である。
また北野武監督も同様で、それに負けず劣らず注目される存在である。
先日、第54回ベネチア映画祭で新作「HANAーBI」がグランプリを受賞し、いまや国際的に話題を集める映画監督になったわけで、あるいは岩井監督以上の注目度と言っていいかもしれない。
とにかくこのふたりが現在の日本映画を代表する映画監督であることは間違いのないところである。
さて、そのふたりの青春映画についてである。
まずは、岩井俊二監督の「Love Letter」から。
この映画は小樽と神戸を舞台に、不思議な糸に繋がれたふたりの女性(中山美穂の二役)の青春を巧みにダブらせて描いた映画である。
ポーランド映画「ふたりのベロニカ」(監督・クシシュトフ・キェシロフスキ)に触発されて作った作品で、遠く離れた土地に住むうりふたつの女性が主人公という発想以外はキェシロフシキ作品とはまったく別の物語になっているが、その詩心の豊かさには共通したものがあり、ともに美しく端正な作品となっている。
何のつながりもないと思われるふたりの女性がほんのわずかな一本の糸からその過去の思いが蘇り、鮮やかな青春の一ページが掘り起こされていく。
複雑に入り組んだ糸を手さばきよく選り分けることで、過去のささいな出来事が重要な意味を帯びてくるといった展開の巧みさは熟達のストーリーテラーのごとき腕の冴えであり、思わず身を乗り出して映画の世界に引き込まれていく。
性急に事を運んでいくことのないその抑制された語り口は完成された大人の語り口であり、岩井俊二監督の並々ならぬ才気を感じさせられる。
現代の見事な青春映画と呼べる作品である。
さて次は北野武監督の「キッズ・リターン」である。
北野武監督、すなわちお笑いタレント、ビートたけしが映画の演出にはじめて手を染めたのは1989年に松竹で製作された「その男、凶暴につき」であった。
この映画は当初、深作欣二が監督をする予定であったが、スケジュールが合わず急遽主演のビートたけしにその役目がまわってきた。
当初はお笑いタレントビートたけしの人気にあやかった客寄せのための起用だろうということで軽く見られていたようだが、撮影が進行するにしたがって周囲の見る目が変化していった。
撮影現場のスタッフはいわばくせ者揃いの職人たちぞろいで、彼らの常として上に立つ者の値踏みをしながら仕事をするという習性がある。
こうした習性は考えてみれば映画の世界だけに特有のものではなく、集団で仕事を行う場合には多かれ少なかれ常に付いて回る問題であろう。
使われるスタッフはその技術に秀でていればいるほど経験と技術には尊大なほどのプライドを持っているもので、生半可なことでは思ったようには動いてくれない。
ましてや上に立つ者がズブの素人となれば、なにおかいわんやである。
だがひとたび彼らの値踏みにかなった場合にはその能力の限りの仕事をし、支えてくれる。
そして両者が馴染み始めるとスタッフたちは監督の手足となって動き始め、それによって計算され尽くせないような芸術的効果も生まれてくるようになる。
ここに総合芸術としての映画の醍醐味があり、集団的な創造作業のおもしろさがある。 こうした現場の事情を背景にビートたけしが初めて監督としてメガホンをとったわけだが、いかにビートたけしといえども様々な軋轢と葛藤があっただろうということは十分に想像できる。
そして見事にそれをクリアしたわけで、作品の出来がさらにそれを補完することになったといえよう。
以後彼は映画監督北野武として一定のペースで映画を作り続けることができるようになる。
そして第6作目に作った作品がこの「キッズ・リターン」であった。
いまや北野武はスタッフたちを自分の手足のように使える立場にある。
それだけの実績と経験を積んだわけで、一時期もてはやされた異業種監督というブームのなかからいまだに映画を撮り続けることができているのは北野武監督ひとりという事実は重い。
そして映画的才気はますます磨かれ、この「キッズ・リターン」のような青春映画の名作を作り出すに至るのである。
落ちこぼれたふたりの高校生がそれぞれ違った道(一方はプロ・ボクサーを、もう一方はやくざの幹部を目指す)を歩き始めるが、まわりまわって結局は同じような所(どちらの夢も実現しない)にたどり着く。
再会したふたりが学校のグランドで昔のように自転車の二人乗りをして走り出す。
「おれたち、もう終わったのかな」
「ばか野郎、まだ始まっちゃいねえよ」
そうなのだ、「まだ始まってもいない」のだというこの言葉に多くの人間が勇気づけられたのではなかろうか。
人生はこれからだ。そう思うことで不思議な優しさと感動がわいてくる。
そして、これは北野武監督自身の決意と再生を目指す言葉でもあるに違いないのだ。
<1998年>
|