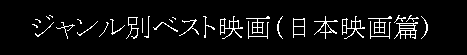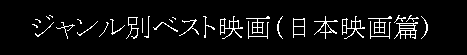ミステリーやアクション映画とは区別して、ちょっと危ない犯罪を扱った作品群から選んでみようと思う。
このジャンルの映画にはキラリと光る良質の作品が多く、映画通に好まれるものが少なくない。
まず、大島渚監督の「白昼の通り魔」がある。
佐藤慶が頭を丸坊主に刈って、異様な風体の婦女暴行犯を演じて迫力がある。
映画におけるキャスティングの重要性はシナリオの優劣に次いで作品の出来を左右する大きな要素になっている。ましてや犯罪者のように心に暗闇を抱え持つ人物を演じる場合、その重要性はさらに大きなものになってくる。存在感のある俳優によって演じられることでリアリティーある人物の造型ができあがり、それによって映画全体のリアリティーが深められる。
この「白昼の通り魔」における佐藤慶はまさにそうした存在感のある俳優であり、彼のキャスティングによってこの映画の出来がある程度決定したといっていいだろう。
大島渚が彼のほか戸浦六宏、小松方正、渡辺文雄といったひとくせある個性的な俳優を好んで使うのもすべからくそうした理由からであり、繰り返し同じ俳優を使うことでより自分独自の世界を表現しやすくなってくる。
またスタッフにおいても同様で、自然と同じメンバーによる集団ができあがることが多い。
よく知られたところでは、小津安二郎と笠智衆やカメラマンの厚田雄春、そしてシナリオライターの野田高悟。
黒澤明と三船敏郎や作曲家の早坂文雄。
溝口健二と田中絹代、シナリオライターの依田義賢。
新藤兼人と乙羽信子と殿山泰司。
今村昌平と小沢昭一、北村和夫、露口茂、北林谷栄。
山田洋次の「男はつらいよ」シリーズなどもそうした例のひとつであろう。
また最近では周防正行と竹中直人、また大林宣彦と尾美としのり、根岸季衣、岸部一徳、入江若葉などといった例もある。
集団でものを作る場合、現場の和やすばやい意志疎通といった人間関係が非常に重要な要素になってくる。この基本が崩れてしまってはいいもの作りは不可能なわけで、自然と気の合う者同士が徒党を組むということが多くなり、同じメンバーでの組み合わせができあがってくる。そして監督は自分の意志を素早く察知するスタッフ、キャストによってスムーズに作品作りを進めていくことができるようになる。
「白昼の通り魔」においてもそうした機能は遺憾なく発揮されているわけで、特に佐藤慶の異様な迫力がこの映画の悪魔的な魅力を倍加させる大きな力になっている。
大島渚監督にはこの他にも「絞死刑」や「少年」のような犯罪を扱った優れた映画が多くあり、「犯罪」という反社会的な行為が彼の創作意欲を強くかき立てる大きくかつ重要な題材になっている。
彼に限らず「犯罪」は表現者の興味を惹きつけてやまない世界である。
そこには赤裸々な人間の本質が極端な形で現れてくる。
そしてその非日常性が映画世界を奥深い広がりのあるものにする。
大島渚監督同様「犯罪」に強く執着している監督に今村昌平がいる。
彼の「赤い殺意」も婦女暴行の強盗犯(露口茂)とその被害者の主婦(春川ますみ)のぬきさしならない関係を重厚に描いた傑作である。
執拗につきまとう犯人とそれを避けようとする被害者の力関係が物語の進行に従って微妙に入れ替わってゆき、主人公の主婦が次第に力強い女に変貌していくプロセスが重い笑いを伴ったリアリズムで語られていく。
オールロケーションで同時録音という今村昌平のこだわりの撮影方法がこの映画を圧倒的なリアリティーと迫力あるものにしている。
いわばドキュメンタリーの手法であり、「人間をまるごと描く」今村監督にとってそれは現実をつかみ取るための必然の手法といえよう。
そして姫田真佐久の技術を駆使した映像が素晴らしく、圧倒的な迫力で迫ってくる。
古い因習と薄っぺらな常識に縛られた女が、次第にたくましく自立していく物語は、今村昌平の得意とする世界であり、主人公の愚鈍でたくましい女を春川ますみが好演している。そして重量感あふれる彼女の肉体が、この物語のリアリティーをさらに確かなものとしている。
また西村晃が吝嗇で口うるさい夫を憎たらしいほど絶妙に演じている。
図書館に勤務する小心だが、欲望の強い、それでいてケチな役人、妻の毎日の買い物にもいちいち目を通しては無駄遣いがあると厳しく責めるといった男を類型におちいらずいかにも身近にいそうな人物として演じている。
そしてその小心翼々たる男が実は裏を返せば女房の懐の中で甘え切っており、愚鈍で従順に見えた女房が次第にしたたかな生命力の強さを発揮し始め、しぶとく一家の中心になっていく様子が入念に描かれていく。
小柄な西村晃と大柄な春川ますみの対照の妙がそんなふたりの関係を視覚的に象徴していておかしい。
さらに犯人役の露口茂が心臓に持病のあるストリップ小屋のトランペット吹きという孤独な男を好演している。寄るべない流れ者の空虚さを埋めようと春川ますみにしつこくつきまとい結局は心臓の発作で死んでしまう。
今村映画の男たちはたいていがこのように自滅してしまうか、女にいいようにしてやられてしまうのが常である。
そして女はいつの間にかその存在を確かなものにしてしまい、ずぶとく生き抜いていく。
まさにこれこそが自然界の摂理なのだと言わんばかりである。
同じく今村昌平が犯罪者を描いた秀作に「復讐するは我にあり」がある。
この映画は佐木隆三の直木賞受賞の同名小説の映画化作品である。
実在の連続殺人犯である西口彰の犯行を克明に追ったこの小説は佐木隆三の綿密な取材によって書かれたものであるが、これまた取材魔で知られる今村昌平がそれにさらに執拗な取材を加えて映画化している。
重いリアリティーを追求する今村監督はこの映画のロケーションを実際に犯行が行われた場所を使って撮影するという鬼気迫る方法をとっている。
こうした現場の雰囲気が演じる俳優にどんな影響を与えるものなのか簡単には想像がつきにくいところもあるが、この殺人場面での緒方拳からは間違いなく異様なオーラが放たれているのを感じることができる。
芸術は自分を狂わせるところから生まれると云われるが、こういう例を見るとそれもなるほど一面の真理だなと深く納得するものがある。
狂気と正気のせめぎ合いが「犯罪映画」の場合、とくに重要なポイントになるということは容易に想像がつくことである。
俳優は自分を狂わすことで殺人者に同化させ、監督は完璧な表現を目指して狂的なエゴイズムの限りを尽くす。
そしてそれを成し遂げられる者が真の俳優であり、監督といえるのであろう。
それなくしてはデモーニッシュな世界の構築はあり得ない。
市川崑監督の「炎上」はいうまでもなく金閣寺炎上の放火犯である修行僧の物語である。
三島由紀夫の「金閣寺」を原作に作られているが、小説では犯人の青年が金閣寺の美しさに魅せられ、その美に殉じて放火をするという観念的な動機が書かれている。
だが映画ではもっとリアルな青年僧の内面のドラマを描いており、内容的には後に書かれた水上勉の小説「金閣炎上」のほうに近い。
この事件の真相は謎の部分が多く、またその特殊性もあり、多くの作家を惹きつける吸引力の強い題材のようである。
「炎上」以外では後に高林陽一監督によって「金閣寺」が撮られているが、耽美的で華麗な映像を駆使したこの映画は、三島由紀夫の原作に近い作品になっている。
また、水上勉が、この青年僧と廓の女の悲恋物語として描いた小説「五番町夕霧楼」が東映(監督・田坂具隆、主演・佐久間良子、河原崎長一郎)と松竹(監督・山根成之、主演・松坂慶子、奥田瑛二)で映画化されている。
「炎上」はそうした作品群の先駆けとなった映画である。
この映画は大映時代劇の看板スター、市川雷蔵が主役の青年僧を演じている。
大映は当初、彼の出演を不安視し、反対している。
時代劇で二枚目を華麗に演ずる彼が、現代劇に出演するだけでもかなりの冒険だが、その役が金閣寺の放火犯であり、生い立ちが暗く複雑に屈折して自閉するどもりの青年僧ということになれば、二の足を踏むのは当然のことであった。
しかし、雷蔵と市川監督の映画化への強い執着とねばり強い説得でなんとか会社を動かすことに成功し、映画化が実現することになる。
そして雷蔵がこの孤独な青年僧を見事に演じ切ったことで、新境地が開け、彼の芸域の広さを改めて世間に印象づけることになった。
あんな二枚目にこんな役がやれるのかといった驚きがあった。
裏日本の暗い風土のなかで貧しく育った劣等感の強い青年僧に市川雷蔵のどちらかといえば普段は地味で目立たないキャラクターが見事にはまり、主人公の孤独といらだちが痛いほど伝わってくるのである。
どもりという強度の劣等感から思ったことの何分の一も言えず、常にもどかしく自閉する哀れな青年僧の雷蔵を見ていると、あるいはこれこそが彼の本質により近いものなのではないかとさえ思えてくる。それほど雷蔵の演技はすばらしい。
父のない子として生まれ、歌舞伎俳優の市川九団次、市川寿海と二度も養子になるという複雑な生い立ちの雷蔵には歌舞伎役者としての華やかな一面と、暗い孤独な一面がある。
そしてその両面の微妙なバランスが雷蔵の魅力を複雑で底の深いものにみせている。
彼はこの明と暗を巧みに使い分け、様々な役柄を演じることで、三七歳という夭折でありながら幅が広く多彩なフィルモグラフィーを残すことができた。
そして、この「炎上」の成功がその最初の足掛かりとなっている。
この後、市川崑監督と再びコンビを組んで「ぼんち」「破戒」が作られたが、いずれの演技も「炎上」と同列線上にある屈折した名演技であり、代表作のひとつに数えられるものである。
戦後映画界に燦然と輝く、まさに不世出の映画スターであった。
「青春の殺人者」と「太陽を盗んだ男」
長谷川和彦は1976年に「青春の殺人者」で監督デビュー、3年後の1979年には「太陽を盗んだ男」を撮っている。
だがそれ以後はなぜかまったく映画を撮っていない。
どういった経緯や事情があってそうなったのかという詳しいことはわからないが、81年に車で人身事故を起こしたことがひとつのきっかけになったのではないかと推測する。
しかし、ただ2本の映画を撮っただけではあるが、この「青春の殺人者」と「太陽を盗んだ男」はともに傑作のほまれが高い。
当時、映画が封切られるや、期待の大型新人として俄然注目を浴びている。
マスコミに取り上げられることも多くなり、そのたびに挑発的な言動をくりかえし、映画の刺激的な内容と相まって当時の映画ファンに強いインパクトを与えた。
そして、次回作への期待が高まっていた時に、交通事故を起こしてしまい、以後いっさい映画を撮ることがなく、いつしか伝説の映画監督として語られるだけになってしまったのである。
「青春の殺人者」は親殺しの映画である。
千葉県で実際にあった事件を題材にして中上健次が書いた小説「蛇淫」を大島渚の作品を長く書き続けている田村孟がシナリオ化し、今村昌平のプロデュースのもとに長谷川和彦が初監督した。
映画の冒頭、主人公の青年(水谷豊)が両親を殺す場面が唐突に現れる。
まず、はじめに父親(内田良平)を包丁で刺し殺し、それを見つけた母親(市原悦子)がその死体を見て驚くでもなく、父親は蒸発していなくなったことにして、ふたりでどこか遠くへ行って隠れて住もうと息子を説得しはじめる。
それはまるでその事件を予期していたとでもいうような態度である。いや、あるいは、もう起こってしまったことは仕方がない、死んだ者よりも生きてる者のほうが大事だというような計算が混乱した頭の中で働いたのだろうか。いずれにしても、この異常な事件に遭遇した彼女の態度はいささかバランスを崩している。
そして彼女はそんな自分の提案に満足し、ふたりだけの生活を想像して恍惚とし始める。
しかし彼はそんな母親の提案を拒否するかのように無残に彼女を殺してしまう。
血の海のなか、母親にかぶせた白いシーツのうえから包丁で何度も刺す場面はおぞましくおもわず目をそむけたくなる。
この衝撃的な殺人のシークエンスが数十分にわたって延々と続くと、観ているこちらはさすがにエネルギーを消耗し、いささか辟易してしまう。
そしてこれほど残酷な殺人であるにもかかわらず、青年の殺人の動機は判然としない。
憎しみや恨みといったものを彼のなかに見ることはできない。
いやそんな彼自身でさえもいささか自分を持て余しているようにも見える。
なにがそうさせるのか、結局、その理由は明らかにされることはなく映画は終わる。
深い暗闇が横たわったままである。
評論家の川本三郎がこのことについて興味深い考察をしている。
少し長いが、次に引用してみる。
『親殺しの殺人の背景にはこの、都市と農村がドラマティックにぶつかり合う現代日本を象徴する風景がある。順の親殺し殺人事件というドラマティックな殺人には実は古典的殺人事件のような「憎悪」「怨念」といったはっきりとした動機がない。加害者である順自身が、おそらくは自分がなぜ親を殺したか説明しきれない。そうした言ってみればムルソー的な現代の「理由なき殺人」の根拠をあえて求めるとすれば、この京葉コンビナートに象徴される、都市と農村がぶつかり合う風景になるのではないか。・・・・・・・・・すぐれた犯罪映画というのは必ずその背後にすぐれた風景を持つのである。』
風景論から芸術や文化を照射する川本三郎の特異な観察である。
この映画では「理由なき殺人」の動機にはあえて踏み込まない。
それを解き明かすのが目的ではなく、謎は謎としたまま、殺人者としての若者の青春を熱い思いで描こうとしている。
そして、その荒廃した青春を通して地獄の深淵を覗こうとしたのかもしれない。
この重苦しい第1作からうって変わって第2作の「太陽を盗んだ男」はポップで躍動感のあるアクション映画になっている。
そして、ここでも独創的な犯罪が扱われている。
ある中学の物理学の教師、城戸誠(沢田研二)が原子力発電所からプルトニュウムを盗みだして原爆を作り、それで政府を脅迫するという一見荒唐無稽とも思えるような着想の物語である。
だがこのいささか現実離れしたような物語を細部をきっちりと描くことで、リアルで説得力のある映画に仕上げている。
とくにアパートの自室を原爆製造工場に変えて手づくりで原爆を作り上げていくプロセスは実に詳しく描かれており、次第に原爆が形になっていく様子が手に取るようにわかる。
なるほど、多少専門的な知識があり、プルトニュウムを手に入れさえすればこうして原爆を個人が作り上げることも可能なのかも知れないと思わせるものがある。
今だとすぐオウムのサリン製造という事件を思い浮かべることができるので、このような着想もけっして現実離れのしたものとばかりはいえないが、当時の感覚ではやはり「お話の上だけ」のことといったニュアンスがあった。
ましてや犯人の要求が「野球のナイター中継を最後まで見せろ」や「ローリング・ストーンズの日本公演を実現させろ」(当時、ローリング・ストーンズの初の日本公演が行われることになっていたが、ミック・ジャガーの麻薬不法所持で公演が中止になった。)といった通常の犯行のイメージからずれるものとあってはなおさらである。
だがこうした荒唐無稽な犯行も、沢田研二によって演じられると妙に説得力のあるものに感じてしまう。彼の軽快で生活感のないキャラクター、犯罪者らしくなく妙に醒めたところのある彼が演ずることで却って底の知れない危うさを感じさせられる。
この映画に先だって作られた彼が主演のテレビ・ドラマ「悪魔のようなあいつ」のシナリオを長谷川和彦が書いており、ここでも沢田研二はピカレスク・ロマン風な悪の匂いのする青年を好演している。城戸誠をその延長線上の人物として眺めてみるのもおもしろい。
対する警察側を代表する刑事を菅原文太が演じているが、沢田の中性的なキャラクターと対照的な男臭さがなんともいい組み合わせである。
そんなふたりの電話による緊迫した駆け引きや、派手なカーチェイスや追っかけの後、ふたりだけでビルの屋上で対決するシーンには、まるで待望久しかった恋人同士のめぐり逢いのような感激がある。
そしてそこで繰り広げられる派手な格闘は死をかけた男同士の道行きでもある。
それはいつまでも闘い続けていたいと思わせるほどいつ果てるともなく続く長いアクションである。
城戸誠の意味のない脅迫はもしかして菅原文太扮する刑事への強烈なオマージュの歪んだ形であり、こうした出会いを秘かに願っていたのではないかと思わせるものがある。
菅原文太はそうした願いに応えるかのように沢田研二を羽交い締めにしたまま屋上から飛び降りる。
長谷川和彦の言い方を借りるならば、これは「牛若丸を抱いてあの世に飛ぶ弁慶」であり「性的なニュアンス」のある「ふたりの心中シーン」ともいえるものである。
こうして死へと向かったふたりだが、弁慶は見事大往生を遂げるが、牛若丸は幸運にも(不幸にもというべきか)生き残ってしまう。
そして心中者の片割れとなった城戸誠が東京のど真ん中で原爆を点火するストップモーションで映画は終わる。
しかし、ここに悲愴感はない。むしろ十全に戦い抜いた戦士の休息のような開放感が漂っている。
「誘拐報道」
この映画は、兵庫県宝塚市で実際に起こった小学生誘拐事件を報道の立場から書き綴ったドキョメント「誘拐報道」をベースにして映画化されている。
その事件は報道協定により世間にはいっさい公表されないが、その水面下では、激しい報道合戦と警察、被害者、犯人とのぎりぎりの攻防が行われており、そこに生まれる様々な人間ドラマを緊迫したリアリズムで描いている。
特に犯人とその家族(小柳ルミ子、高橋かおり)の描き方に力点が置かれており、犯人役の萩原健一の力演が見事である。
学校帰りの少年が人通りのないトンネルをでた瞬間、空中からスローモションで大きな網が突然落ちてくる。
この唐突に始まる誘拐場面でまず驚かされ、続いて犯人の足取りをていねいに追っていく軽快な展開であっという間に映画のなかに引き込まれていく。
犯人はまず自分の故郷である雪に被われた奥丹後の海辺の町へと向かう。
吹き荒れる風と雪の中、少年を海に投げ込んで始末しようとするが、釣り人の姿が目に入り、果たせない。
さらに場所を移動しながらその機会をうかがうが、なかなかそのチャンスがつかめず次第に焦ってくる。
その時、布団袋に包まれた少年の「オシッコ」という声が聞こえる。
それまで生死が不明だった少年が、まだ元気でいることをわれわれ観客は知り、幾分ほっとする。
犯人はロープで縛られた少年を袋から出してやり、自ら小便をさせてやる。
そして結局はこのことで少年を始末しようという決意が急激に萎えてしまうのである。
そのあたりの犯人の内面のドラマが萩原健一の表情と行動で見事に表現されている。
また奥能登の荒々しい風景(吹き荒れる風と雪、日本海の逆巻く波、そこを飛び交うかもめの群)がそのドラマをさらに盛り上げている。
まさに映画的快感をたっぷりと味わえることのできるシークエンスである。
さらに、ここで犯人が母親を訪ねる場面を設定する事で犯人の心象風景を複雑に見せることになる。
突然の来訪に驚く様子もみせず、息子が鬱屈した気持ちを抱えているのをそれとなく察し、何も聞かずに、ごく日常的な態度で手早く食事を用意してやる老いた母親(賀原夏子)。
緊迫したこのドラマの中で唯一心和む場面である。
男が気の弱りを見せたとき、帰っていくのは結局、母親のふところがいちばん安心できる場所なのだ。
しかし、それによって犯人の不安と葛藤がさらに増幅されるのも確かなことである。
母親との別れをすませた犯人は、身代金の受け渡し場所へと向かうが、これがことごとく失敗してしまう。
いたずらに時間ばかりが経過し、犯人は次第に焦ってくる。そして被害者である少年の両親(岡本富士太、秋吉久美子)の不安と悲しみも頂点に達する。
捜査陣の苦悩も深まっていく。
このあたりの犯人、被害者、警察、取材陣の動きを積み重ねて描くサスペンスの盛り上げ方は非常にスリリングである。
特に財布を落としてしまった犯人が被害者に電話をしているうちにコインがなくなってしまい、「10円玉がないんじゃ、10円玉が!!」と叫ぶシーンは犯人の焦りと苦悩を描いて圧巻である。
そして少年が寒さと疲労で衰弱し始めると電話で「子供を持て余しとるんじゃ!」と弱音を吐き始める。
すべての計画が狂ってしまい、袋小路に追いつめられたようにどうしようもなくなっていく。
ここまでくると私は、完全に犯人に感情移入してしまっており、徒労と悔恨のなかで犯人が絶望する姿に身からでた錆とはいえ少なからず同情を禁じ得ない。
まさに手も足も出ないとはこのことである。
そして、ついには警察の不審尋問にあうと抵抗もなくあっさりと犯行を認めてしまう。
こうして誘拐事件が終わり、少年は無事保護され、報道協定も解除され、各社がいっせいに動き始める。
そして残された犯人の家族に取材陣や野次馬が雪崩をうって、駆けつける。
この場面には胸を打たれる。
家の明かりを消して、娘とふたりで抱き合ってこの嵐の過ぎ去るのを待ち続ける姿はまことに無残である。
まだ暗い朝方、家のまわりを包囲していた記者や野次馬たちが潮が退くようにいなくなった時、母娘が身を隠すために家を出ていく。
ただひとりそこに身を潜めていた若手の記者がすばやくフラッシュをたいて母娘の写真をスクープすると、幼い娘が「うち、お父ちゃん好きや!」と眼に涙をためて記者に叫ぶ。
そして、逃げるようにして暗闇の中を去っていく。
こうして深い余韻を残して映画は終わるのである。
伊藤俊也監督、会心の一作である。
また、「さそり」以来、すべてのシナリオを担当している松田寛夫の会心の一作でもあり、骨太でよどみなく書かれたシナリオがこの映画を力強く支えている。
「水のないプール」(若松孝二監督)と「十階のモスキート」(崔洋一監督)はどちらも内田裕也主演の優れた犯罪映画である。また同じ内田裕也主演の「コミック雑誌なんかいらない」(滝田洋二郎監督)も同系列の映画であり、こちらは犯罪やスキャンダルを追いかける過激な突撃リポーターを描いている。かの悪名をとどろかせた三浦和義が本人の役で登場してくる。
「水のないプール」は一人暮らしの若い女性をねらって夜な夜なクロロホルムで眠らせ、性犯罪を犯す男が主人公である。
この変質的な犯罪を単なる変質者の犯罪として描くだけでなく、人間存在の暗闇を見据えようとする作家の冷徹な視線があり、質の高い作品になっている。
それは「十階のモスキート」も同様で、どうしようもない人間の愚かさやおかしみに彩られた孤独な精神が次第に行き場を失っていくさまが静かな口調で語られていく。
苦い表情の内田裕也がこうした犯罪者を演じるとまさに適役である。
そして、「コミック雑誌なんかいらない」では、犯罪者ではないが、犯罪すれすれと思われるような過激な取材をするいわゆる突撃レポーターを演じている。
内田裕也演ずるレポーターが現実の事件やスキャンダルを追いかけ、その過激な突撃ぶりに思わず興奮させられる。
抗争中の暴力団の組事務所に体当たりの取材を行い、本物の組員と取材をめぐって一触即発のやりとりをする場面などは、劇映画という枠を越えた本物の迫力を感じ、フィクションとノンフィクションの間を自在に行き来する手法が、この映画では臨場感あふれる効果を生みだしている。
そしてこの手法によって1985年という時代の側面が鮮明に浮かび上がってくる。
それはきわめて歪んだ形のものであり、現代の深い闇を感じさせるものである。
そうした意味でもこの映画は実に犯罪的であり、しかも同時に優れた犯罪映画でもある。
この映画のラスト近くに、豊田商事会長殺人事件の再現場面が出てくる。
ビートたけしが犯人に扮して、テレビで実況中継された事件そのままの異様な迫力で殺人場面を再現している。
現実と虚構の間を行き来して、様々な事件の取材を重ねた末のクライマックスの事件として登場するこのシーンは、果たして現実なのか虚構なのか判然としないような実在感がある。
ビートたけしの抑えた静かな狂気に慄然とさせられる。
「TATTOO・刺青あり」(高橋伴明監督)はひとりの若者のねじ曲がった暗い情念が次第に犯罪へと落ちていく様を冷徹なリアリズムによって描いた作品である。
「三十歳になるまでに何かどでかいことをやってやる」という野心をもった若者が、結局は、その野心ばかりが先走り、現実との深いギャップの中で最後は自滅的とも思える銀行強盗へと突っ走ってしまう。
「どでかいこと」「ほんまもんの男になる」ことが銀行強盗だというのは悲しく哀れである。
身体に彫った刺青は自らの存在と野心を誇示する象徴でもある。
そしてその刺青に殉じるよう銀行に突入し、最後は射殺されて死んでしまう。
そんな若者を宇崎竜童が熱演している。
「その後の仁義なき戦い」と「駅STATION」の好演とともに彼の代表作といえる。
そして、この若者の自滅への軌跡をピンク映画出身の高橋伴明監督が粘っこいリアリズムで描きあげている。
先にあげた沢田研二、萩原健一、内田裕也、そして宇崎竜童と犯罪映画の秀作の主演者にミュージシャン出身の俳優が期せずして並んだ。
単なる偶然かもしれないが、非常に興味深い。
彼らに共通した反権力的な個性やミュージシャン特有のフットワークの軽さがそうした役柄にうまくはまるのに違いない。
また音楽(特にこの場合はボーカル)と映画(の演技)は肉体を使って表現するという点では非常に近しい表現形態といえる。
表現するということにおいて音楽も映画も大きな違いはない。
そしてもともと彼らは時代を読みとる鋭い感性の持ち主であり、吸引力の強い個性の持ち主なのである。
そんなところがミュージシャンから俳優に転じて成功する理由のひとつであり、彼らを優秀な監督たちが使いたがる理由でもあろうと思う。
いずれも映画の中で実に輝いて生きている。
「さらば愛しき大地」(柳町光男監督)は茨城県の「鹿島地方」という高度成長期の巨大開発により大きく変貌を遂げていった地域のなかで、その都市化に足並みを合わせるようにして破滅していく男を描くことで、人間の精神の荒廃を鮮烈に浮かびあがらせた作品である。
根津甚八演ずる農家の長男が農業を嫌って、鹿島開発に関わる砂利トラックの運転手をやっている。
彼には幼いふたりの息子がいるが、この子供たちが事故で水死したことから人生の歯車が狂いだす。
女房(山口美也子)ともうまくゆかなくなり、家を出て馴染みの店の女(秋吉久美子)と同棲をし、いつしか覚醒剤にも手を出すようになってしまう。
荒む一方の生活のなかで、ついには同棲の女を包丁で刺し殺してしまう。
緑あふれる田園風景とそれにそぐわない巨大な煙を吐き出す大工業地帯のなかで、傷ついた男と女の結局は破滅していくしかない物語が静かな口調で語られていく。
そして、そんな事件をよそに何事もなかったかのようにいつも通りの生活が繰り返されていく。
そうした営みも事件もまるで風景の一部でもあるかのように時間は淡々と流れていく。
物語の間に何度も挿入される鹿島の風景、風に波打つ緑の稲、生き物のように休みなく煙を吐き出す無機質な工場、ここにもまた都市と農村がぶつかりあう歪んだ風景が横たわっている。
そんな風景の中で覚醒剤によって破滅していく男の狂気を根津甚八が見事に演じている。
彼は「その後の仁義なき戦い」でも覚醒剤中毒のやくざに扮しており、狂気と正気のはざまをうつろう中毒者の危うい不気味さを演じて印象に残る。
そんな根津甚八の滅びへの足取りを見るにつけ、人間の愚かしさ、哀しさ、寂しさを実感させられる。
作中、落ちぶれ果てた根津が秋吉久美子との間にできた幼い娘をつれて町の食堂で寂しく食事をするシーンがあるが、ここでふと葛西善蔵の代表的な短編小説である「子をつれて」を思い出した。
この小説は、落魄した小説家が何ヶ月もたまった家賃が払えず、借家を追い出され、やむなく幼い子供を連れてあてもなく町を彷徨うといった寒々しい物語である。
その小説と共通する心細い惨めさがここにもあり、胸を打たれる場面である。
無惨な人生というべきか、あるいは人生こそが無惨というべきなのか。
こうやって足を踏み外す人間はことさらめずらしくもなく、だが、そうしたことも人々はいつしか忘れ去り、何事もなかったかのように日々の営みを繰り返していく。
それがわれわれの住む社会というものであり、人生なのだという思いを強くする。
「死んでもいい」(石井隆監督)
小さな不動産屋を営む中年男(室田日出男)が若い女房(大竹しのぶ)と暮らしている。
そこへ、ある日得体の知れない若い男(永瀬正敏)が現れ、従業員として雇われる。
若い男は次第に大竹しのぶにひかれはじめ、ふとしたきっかけから不倫の関係になる。
そして、それを亭主に知られたことから、亭主を殺してしまう。
いわば日本版「郵便配達は2度ベルを鳴らす」である。
石井隆監督といえば、かっては劇画家として勇名を馳せた人で、そのスキャンダラスでエロチックな作風に私もかつて魅了されたことがある。
その当時から登場する主人公たちの名前はどれも「名美」と「村木」であり、表現の場が映画に移ってからもそれは一貫して同じであり、こだわり続けている。
「名美」は、石井監督にとっては永遠の女性であり、また女性なるものの凝縮された総称でもある。
そして女性という生き物を作品を越えて重層的な視点で描き続けている。
それを証明するように、この作品の名美である大竹しのぶのなんと危険な魅力にあふれていることか。
個人的な好みを言えば、あまり好きな女優ではないが、この映画の彼女はなかなか妖しくエロチックであり、「死んでもいい」と男に思わせる魔力を秘めている。
彼女の演技のうまさは定評のあるところだが、ここでは演技を越えた危うい官能が漂っている。
さわれば間違いなく火傷をするが、それでも手を出さずにいられない魔力が自然と匂い立っている。
そして大竹しのぶが童顔であることでいっそう倒錯したものに感じさせる。
やはり、犯罪の裏に女あり、ということである。
|