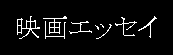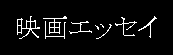|
映画と涙
若い頃には考えもしなかったことだが、最近、映画を観て涙を流すことが多くなってきた。若い時には、どんなに悲しい物語を観ても、涙などとは無縁であったのだが。
果たしてこれはいかなる作用によるものか。
よく、歳をとると涙もろくなると言われるが、本当にそうである。
これは、多少とも人生の機微が解るようになってきたということなのだろうか。
子供の味覚は幅がなく、苦みを味わうことができないが、成長するに従って微妙な味がわかってくる。それと同じように人生に対する味覚も歳とともに発達してくるのであろうか。
ともかく、ことほど左様に映画を観ながら泣いてしまう。
少し情緒不安定気味なのかもしれないなどと思ったりするのだが、最近では、泣くということが映画の出来を測るひとつのバロメーターになったりもしている。
しかし、時にはお涙頂戴式の作為的なものもあり、それにも簡単に反応してしまうので、多少要注意ではあるが。
そうした場合は「泣いては駄目だ」と抵抗するのだが、おもわずそのツボにはまってしまい、だらしなく泣いてしまう。
そんな時はさすがに少し気恥ずかしい。おもわず反省してみたりするが、それでいて心の中に解消されたものがあり、気分がスッキリしている。決して嫌ではない。
こういった涙を流す精神構造というものを考えてみると、いろんな形のものがありそうだが、特に私の場合、<やさしさ>や<まごころ>といったものに涙を誘われることが多いように思う。
つらい、悲しいだけではなかなか泣かないが、それがいったん優しさとか真心といったものに触れるととたんに涙腺が刺激される。我ながら情けないほど涙が流れてしまう。
最近観た映画の例でいえば、萬屋錦之介(中村錦之介と言ったほうがわれわれ世代にはぴったりくるのだが)の「関の弥太っぺ」(監督 山下耕作)がある。
先日(三月十日)錦之介が亡くなり、その死を追悼する意味で再び観なおした。
長谷川伸原作のこの映画は錦之助主演の「瞼の母」「遊侠一匹」とともに彼の代表的な股旅映画であり、どの作品も思いっきり泣ける。
昔、助けた少女と妙ないきさつから十数年後再び巡り会うことになるのだが、やくざ渡世で虚無的に生きてきた錦之助の顔は別人のように変わっており、再会した娘おさよ(十朱幸代)にはわからない。しかし、別れの時、昔おさよが父親と別れ、心細い思いをしていたときに語りかけた励ましをもう一度同じ言葉で語りかける。娘はその言葉でこの人こそ昔の恩人だと気がつくというクライマックス。
「おさよさん、このシャバにゃ悲しいこと、つらいことがたくさんある。だが、忘れるこった。忘れて日が暮れりゃ明日になる。・・・・あぁ、あしたも天気か」
もう、いけない。熱いものが胸にこみあげてきて、あっというまに目がかすんでくる。
無情なやくざ渡世にあってもわずかに残っていた純な心。心の奥底に閉じこめてしまっていたやさしさがすべてを断念してしまった錦之助の最後の別れの言葉としてでてきたのである。この優しさに触れたとき、その思いの深さが万感胸に迫ってくる。
ここまで書いてきて思い出したのだが、最近は映画に限らず歌を聴いたり、本を読んだりして涙を流すこともある。バカなと思うかも知れないが、本当なのだ。
涙を流した歌は、さだ・まさしの「風の中のライオン」という歌である。
若い医者が恋人と別れてアフリカのケニアで辺地医療の仕事に就き、その生活の様子を手紙で恋人に書き送るという歌なのだが、アフリカの雄大な風景が映像的に歌いこまれており、そのなかで彼が「自分はこのアフリカの雄大な自然の中で、風に吹かれて誇り高く立つライオンになるのだ」という決意を手紙にしたためる。そういう内容の歌である。
次に、本を読んで泣かされたのは、同じく、さだ・まさしが書いた「絶対温度」という本の中に書かれた鉄道員のエピソード。
これはくわしい内容は省くが語り口のうまさについ泣かされてしまった。
内容を書くと原文の良さを損ねそうなので、これは読んでもらわないと仕方がない。
その他に藤沢周平の短編のいくつか。これはもう絶品である。文句なく面白く、泣かされる。藤沢周平もつい先日残念ながら亡くなってしまい、これ以上作品が読めなくなってしまった。残念な限りである。
以上、これまでに泣かされたいくつかのものを書いてきたが、とにかく、泣くというのは精神衛生上いいことだろうし、共感するものがそれだけ多いということだろう。そのぶん人生を深く味わえるということではないかと自分勝手に解釈している。
|