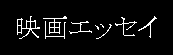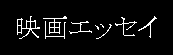|
東映東京大泉撮影所の頃
昭和四十六年、大学に籍を置いたまま結婚。とりあえず食っていくために、わずかなつてを頼って、東映東京大泉撮影所の美術の下請け会社に潜り込むことができた。
学生との二足の草鞋の生活の始まりであった。
映画青年の端くれであった私は、わずかでも映画に関わった仕事に就くことで満足しようと考えていた。
しかし、現場の過酷な仕事はそんな思いをみごとに吹き飛ばしてしまう。
実際の撮影現場は映画好きの学生の情熱などが通用するほどやわなものではなく、日々スケジュールの消化に忙殺されるだけの毎日であった。
当時の映画産業は斜陽の度合いを加速度的に速めており、そのしわ寄せは撮影の現場に如実に現れていた。
撮影所ではこの前近代的で劣悪な労働環境を改善するための労使の交渉が繰り返し行われており、権利の獲得のため、時には殺気だった空気が流れることもあった。
しかし、下請けの零細な企業に身を置く私はそうした動きに参加することもできず、ただ傍観するだけであった。
満たされず鬱屈した日々の中で、いつか映画好きで同好の士と呼べるようなスタッフたちと知り合うようになり、彼らと映画への思いを語り合うことでわずかに自分を慰めていた。 そして、そんな仲間たちが集まって、映画作りの夢を実現させようというグループが自然とできあがっていった。長時間束縛される仕事の合間を縫ってシナリオを書き、お互い批評し合うという活動がいつのころからか始まった。
当時、映画五社の中で産業の陰りが最も強く現れていたのは日活と大映であり、前年にはこの二社がともに映画を配給するダイニチ映配という会社を設立しており、これによってなんとか起死回生をはかろうとしていた。
しかし、結局、この策もわずか一年半ほどで挫折してしまうのだが、この時、残り火が突然勢いを増すようにして、日活で何本かの優れた映画があらわれる。
のちに、これらの映画群を指して「日活ニューアクション」と呼ぶようになるのだが、そのなかでも澤田幸弘監督の「反逆のメロディー」、藤田敏八監督の「ワイルド・ジャンボ」「暴走集団71」などはアナーキーなエネルギーを発散させた優れた作品であった。無意味な死に向かって爆走していく若者たちを描いたこれらの映画は、若い熱心な映画ファンに喝采をもって迎えられた。それは、六〇年代後半から続いていた過激な政治状況の終焉を告げる最後の祭りであるかのような輝きであった。
そして、この年の八月、藤田敏八監督の「八月の濡れた砂」を最後にダイニチ映配は幕を閉じることになる。
「八月の濡れた砂」はそういった意味でも記念碑的な作品であるが、それとともにこの映画は、当時の時代の気分を見事に表現した作品として記憶に残るものであった。
若者たちの無為な日々が湘南の夏の海を背景にみずみずしく描かれた藤田敏八監督会心の作品であった。
湘南の海を舞台に太陽族という無軌道な若者たちの青春を扱った映画「太陽の季節」「狂った果実」からその後の日活の屋台骨を背負う石原裕次郎という大スターが現れたことを思えば、これは奇妙に符合するものであり、歴史の皮肉を感じさせる。
目標を失った反抗のエネルギーが無為な日常の中で虚しく空回りする。行き場のない怒りをもちながら、何をするでもなく無意味な行動をただ繰り返す。
そして、その苛立ちと焦燥が時代の閉塞感と見事に重なり合う。
さらに、それは当時の私自身の心情とも重なるものであり、強く印象に残ることになったのである。
この後、わずか数ヶ月でついに大映は倒産。映画製作は行われなくなる。
そして、日活も製作の大幅な変更を行い、ロマンポルノへと路線を移行していくのである。映画界の冬の時代はもうすでに始まっており、ますます混迷の度合いを深めていくことになるのである。
翌年、東映でもこれら「日活ニューアクション」に続くような作品が生まれる。
伊藤俊也監督の第一回監督作品である「女囚701号・さそり」がそれである。
劇画を原作に企画されたこの作品の主演はあの日活ニューアクションの「反逆のメロディー」「ワイルド・ジャンボ」「暴走集団71」等で華々しい活躍をみせた梶芽衣子であった。彼女は日活ニューアクションの象徴的なヒロインとして、危険な強さと優しさをもった女を体現する女優であった。
そして、この「女囚701号・さそり」でそのイメージをさらに深く表現していくことになるのだ。裏切られた女の怨念がモダンでシャープな映像によって見事に表現されている。
梶芽衣子は剃刀のように鋭い殺意を全身から発散させながら女囚さそりを見事に演じている。
この頃、伊藤俊也監督は「撮影所通信」という新聞を代表で発行していた。
昭和初期、京都太秦撮影所の大部屋俳優であった斎藤雷太郎が同名の個人新聞を発行していたという事実に伊藤監督が関心を持ち、このことを同じ映画人として自分なりに詳しく検証したいという想いからこの新聞を始められた。私もこの新聞の購読者の一人であり、映画に関する拙い文章をこの紙上に書いたといういきさつもあって、「女囚701号・さそり」の製作には少なからぬ思い入れを感じていた。
直接製作に関わることはなかったが、ひそかに応援のエールを贈り続けた。
そして完成した映画は初監督作品とは思えない水準の高さで、撮影所は久しぶりに登場した有望な新人監督を祝福する空気につつまれた。
作品の出来とともに興行成績もよく、引き続き「さそり」第二作目が製作されることになった。
「女囚さそり・第41雑居房」である。1作目の耽美的なスタイルをさらに押し進めた作品であり、映像上の実験が多く、意欲的な作品であった。
梶芽衣子の主演は変わらず、さらに脇を個性的な女優でかためた。
アングラ演劇で人気の高かった早稲田小劇場の看板女優、白石加代子、日活ロマンポルノで突如脚光を浴びた伊佐山ひろ子などが起用されたのだ。その起用は伊藤監督の時代に対する鋭敏な感性の現れであろうと思われる。
そういった意欲がスタッフをはじめ撮影所内に充満し、活気に満ちた毎日が続いた。
明くる年、東映で「仁義なき戦い」が封切られる。
深作欣二監督会心の作品であり、前年に作られた「現代やくざ・人斬り与太」シリーズの流れをくむ作品である。「人斬り与太」は現実のやくざの実体に近い暴力的な映画であったが、「仁義なき戦い」ではそれをさらに押し進め、血みどろの抗争をダイナミックな映像で描いている。
それまで人気のあった<やくざ映画>はいわゆる任侠映画であり、鶴田浩二や高倉健が着流し姿で登場し、義理と人情に揺れ動くという世界を描いており、いわば一種の時代劇といえるものであった。そのなかで数多くの名作が生まれ、多くのファンに支持されてきたが、次第にその様式性の中でマンネリに陥り始めたのである。
それを打ち破るような形で出てきたのがこの「仁義なき戦い」であった。
手持ちカメラを多用し、まるでカメラが抗争の当事者であるかのような迫力ある映像を創り出している。
任侠の世界を描いたやくざ映画は時代劇として京都撮影所で作られており、その系譜を継ぐようにして「仁義なき戦い」も京都で作られることになる。東京撮影所に所属する深作欣二はまるでヤクザのなぐり込みを思わせるような意気込みで勇躍京都に乗り込んで「仁義なき戦い」を撮るのである。
そして見事に映画は大ヒットをし、その威勢をかってシリーズ化されていくことになるのである。
作品の完成度の高さ、さらには興業的な成功も含めて、これはもう東映撮影所にとってはひとつの事件ともいえるものであった。
以上が私が在籍した3年6ヶ月間の撮影所生活での風景である。
そして昭和四十九年の秋、まだ夏の名残が残る頃、撮影所での生活を断念して、東京を去ることになったのである。
わずかな期間の撮影所生活であったが、過酷な中にもやはり物づくりの一端を担うことで味わえる面白さを感じることも多かった。 また多少とも映画製作の裏側を知ったことで映画にたいする見方が変わったのではないかとも思う。
そして時折、スクリーンのクレジットタイトルで懐かしい名前を発見するたびに、あのころを懐かしく思い出すのである。
|