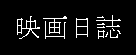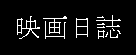今を生きる現代アメリカの生きのいい若者たちの恋模様である。
昨日観た「イン&アウト」もゲイの問題を描いた映画だったが、こちらも同じくゲイの女の子が主人公である。
性的に自由なアリッサ(ジョーイ・ローレン・アダムズ)は10代の頃から様々な性体験を経験しており、平均的な青年であるホールデン(ベン・アフレック)がそんな彼女に一目惚れをしたことから巻起こる恋模様が生き生きと描かれている。
しかし奔放な性体験を積んではいても彼女は「本物の恋」を真剣に求めている女の子だ。
そんな彼女がゲイを承知で友達としてつき合いだしたホールデンの真剣な愛の告白に心を動かされ、戸惑いながらもホールデンを愛するようになっていく。
実は彼女は生来のレスビアンというわけではなく、これまでにも数々の男との性体験も経験しているのだが、今はレスビアンとしてのみ生きているといったことが分かってくる。
そしてホールデンがそのことを相棒のバンキー(ジェイソン・リー)から聞かされたことからさらに新たな悩みにとりつかれることになっていく。
男との経験はないと聞かされていたホールデンは女性との経験に対しては寛大だったにもかかわらず、内心穏やかではいられない。
そしてついにその不満を彼女に対してぶつけてしまう。
だがそんな彼の態度が逆に彼女から手厳しく批判されることになる。
彼女は云う。「確かにこれまで様々な性体験をしてきたが、それはすべて自分から進んで選択してきたことであって、人からとやかく云われることではない」と。
「愚かしい選択や失敗はあったけれど、それはどんなセックスが自分にあっているかということをいろいろと試そうとしていただけで、その結果あなたという理想の相手と出会えたのだ。そんな過ぎ去った過去のことなど今の自分にとってはどうでもいいことなのだ」と涙ながらに訴えるのである。
そうした自分の生き方を毅然と言い切る彼女の姿は逞しい。
ただ単に性にルーズなだけの女の子ではないということが、よく分かる。
その生き方の根底に自分に正直であろうとする真剣さが感じられる。
そしていつの間にかそんな彼女のまっすぐな生き方に強い共感を覚えてしまう。
このシナリオを書いたのは監督でもあるケヴィン・スミスであるが、こうした描写を見ていると並ではない才能を感じさせられる。
さらに彼はホールデンが描くマンガのモデル役としても出演しており、悩めるホールデンに味のある忠告をすることになるのだ。
彼は云う。昔、エイミーという奔放な性体験をもつ女性とつき合っていたが、ある時、彼女の昔の性体験を聞いたことからふたりの関係がおかしくなり、ついにふたりは別れることになってしまった。
彼女の性体験に比べて性的に未熟であった彼は負い目からつい彼女を「アバズレ」と罵倒してしまったのである。
だが、別れた後に考えてみると、彼女は自分に対してセックスを求めていたのではなく、ほんとうは彼自身を求めていたということに気づいたというのである。
そしてそれに気づいたときはもう手遅れだった。それ以来、自分はいつもエイミーの面影を追い続けているのだと。
なんとも胸に響いてくる話ではないか。
だが、こんな貴重なアドバイスをもらったものの、結局アリッサとホールデンは別れることになってしまうのだ。
実によくできた話である。
セックスについての大胆で過激な会話、しゃれたセリフ、リアリティのある生きたセリフ、そういったものが次々と飛び出してきて、聞いているだけでも飽きない。
とくにアリッサとバンキーがお互いの傷跡を見せ合いながら性体験の失敗比べを繰り広げるところなどは「ジョーズ」でのロバート・ショーとリチャード・ドレイファスの傷跡比べを彷彿とさせて印象に残る。
いかにも性に対しておおらかな今どきの若者の生態が垣間見られるといった場面である。
笑い転げるふたりの横で苦虫を噛みつぶしたような表情のホールデンがひとり取り残されているといった図がなかなか笑える。
そこから彼らの生き生きとしたリアルな姿が浮かび上がってくる。
さらに出演者の顔ぶれもなかなかいい。
とくにアリッサを演じたジョーイ・ローレン・アダムズが強い印象を残す。
強靱さと柔軟性を併せ持ち、ひたすら自分流の生き方を貫いていく姿は爽やかである。
さらにホールデン役のベン・アフレックもなかなかいい味を出して好印象である。
彼の役名が「ライ麦畑でつかまえて」の少年の名前と同じというのも面白い。
いかにも悩める若者の象徴のようなこの名前がついているところが案外ミソなのかもしれない。
製作総指揮 ジョン・ピアーソン 製作・編集 スコット・モージェ
監督・脚本・編集 ケヴィン・スミス 撮影 デヴィッド・クライン
美術 ロバート・“ラットフェイス”・ホルツマン 音楽 デビッド・ビルナー
出演 ベン・アフレック/ジョーイ・ローレン・アダムズ/ジェイソン・リー
ドワイト・ユエル/ジェイソン・ミューズ/ケイシー・アフレック
|