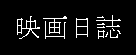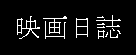奇妙な名前の題名である。
映画のなかでそれは超エリートばかりを集めた未来社会の宇宙開発局の名前のことを指す。
そこは完全なる遺伝子をもつ選ばれた人間だけが入ることを許された組織であり、厳しい管理によって遺伝子の劣った人間たちの侵入を防いでいる。
そしていつか地球外に飛び立つ名誉ある宇宙飛行士となるための厳しい訓練を日々受けている。
主人公ヴィンセント(イーサン・ホーク)は自然出産で生まれた劣性遺伝子をもった青年である。
彼は幼い頃から宇宙飛行士になるという夢を持ち続けているが、遺伝子の優劣だけで人生が決定されてしまう未来社会のなかではその望みが実現する可能性はない。
その不可能な夢を彼は別人になりすますことで実現しようとする。
自動車事故で下半身不随となったエリート、ジェローム(ジュード・ロウ)との契約で彼の血液や尿や体毛の提供を受けて巧妙に彼になり代わるのである。
そして今では宇宙開発局のエリートとなって木星へ飛び立つ日を待つ身となっている。
彼の日常はまず浴室で全身の体毛を洗い落とすことから始まる。
それは無菌室のようにチリひとつない宇宙局のなかで自分の体毛が落ちるのを防ぐためである。
その体毛から彼がジェロームの偽物だということが発覚するのを怖れるための処置なのである。
それほど宇宙局では不適格者の侵入に目を光らせているのだ。
だがその洗い流す行為は発覚の予防ということだけではなく、彼がジェロームになり代わるための神聖な儀式のようにも思えてくる。
宇宙局では入退去の際には必ず尿と血液の検査が待ち構えており、ヴィンセントはジェロームの血液と尿を使って毎日それを巧妙にかいくぐっている。
すべてを隠し、ジェロームとして生きるヴィンセントの懸命さは痛々しい。
それはまるで完全犯罪を遂行していく犯罪者を思わせる孤独な姿である。
いつそのたくらみが綻んでしまうかもわからないという不安定な緊張感がある。
そしてそれがシンプルで無機質なガタカのセットや建物といった映像のなかでいっそう際だったものになってくる。
さらにマイケル・ナイマンの流麗な音楽がかぶさることでヴィンセントの孤独な魂の揺らぎが浮かび上がり、やるせない哀感が漂ってくるのである。
そうした不条理な未来世界の物語をこのように美しく映像化してみせた手腕はなかなかのものといえよう。
監督、脚本はともにアンドリュー・ニコルによるものだ。
未来社会の映像化といえば今ではCGを使った大がかりなSFXによる撮影がほとんどであるが、ここではそうしたテクニックとは無縁である。
ヤン・ロルフスの余計なものを排したシンプルなデザインのセットとフィルターを使い画面に沈んだ色調を施しただけの映像で不思議な未来空間を作り上げている。
そして爆発も破壊もない静かな映像が科学ですべてを決定してしまう未来社会の非情さを見事に表現している。
だからこそヴィンセントと彼に関わることになるジェロームやアイリーン(ユマ・サーマン)のような脱落者の哀しみもともに浮き上がってくるのである。
人間の人生や可能性は数字だけで決められるものではない。
そんなもので可能性が規制されたりつぶされたりしてはいけないのだ。
ヴィンセントにはそうしたジェロームやアイリーンの熱い想いも託されているのである。
もうヴィンセントに後戻りはない。
それは子供の頃、なにをやっても勝てなかった遺伝子操作で生まれた弟に海での水泳競争で初めて勝った日の思いと同じものであった。
その時彼はこう考えたのだ。
「もどることは考えず、全力で泳いごう」と。
その日から彼の人生のすべてが変わり始めたのである。
ガタカ(GATTACA)とはDNAの構成要素である(G)uanine
(A)denine(T)hymine (C)ytosineの頭文字をとってつけられた名称である。
監督・脚本 アンドリュー・ニコル 音楽 マイケル・ナイマン 美術 ヤン・ロルフス
出演 イーサン・ホーク/ユマ・サーマン/アラン・アーキン/ジュード・ロウ
|