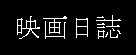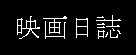2/26 トレインスポッティング
(96イギリス)

アメリカやヨーロッパのドロップアウトした青春とドラッグは切り離すことのできない密接な関係にある。
刹那的に生きる青春とドラッグとは常にワンセットになっている。
そうした世界を描いた映画は数多く、よく知られたところでは「イージー・ライダー」「ドラッグストア・カーボーイ」「シド・アンド・ナンシー」などが思い浮かぶ。
またとくにドラッグを前面に押し出した作品でなくとも、ごくありふれた日常風景として頻繁に登場してくる。
それほどアメリカやヨーロッパではドラッグは日常的に蔓延しているということであり、けっしてめずらしいことではないということだ。
こうした映画を観る度に思うのは、ヨーロッパやアメリカの若者たち(もちろん若者に限らず大人も含めてのことだが)は何と簡単にドラッグに手を出すのかということだ。
日本でも覚醒剤使用の広がりや低年齢化が問題になってはいるが、こうした欧米の現状と比べればまだまだとるにたらない規模である。
日本社会にはドラッグに対する根強い抵抗感と倫理観がまだ厳然と存在しているのである。
国民性の違いと言ってしまってはそれまでだが、こうした事実を思うとき、欧米社会に根付いた精神の荒廃をあらためて考えてしまう。
それはわれわれ日本人の想像をはるかに越えたものだ。
イギリス映画「トレイン・スポッティング」に見られる青春からもイギリス社会の疲弊と荒廃の深さを強く感じさせられる。
そしてそうした社会の呪縛から逃れようとするが、なかなか逃れ切れない若者の日常を時にはコミカルに、また時には残酷に描くことで、イギリスの若者が生きるもっとも新しい今を見せてくれる。
ジャンキーである主人公の幻覚がくりかえし描かれるが、そのなかでも印象的なのは便器に顔を突っ込んだ主人公が排水溝のなかへ吸い込まれてゆくと、そこは海のように広い水中になっており、その水の中を主人公がまるで空を飛ぶように泳いでいくというシーンである。
水の底から仰いで撮った画面には強い太陽光線が差し込んでおり、そのなかをシルエットになった主人公が気持ちよさそうに泳いでいく。
美しく独創的なショットである。
そしてここに主人公の願望が見事に表現されている。
重苦しくなるテーマを軽いフットワークで描くのはダニー・ボイル流のスタイルのようだ。
どうしようもない青春を否定的に描くのではなく、社会を告発しようとするのでもなく、また特別なものとして描くのでもなく、きわめて 自然であたりまえのものとしてクールに描いている。
ここが現代的で新しい。
そしてそこにダニー・ボイルの暖かな眼差しが感じられるのである。
主役を演じるユアン・マクレガーがなかなかいい。
この映画を印象深いものにしているのは彼の魅力によるところが大きい。
彼はダニー・ボイルの監督デビュー作である「シャロウ・グレイブ」にひき続きこの「トレイン・スポッティング」に主演し、さらに3作目の「普通じゃない」にも主演をしている。
また話題のイギリス映画「ブラス」にも主演するといった具合で、いまもっとも注目すべきイギリスの若手俳優である。
けっして二枚目ではないが、強く惹きつける独特の個性をもっている。
今後の活躍を見守りたい俳優のひとりである。
|