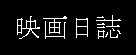
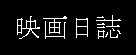
 毎年開かれる恒例の行事で、昨年は観られなかったが、一昨年は古厩智之の作品上映ということで観に出かけた。 今年は篠原哲雄の作品上映である。 彼の映画は「月とキャベツ」を観て好印象を持っていたので観に行くことにした。 上映作品を上映順に並べてみると「RUNNING HIGH」 「YOUNG & FINE」 「恋、した『オールドタウンで恋をして。』」 「山崎まさよしビデオクリップ『One more time, One more chance』」そして篠原哲雄監督を囲んでのトークがあり、最後が「草の上の仕事」というプログラムである。 「RUNNING HIGH」は89年に撮られた26分の8ミリ作品で、ぴあフィルムフェスティバルで特別賞を受賞している。 これは全編ひたすら自転車で走り続ける作品で、アクション映画ともラブ・ロマンスともいえる内容の映画である。 これが篠原監督の処女作であり、助監督の仕事のかたわら撮った作品だそうである。 ほぼサイレントに近く、自転車の走りだけを多彩なカットとカメラアングルで追うといった映画の原点のような作品である。 シンプルだがけっこう飽きさせないで見せる映画である。 「YOUNG & FINE」は今の高校生の日常を丹念に描いた作品。 男女の高校生のカップルと新しく赴任してきた若い女教師の微妙なバランスが笑いとエロスとちょっとほろ苦い感傷のなかで描かれる。 「恋、した『オールドタウンで恋をして。』」は最新のテレビドラマである。 「山崎まさよしビデオクリップ『One more time, One more chance』」は「月とキャベツ」に主演した歌手、山崎まさよしのミュージック・ビデオである。 そして最後に上映されたのが「草の上の仕事」である。 これは1993年神戸インディペンデント映画祭でグランプリを受賞した作品である。 いわば篠原哲雄監督の出世作ともいえる作品で、この作品によって広く世間に認知されるようになった。 これは実にシンプルな映画である。 ふたりの男が草原の草を草刈り機でただひたすらに刈り続けるというだけの映画である。 ただそれだけの映画がなぜか心地よく、不思議と強い印象を残す。 人気のない高原に若いふたりの男がトラックで現れ、黙々と草を刈り始める。 草刈り機のうなる音だけが流れる。 ひとりの男は手慣れた手つきで草刈り機を操るが、もうひとりの男の手つきは危なっかしい。 どうやら彼はアルバイトで、今日初めて草刈り機を手にしたようである。(このアルバイトの男を「爆笑問題」の太田光が好演) その慣れない手つきをもうひとりの男がしきりに注意する。 操る要領を教えるが、その声は手厳しい。 アルバイトの男はそんな態度に不満そうである。 こんなふたりの関係が反発したり近づいたりしながら作業が続いていく。 そして夕闇とともに一日の仕事が何事もなく終了する。 この映画を見ていると昔やった単純労働のアルバイトをふと思い出してしまった。 その時にもこれと似たような状況があったことを思いだしたのだ。 単純な労働のなかにも思いの外に起伏があり、無為に過ぎていくかのような時間のなかにもけっこうなドラマが展開しているものなのである。 そんなことを考えながら観ているといつのまにか自分も彼らと一緒に草を刈っているような気分になってくる。 単純な作業の繰り返しが決して辛いものではなく、むしろその単調なリズムに身をゆだねることで次第に心地よい気分に変わっていく。 そして仕事の終了(すなわち映画の終了)とともに労働の後の心地よさ、ひと汗かいた後の爽快感に満たされているのである。 ということで一仕事終えた気分で会場を後にしたのである。
|
|
|
|
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
