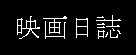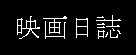3/20 現代やくざ・血桜三兄弟
(71日本)

ここ1週間は1本の映画も観ないで過ごしてしまった。
集中的に何本も観ることもあればこのようにまったく観ないで過ごしてしまうこともある。
気分が乗る乗らないということがあるわけで、その気にならないときはあっという間に時間が過ぎているしまっている。
今月はわりと気分が乗らない月というわけで、今日まででまだわずか4本の映画しか観ていない。
一応の目安としては月に最低でも10本の映画は観るように心がけているのだが、この調子で行くと今月はその数には届きそうにない。
なるだけ自然な気分に任せているので、こんな月があるのも仕方がない。
「観なければならない」という義務感で映画を観るのはダメだと自戒している。
だから観たくないときは観たくないままにまかせておく。
そして観たくなれば観たいだけ何本でも集中的に観るわけである。
やはり映画を観る基本は「楽しさ」でなければならない。
どんな芸術的な作品であっても映画の基本は面白くなければならない。
もちろん面白さの質や内容は様々ではあるが。
だから面白く観ることができなくなればそれはもう映画を観る価値がないということだ。
そしてそれは映画を観なくなる時だということである。
だから逆に面白く観られる限りはいつまでも映画を見続けていくということだ。
さてそんなわけでこんな時はあまり難しく考えないで観られるものをと思い、久しぶりで東映の古いやくざ映画を観ることにした。
菅原文太主演の「現代やくざ・血桜三兄弟」である。
監督中島貞夫、そして共演が渡瀬恒彦、伊吹吾郎、荒木一郎で、悪役に小池朝雄というメンバーである。
菅原文太主演による「現代やくざ」シリーズとして作られたうちの第5作目の作品で、この作品のあと深作欣二監督によるシリーズ 第6作「現代やくざ・人斬り与太」が作られ、これが「仁義なき戦い」へと繋がっていくことになる。
高倉健や鶴田浩二による着流しの任侠映画が下火になりつつあり、後の「仁義なき戦い」シリーズによる実録路線が軌道に乗る前というちょうど両者の狭間に位置する頃の映画である。
であるから当然出演者がみな若い。
そのなかでも菅原文太の活きの良さが特に目立っている。
この頃の菅原文太はドスの利いた鋭さで本物のやくざ以上の迫力がある。
飢えた狼が獲物を見定めるような野生の鋭さがある。
そんな菅原文太が凄むと怖さと同時に惚れ惚れとする男の色気が感じられる。
研ぎ澄まされた刃物のように逃げ出したい恐さと同時に強く惹きつけられる吸引力というか、そんな魅力が全身から発散しているのだ。
やはり、やくざ映画は俳優の魅力によって成り立っている映画なのだということを改めて認識しなおした次第である。
|