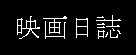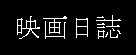6/28 緑の街
(97日本)

10年ほど前、ネームバリューのあるタレントや歌手を監督にして映画を撮らせるという企画が盛んに行われたことがあった。
低迷する日本映画の活性策のひとつとして考え出されたものだが、当時は話題性を狙っただけのいかにも安易な方法に思われたものだ。
そして実際ほとんどが話題性だけで終わってしまったものだが、今になって振り返ってみるとこの試みは割合と意義が深かったのではないかというふうに思われてくるのである。
参考までに記憶にあるところを記してみると次のようになる。
「その男、凶暴につき」「あの夏、いちばん静かな海」の北野武、「稲村ジェーン」の桑田佳祐、「家族輪舞曲」の椎名桜子、「麻雀放浪記」の和田誠、「風、スローダウン」の島田紳助、「無能の人」の竹中直人、「グッバイ・ママ」の秋元康、「外科室」の板東玉三郎、「魚からダイオキシン」の宇崎竜童、「空がこんなに青いわけがない」の柄本明、といったところである。
このうちその後も監督を続けているのは北野武、和田誠、竹中直人の3人である。
この3人のその後の活躍はここで改めて言うまでもないが、こうした才能がこの流れの中から生まれたことの意義は大きいということだ。
もちろんこうした括り方で語ることは必ずしも的を得た方法ではなかろうが。
これはあくまでも同時多発的に起こった流れであり、本来は個々のものとして語るべきものであり、才能ある人間がたまたま時流の中で機会を得たということなのだろう。
ところでこうした流れの中で歌手の小田和正も異業種監督のひとりとして映画を撮っている。
そして当然のようにその作品は批判の集中砲火を浴びることになった。
残念ながら私は「いつか、どこかで」というその監督作品は観ていない。
だからどの程度のレベルの映画なのかはわからないが、映画には素人である異業種のスターが監督をやるとなると作品の出来云々以前に様々な非難中傷が巻き起こるのは当然予想されることではある。
こうした場合はほとんどが冷笑されるか無視されるというのが通り相場のようである。
もちろん小田和正もこうした反応は当然予想したうえでの行動ではあったのだろうが。
そして今回、彼はこの映画製作の際の一連の騒動を題材にして「緑の街」という作品を撮りあげた。
初監督の際の騒動や苦い思いをベースにしたこの作品は当然彼の捲土重来を期そうとする意気込みも感じられるが、それ以上にその時の思いや体験をいまいちど冷静に検証し直したいといった真摯な態度が見て取れるのである。
そしてそれを2重3重に物語に組み込んで巧みに映像化している。
これを観る限りにおいては、彼の映画つくりは決して思いつきやファッションなどといった生半可な動機だけではなかったのだということがよく解る。
そしてその時の体験がなかなか巧妙に映画のなかに取り込まれているのである。
集団で行う映画作りの難しさや苦しさ、特にスタッフやキャストたちとの人間関係の難しさを中心に据えて物語を進めていく展開はなかなか見事である。
撮影している映画の物語と現実の映画作りの物語が重層的に描かれていくことで撮影中の映画の主人公と映画を監督する主人公の思いが重なり始め、次第に作者である小田和正の心情がそこにあぶり出されていくという構造をこの映画は持っている。
それが爽やかな初夏の映像と音楽で叙情的に描かれていく。
しかし如何せん作りがあまりにもオーソドックスすぎるのだ。
新奇な映像や実験的な映像といったものとは一線を画したきわめてオーソドックスでわかりやすい映画なのである。
だからこそ好感が持てるともいえるのだが、それが逆に人によっては食い足りなさと映ってしまうかも知れない。
そしてそうしたことも含めて、おそらくはこの映画も前作同様あまり顧みられることなく、冷遇されたままで終わったしまうのであろう。
そんな予感を持ちながら映画を見終わったのである。
ところでこの映画は地元のテレビ局RAB青森放送の企画で毎年行われている「シネマ・フェスティバル」のプログラムとして上映されたもので、上映後、小田和正によるゲスト・トークがつくというおまけ付きであった。
そしてここでも撮影中のエピソードが披露されるといったこともあり、なかなか楽しめる内容であった。
監督・脚本・音楽 小田和正 撮影 西浦清/今井裕二
出演 渡部篤郎/中島ひろ子/泉谷しげる/尾藤イサオ/津川雅彦
河相我聞/林泰文/角替和枝/大江千里/武田鉄也/大友康平
|