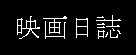
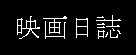
 その映画「HANA−BI」がようやく上映されることになったのは今年に入ってのことであった。 さらにわが弘前での上映はそれより数ヶ月遅れの上映となった。 題名「HANA−BI」の「HANA(花)」は「生」を表し、「BI(火)」は銃撃、すなわち「死」をイメージしている。 「死」は北野武監督の映画の大きな柱になっているテーマであり、これまで一貫して追及してきたテーマである。それはここでも例外ではない。 そしてその「死」を象徴する「火」=「銃撃」すなわち暴力が唐突に現れてくるのもこれまでの映画同様である。 だが、ここで違っているのは現実の彼自身が交通事故によって生死の境をさまようという体験をしたことで死がより具体的で身近なものになったということである。 それまでは映画という虚構の世界の出来事としての「死」であったものがより鮮明で避けがたいイメージとして捉えられるようになったということだ。 そして鮮明度を増しただけ映像表現もより明確な焦点を結んだものになっているのである。 さらに北野武自身が入院中に描いたという「花」の絵や現実の花や海といった「生」を象徴するものが繰り返し登場してくることによって「死」の輪郭がより明確なものになっている。 また極端に少ないセリフや大胆な省略といったいつも通りの手法が映像の緊張感をさらに高めている。 とくに北野武自身が演じる主人公とその妻(岸本加世子)のふたりは「あの夏、いちばん静かな海」の聾唖の少年と少女のその後の姿ではないかと錯覚してしまうほど極端にセリフが少ない。 もちろん彼らふたりが聾唖の夫婦というわけではなく、セリフよりも絵によって語らせようという北野武流の手法によるものであり、これはその手法が到達したひとつの頂点を示したものといえるだろう。 それによって見事な映像詩の世界を作り上げている。 私は事故以前の北野武映画にはいささか懐疑的であった。 だが、事故以後の作品である「キッズ・リターン」とこの「HANA−BI」には素直に感心してしまうのだ。 それまでの表現のややあやふやに思えた印象が消え、明確な像を結んできたように思える。 いわば彼の「人生の覚悟」といったふうなものを強く感じるのである。 人生の総括といったふうなもの、瑣末なものを削ぎ落とした末に見えてきたもの、それに向かって着実に歩み始めたのを感じるのである。 |
|
|
|
|
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
