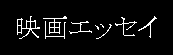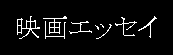|
大藪春彦とハードボイルド映画
大藪春彦が亡くなった。
私が彼の代表作「野獣死すべし」を読んだのは、大学1、2年生の頃だったと思う。
それは、私が本格的なハードボイルド小説を読んだ初の体験でもあった。
私がこの本を手にしたのは、世評高い小説ということももちろん理由のひとつではあったが、彼が同郷の作家だということがその一番の大きな理由であった。
香川県という所は、きわめて作家の育ちにくい土地柄のようで、過去、名を成した作家といえば菊池寛と壺井栄がいるくらいで、同時代の作家というとほとんど皆無であった。
確かに同郷の作家の有無などは、大した問題ではなく、そうした数や顔ぶれを云々することは郷土エゴまるだしで、あまり褒められたことではないかもしれないが、若い頃は、それがなんとも不満であった。
「野獣死すべし」は昭和33年に大藪春彦が早稲田大学3年生の時に書いた作品である。
学生の同人誌に掲載されたこの作品をふとしたきっかけから江戸川乱歩が読み、その面白さに、直ちに彼が雑誌「宝石」に転載し、広く世間に知られることになる。
そして推理小説ファンから圧倒的な支持を受けることになる。
さらに東宝で映画化されたことで、推理小説ファンの枠を越え、広く全国に知られるようになった。
大藪春彦24才、須川栄三監督28才、シナリオの白坂依志夫26才、音楽の黛敏郎29才、さらに主演の仲代達也が27才と主なスタッフ、キャストのほとんどが20代という若い集団による映画作りであった。
大藪春彦は小学校5年生の時に北朝鮮で終戦を迎えている。
この時、彼の父親は軍隊に応召されて不在であり、残された母親と三人の妹をかかえて、彼が一家の柱となって働かなければならなくなる。
家は接収され、毎夜のようにソ連軍の銃声が響き、朝になると死体が何体も転がっているというような悲惨な状況の中、彼は生きるために何でもやった。
盗み、かっぱらいは毎度のことで、まさに弱肉強食の世界であった。
また、そうしたなかで末の妹が栄養失調になったり、別な妹がジフテリアに罹ったりした。
彼は、そのジフテリアの妹を背中にくくりつけて、丸二日間、血清のある病院を探し回った。
もうだめだと観念しかけたとき、父親の友人でもと医者だった人が、総督府の医療室にしのびこみ、ストックのなかにたった一本残った血清を手に入れてくれ、妹は危うく一命をとりとめることになる。
こうした混乱の中、やっとヤミ船に乗る段取りができ、半死半生の状態で南朝鮮にたどり着く。さらにそこから米軍キャンプまで死の行進が続き、やっとの思いで日本に帰り着くことができたのである。
しかし故郷の香川県に住みついてからも平安な日は訪れず、引揚者ということで、いわれなき差別をされ、いじめられたり、喧嘩を売られたりの毎日を過ごすことになる。
また、中学の終わり頃には脊椎カリエスになり、それが癒えた後も、高校の途中でまた再発してしまう。
こうした絶望的な状況が続くなかで、彼は次第に文学に没頭し始める。
高校にはいると新聞部と文芸部、そして演劇部に所属し、文学書をかたっぱしから読み、演劇の演出をしたり、過激な文章を新聞に発表したりして過ごす。
また不良仲間と親しくつきあったり、校則を無視し、しばしば学校と対立したりする。
そして、学校新聞に天皇を批判する文章を掲載したことから学校との間で一悶着を起こしてしまう。
学校当局は、この新聞をすべて回収して、秘かに焼くことでこの問題を収拾してしまう。
この事件で彼は深い敗北感を味わい、ますます反権力の意識を強くする。
このような経緯は、「野獣死すべし」の主人公、伊達邦彦の前半生としてすべてそのままの形で書かれている。
そして、こうした幼少時を過ごしてきた大藪の絶望と怒りが、主人公、伊達邦彦の行動原理の骨格となって投影されている。
これは作者、大藪春彦の現実の物語であると同時に作者の鬱積した暗い情念を物語のなかで解放しようとした小説でもある。
また大藪は早稲田に入学するとすぐ射撃部に入り、射撃に熱中している。
この時の経験と知識を物語に生かし、非常にマニアックな銃の描写をおこなうことで作品にどす黒いリアリティーをもたせている。これがそれまでの探偵小説類と決定的に違うところであり、新しさであった。
こうして、日本初ともいえる本格的なハードボイルド小説の誕生となった。
彼の作品は以後のハードボイルド小説の原型となっており、映画においても同様である。 「野獣死すべし」を作った須川栄三も引き続き「凶銃ワルサーP38」をもとに映画「皆殺しの歌」を作っている。
この映画のシナリオは寺山修司が書いているのだが、これは彼が書いた初めてのシナリオでもあった。
寺山は大藪と同じく早稲田大学教育学部の学生で、大藪よりも1年後輩で、ともに二十代の早熟な才能の持ち主であった。
こうした事実をみていると価値観の定まらぬ戦後社会の混沌のなかにあって押さえようもなく噴き出してくる若いエネルギーの放射を感じるのである。
この他にも日活で映画化されており、古川卓巳監督「拳銃残酷物語」や鈴木清順監督「野獣の青春」の2本の映画がよく知られている。どちらも宍戸錠が主演で、大藪のハードボイルド作品の主役には実に適役であった。
特に「野獣の青春」の宍戸錠はなかなか恰好よく、後の映画化で活躍した松田優作とともに、強く印象に残っている。
また「野獣の青春」は鈴木清順のいわゆる清順調美学といわれる手法で撮った最初の作品としても知られている。
1979年に村川透監督と松田優作のコンビで「蘇る金狼」が作られる。
そして翌年には引き続いて「野獣死すべし」が作られている。
この2本の映画になるとやはり時代の違いといったこともあり主人公の暗い絶望や怒りといったものは薄められ、純粋にアクションの面白さだけをスタイリッシュに描いた作品になっている。
そして、エンターテインメントとしての面白さはなかなかのもので、松田優作の日本人ばなれしたバタくさいキャラクターがこの映画では十二分に生かされており、そのしなやかな肉体から繰り出されるアクションは実に見応えがある。それはまるでスポーツを観戦しているような爽快感があり、ハードボイルド映画としては申し分のない出来になっている。
この二作品に先行して作られた「最も危険な遊戯」と「殺人遊戯」及び「処刑遊戯」のいわゆる「遊戯シリーズ」と呼ばれる作品とともに、良質のハードボイルド映画として記憶されるものだ。
大藪春彦は生涯に100を越える作品を残しているが、私が読んだ作品は「野獣死すべし」の他には十本に満たないほどであり、決して熱心な読者というわけではない。
しかし、このデビュー作の「野獣死すべし」の強烈な印象は今でも鮮やかである。
これは単にハードボイルド小説というだけでなく、青春文学としても優れた作品であろうと思う。
おそらく今後も長く読み継がれていくことになる作品ではなかろうか。
最後に同郷人のひとりとして、彼の死を心から悼むのである。 |