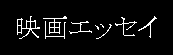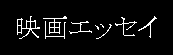|
映画ウィークリー
和田誠が、その著「シネマッド・パーティー」で、映画ウィークリーという連想ゲームのような遊びをやっている。
どういうものかと言えば、1週間の月から日までの、それぞれの文字から、連想する映画を材料にして、思いつくままに書いていくという遊びである。
彼は、洋画でこれをやっているが、こちらは日本映画で、やってみようと思う。
まず、月であるが、題名から思い出してみると、「雨月物語」や「月はどっちに出ている」「月光の夏」などが、浮かんでくる。
子供時代に、胸躍らせて観た「月光仮面」なんてのもあった。これは、映画よりも、むしろテレビ映画の方を夢中になって観た。
日曜日の午後六時になると町の中から、子供たちがいっせいにいなくなるほど、どの子供も、夢中になってこれを観たものである。
テレビでの主役は、大瀬康一で、まったく無名の役者であったが、この映画のヒットで一躍、子供たちのヒーローになった。
劇場映画の方は、大村文武が主演で、彼は東映現代劇のバイプレーヤーで、嫌みな悪役などもやることがあり、子供心にも、とても正義の味方には見えず、これは明らかなミス・キャストであった。
「雨月物語」は日本映画の代表的な名作であり、いまさら説明の必要もないかもしれないが、溝口健二の代表作である。
原作は、上田秋成。
森雅之、小沢栄(後に、栄太郎)、田中絹代、京マチ子、水戸光子らが出演している。 戦国時代を舞台に、情感あふれる幽玄の世界を見事に創り出した作品である。
溝口健二の映画は、ワンシーン、ワンカットの長廻しが特徴だが、この映画の中でも、クレーンを使った素晴らしい長廻しが数多くあり、幽玄の世界の幻想性が、このクレーン撮影の空中を彷徨うような不安定な視点によって、効果的に表現されている。
火で思い出すのは、なんと言っても「七人の侍」の野武士の隠れ家の焼き討ちシーンである。木と茅で作られた巨大な山家が、見る間に火に包まれるこの場面は、映画的な迫力に満ちており、観るものを圧倒する。
このシーンの撮影には、ちょっとしたトラブルがあった。
後に判ったことだが、撮影当日は異常乾燥注意報が出るほど空気が乾いており、それを知らずに、山家にガソリンを多量にかけたため、火の廻りが速く、予想以上の猛火になってしまった。
この山家には、土屋嘉男演ずる百姓のさらわれた女房(島崎雪子)が、野武士たちと住んでおり、この火事で野武士たちとともに、山家から出てくるのだが、土屋嘉男と顔を合わせると、再び火の中に駆け戻ってしまう。それを土屋嘉男が追おうとするが、火の勢いが強く、入っていけないという芝居が展開される。
しかし、あまりにも火の勢いが強すぎ、土屋嘉男は一歩進んでは数歩戻り、ということを繰り返し、終いには、水に濡れた泥を顔になすりつけて必死で演技をする。山家を飛び出し、斬られて横たわっている野武士たちも、あまりの熱さに、倒れた姿勢のまま、少しずつ後退をする。
結局、土屋は逃げることなく、最後まで演技を続けるが、撮影後、顔が火傷で火膨れてしまう。その時の熱の強さを表す話として、島崎雪子が逃げ戻る時に、脱ぎ落としていった打ち掛けが、一瞬のうちに跡形もなく燃え尽きてしまったというほどである。
火を使うシーンというのは、予想がつきにくく、一発勝負になってしまうので、どうしても、こうしたハプニングが起こりがちである。
しかし、まちがいなく絵になるものであり、映画的にはじつに魅力ある材料なのである。
市川崑監督の「炎上」はそうした意味でも、火が一方の主役とも言える映画であった。
三島由紀夫の「金閣寺」を映画化した、この作品で、市川雷蔵は意欲的な演技を見せている。
時代劇の看板スターである彼が、吃音で、貧しい育ちの学生僧という暗く、屈折した役柄を演ずるのは、かなりの冒険だったと思うが、これが、あの二枚目の雷蔵かと思えるような変身を果たしている。
雷蔵の生来的に持っている暗い陰が、この主人公の孤独な性格と、うまく合ったといえよう。
この映画は金閣炎上で終わるのだが、もう一方の主役であるこの火災シーンで、市川崑は、カメラマンの宮川一夫とともに、実験的な撮影をしている。
燃え上がる炎の先から、吹き上がる火の粉をはっきりと判るように映像化しようとする。
実際の火の粉では、なかなか思うような効果は上がらず、結局、金粉を吹き上がらせることで、その美しい炎上シーンの撮影に成功する。
この他に、火を使った印象的な映画に、「泥の河」がある。
宮本輝の太宰賞受賞作の映画化作品であるこの映画は、小栗康平監督のデビュー作品でもある。
昭和三十年代初期の大阪、安治川添いの町を舞台に、そこに住む少年と、その川にある日突然現れた、水上生活者の少年とその姉である少女との出会いと別れを、当時の風俗を丁寧に絡ませて、静かに描いた佳品である。
安治川に浮かべた廓舟に住んでいる少年が、天神祭りの夜、主人公の少年に、宝物を見せてやると言って、この舟に連れてくる。川に沈ませた笹竹を引き上げると、たくさんの川蟹が付いてくる。これが、その少年の宝物である。
少年はその川蟹をアルコールに浸し、甲板に置くと、それに火をつける。アルコールの淡い炎をまとった川蟹が、もがき苦しみながら甲板を走り、最後は、暗い夜の川に落ちてゆく。
美しくも残酷な場面である。自分ひとりの力ではどうしようもない少年の孤独と、悲しみに、胸を打たれる。
この他に思いつく作品に、「吉原炎上」「火の鳥」(手塚治虫の漫画の映画化作品と、もう一本同名の映画がある。その映画で仲代達也が初めて主役を演じている。そして、仲代はこの2本の映画のどちらにも出演している。)などがある。
水といえば、まず第一に連想するのは、雨であろうか。
雨は、日本人とは切っても切り離せない関係にあり、文化的にも、日本人と深い繋がりがある。
雨や水を使ったことわざや言い回しが多くあることでも、それはわかるだろう。
思いつくだけでも、<雨降って、地固まる>とか<水心あれば、魚心あり><水くさい><水に流す><水入り><水を向ける>など様々ある。
雨と言えば、やはり真っ先に思いつくのは、なんと言っても黒澤明の作品である。
黒澤の尊敬するジョン・フォードが、かって彼に「君は、雨が大好きなんだね」と言ったというが、それほど、黒澤の映画には、印象的な雨のシーンが多い。
「七人の侍」の雨の合戦。「野良犬」の雨。「羅生門」の豪雨。「赤ひげ」の長屋に降りつける強い雨。「八月のラプソディー」の最後の場面の風雨。
雨を描かせれば、黒澤にかなう者は、いないだろう。さらに言えば、自然描写のうまさは、他の追随を許さない。
成瀬巳喜男監督の「浮雲」にも、印象的な雨のシーンがある。
戦時中、外地で不倫関係にあった男(森雅之)と女(高峰秀子)が、引き揚げてきた戦後の日本で、生活に破れ、また、ふたりの関係を清算する事もできず、結局、成り行きに任せて、淋しく屋久島へと落ちてゆく。
屋久島は、日本有数の雨の多い地域で、二人が島に着いた日から雨はやむことなく降り続ける。それは、行き場のないふたりの哀れさを象徴するような陰気な雨である。
森雅之と高峰秀子が、絶妙の演技で、このどうしようもない男と女を演じている。
特に、森雅之がこうした男の弱さ、ずるさを演じると絶品である。
インテリのデカダンスを、このように気品を漂わせて演じられる俳優は、数少なく、戦前の貴族的な文化を身につけた彼ならではのものであろう。
「博奕打ち・総長賭博」の雨が降る墓場のシーンや、「関の弥太っぺ」の雨の出入り、「大殺陣」の雨中の一斉捕縛といったところも印象深い。
「裸の島」と「砂の女」では、水が物語の重要なキーポイントになっている。
「裸の島」は瀬戸内海の無人島で、貧しい夫婦(乙羽信子と殿山泰司)が農作物を作っているのだが、水のない島なので、対岸の土地から水を運ばなければならず、小舟で繰り返し水を運ぶという不毛な労働を延々と続ける。シジフォスの神話を思わせるこの物語を、新藤兼人監督は、セリフが一切なく、映像だけで語るという実験的な映画に仕上げている。
「砂の女」では、水が希望を託すものとして描かれる。
砂に埋もれた民家に、男(岡田英治)が蟻地獄に落ちた蟻のように囚われ、そこに住む女(岸田今日子)と共生させられる。何度も脱出を試みるが、果たせず、しかし、偶然の出来事からそこでの生活に新たな希望を見いだしてゆく。
それは、男が考え出した毛細管現象を利用した水の貯水法であり、その研究と実験に没頭するうちに、次第にそこでの生活に充足していく。
この寓意的な物語が、水を思わせる砂の豊かな表情を、美しく映像化しながら語られていく。
次に、水のついた題名をあげてゆくと、「水の旅人・侍KIDS」「水の中の八月」「水のないプール」などが思いつく。
また、水が集まって、川になるということから、「笛吹川」「紀ノ川」「忍ぶ川」などが浮かんでくる。どの作品も原作があり、それぞれ深沢七郎、有吉佐和子、三浦哲郎の原作である。
その他に、先に挙げた宮本輝の「泥の河」とともに、彼の川の3部作といわれる「道頓堀川」と「蛍川」も映画化されている。
木が集まれば、森とか林になり、それから連想すると、まず、「羅生門」が浮かんでくる。
木の葉の影を効果的に使った撮影法によって、森を異次元の世界として表現することができ、そこで繰り広げられる赤裸々な争いを、いっそう際立たせている。
「となりのトトロ」もそうした森の持つ怪しい生命力が、作品のモチーフになっている。森や林は、霊とか物の怪が宿る神聖な場所という、一種、原始宗教的なものと強く結びついた側面があり、「火まつり」では、そうした霊気に人が動かされていくという神話的な世界が描かれている。
黒澤明監督の「蜘蛛巣城」も、森に住む物の怪の予言から、物語が動き始め、まるで、その予言にそそのかされるように、登場人物たちが悲劇へと突っ走っていく。
また、この映画の最後には、「森が動く」という壮大なシーンが登場する。
林といえば、竹林があるが、「越前竹人形」と「古都」には美しい竹林が登場する。
どちらも京都が舞台であり、竹林といえば、やはり京都のイメージが強い。
古い寺や街並みと、竹の涼やかなイメージは、よく結びつく。
次に、金であるが、金は黄金であり銭である。あらゆる人間の欲望の対象であり、これを巡って様々な人間模様が生まれることになる。
「不知火検校」の座頭徳の市は、金と力を得るためには、どんな悪事も厭わない男である。
人の弱みにつけ込んでの金貸しから始まり、強請、脅しは言うに及ばず、殺しも厭わず、あらゆる権謀術数の限りを尽くして、検校の座に登り詰めるが、最後は悪事が露見して捕えられる。このまったく新しいタイプのアウトローを、勝新太郎が、嬉々として演じている。
それまでの彼は、自分の本当の持ち味がどういったもなのか判らず、中途半端な立場に甘んじていたが、この役を得たことで、新境地を開くことになる。
役者としての、進む方向が明確になったという意味でも、この作品は勝新太郎にとってのターニング・ポイントであったと言える。これが、後の「座頭市」シリーズへと繋がっている。
金の亡者で、忘れがたいのは、「しとやかな獣」である。
この映画に登場する家族は一家全員が、金の亡者であり、すべての価値基準が金である。 金のためには、犯罪すれすれのこともやるが、決して犯罪は犯さず、生活は至って質素で、一市民としての立場はけなげに守っている。
娘がその美貌を武器にして、作家の2号になっており、一番の稼ぎ頭であり、伊藤雄之助が小ずるく、底の知れない父親をカリカチュアライズされた演技で、怪演しており、秀逸である。
物語のはぼ全編が、彼らの住むアパートで展開され、舞台劇を思わせるような構成になっている。
つぎつぎに登場するいわくありげな人物たちの、金を巡っての駆け引きが、スピーディーに展開され、欲と欲の絡み合った戯画化された人間喜劇となっている。
滝田洋二郎監督の「木村家の人々」も似たような話だが、もう少し、陽気で、マイホーム的な物語である。
「しとやかな獣」は、どす黒い欲望が渦巻いているが、「木村家」の方は、ある種、スポーツ的な軽やかさがある。
この路線の映画は、過去にもいろいろあるが、どケチや商い物を描くとなると、やはり大阪を舞台にとったものが多くなるようだ。
西鶴物を原作にした「大阪物語」や近松門左衛門の「冥土の飛脚」を映画化した「浪花の恋の物語」や「横堀川」などがそれである。
さらに金から連想されるものに、銀行がある。
「TATOO・刺青あり」は、三菱銀行を襲った、あの犯人、梅津を題材のした映画であり、襲撃に至るまでの、暗い情念をラディカルに描いている。
梅津を演じた宇崎竜童の破滅に向かって落ちてゆく、ねじれた演技が、強く印象に残っている。
同じ銀行強盗ものでは、「遊びの時間は終わらない」が面白い。
ある銀行で、銀行強盗の防犯訓練を行うのだが、犯人役に扮した若い警官(本木雅裕)が、その役柄に熱心なあまり、本物の強盗のようになってしまうという喜劇である。
なにかの拍子に、現実が横滑りしてしまい、起こるはずのないことが起こってしまったという白日夢のような物語を、ブラックな笑いのなかに、描いており、なかなか味のある作品である。
さらに、もう一本。「十階のモスキート」も銀行強盗で破滅してしまう警官を描いており、この男を、内田裕也が好演している。
借金を重ねて、次第に身動き出来なくなっていく、うだつの上がらない派出所の警官と、過激にロックを歌う内田裕也とでは、共通項が感じられないが、警官姿の内田には、悲しいようなおかしさがあり、ふしぎな雰囲気を醸し出している。
小泉今日子が、内田の娘で、ちょっと不良っぽい竹の子族の女の子を演じており、出演場面は少ないが、印象に残っている。
金で印象的な映画を、最後にひとつ。
内田吐夢監督の「飢餓海峡」である。
ここでは、犯罪を立証する重要な証拠として、札束が、使われる。
殺された娼婦(左幸子)が、後生大事に持っていた犯人、犬飼太吉(三国連太郎)の爪と、彼から貰った札束が、犯罪立証の重要な鍵になる。
戦後の混乱期に、ただ一度会っただけの男と女の数奇な運命が、圧倒的な表現力で語られる。
さて、次に、土であるが、そのものずばりの題名で、内田吐夢監督の名作「土」がある。
これは、未見だが、長塚節の自然主義文学の名作が原作となっている。
農村の厳しい労働が、内田吐夢の骨太なリアリズムで描かれているのだが、残念ながら、オリジナル版は消失されており、短縮版が残されているだけである。
黒澤明監督の「わが青春に悔いなし」にも、同様の厳しい労働が、感動的に描かれている。
原節子が、スパイ容疑で獄死した野津(藤田進)の遺志を継ぎ、農村に住む彼の両親とともに暮らそうと、その家を訪れるが、スパイの家族として、村八分にあっており、仕事も出来ず、家に逼塞している。
そこで彼女は、野良着に着替えると、鍬を持ち、敢然と農作業を始める。
村人たちの悪意と、非難の目が容赦なく降り注ぐが、かまわず作業を続けていく。
田圃の土おこしに始まり、田植えまでの土との格闘が、まるで戦場の闘いのような激しさで表現されていく。
しかし、大学教授の令嬢として育った彼女には、あまりに過酷であり、ついに精根尽き果て、倒れてしまう。
村人たちの手前、ひっそりと夜中にだけ農作業を行っていた野津の母親(杉村春子)も、そうした彼女の堂々とした態度に力づけられ、次第に前向きな姿勢に変化してゆく。
村人たちの仕打ちは、日毎に悪質なものになってゆくが、彼らは、決して挫けない。
ある日、田植えの終わった田圃に行くと、せっかく植えた苗が荒らされており、そこには、「スパイ入るべからず」「売国奴」と書かれた立て札が、何本も立てられている。
彼女らは、無言でそれを抜き始めるが、その時、それまで全く反応を示さなかった年老
いた父親(高堂国典)が現れ、理不尽な経緯に怒りをぶつけるように立て札を引き抜いて
いく。それを見て、挫けそうになっていた彼女たちは顔を見合わせて微笑む。
これらのシークエンスが、力強い映像で克明に描かれてゆく。
それは、原節子の、何ものにも負けない強い自我と決意の深さを、気高いまでに表しており、感動的である。
今井正監督の「米」も、古い因習に縛られた農村の生活を、霞ヶ浦を舞台に、リアルに描いた佳品である。望月優子が、抜き差しならぬ貧困と因習の中で、喘ぎ苦しむ農家の女房を熱演していて、哀しい。
土を耕す百姓といえば、過酷な労働と貧困という前近代的なイメージがどうしても付きまとうが、現代の農家の実態はすでに、そうしたイメージからは遥か遠くのものである。 根岸吉太郎監督の「遠雷」に登場する農家の青年(永島敏行)は、そうした前近代的な呪縛とは無縁の、きわめて現代的な割り切った考えの持ち主であり、適当に人生を楽しみながら、着実に自分の生活を築いてゆくといった逞しさを持っている。
使い古された純朴な農家の若者といったステレオタイプの人間ではなく、今を生きるリアリティのある若者として、生き生きと描かれており、好感が持てる。
さらに、土からは、大地がイメージされ、日本で大地といえば、やはり北海道であろう。
北海道が似合う俳優の筆頭は、なんと言っても、高倉健をおいて他にはいない。
古くは、内田吐夢監督の「森と湖のまつり」に始まり、「ジャコ万と鉄」「網走番外地」シリーズ、「幸福の黄色いハンカチ」「駅・STATION」「居酒屋兆治」に至るまで、北海道を舞台にした作品が多い。
そして、北海道と土のイメージの両方を備えた映画が「遥かなる山の呼び声」である。 「幸福の黄色いハンカチ」に続いて、山田洋次監督とコンビを組んだ、この映画は題名からも判るように、「シェーン」をベースにした映画である。
北海道、中標津のとある牧場に、複雑な過去を背負った男(高倉健)が現れ、母子ふたり(倍賞千恵子、吉岡秀隆)で懸命に生きている、その牧場に雇われ、彼らを陰になり日向になり支えていくという物語である。
高倉健をイメージして作られたと思われる主人公を、例のごとく、哀感と孤独を漂わせて演じている。そして、不器用ではあるが誠実に、まるで牧羊犬を思わせるような健気さで母子を見守ってゆく。
しかし、こうした満ち足りた日々は長くは続かず、男は、過去の過ちから警察に捕らえられ、姿を消すことになる。
高倉健が護送される日、倍賞千恵子が、高倉の心意気に惚れ込んでいる男、ハナ肇とともにその列車に乗り込むが、刑事たちの手前、彼に直接話は出来ない。そこで、倍賞とハナ肇が、世間話を交わすという体裁で、その後の母子の元気な様子を知らせる。そして、彼をいつまでも待ち続けるという彼女の想いの丈が、涙ながらに語られる。
この映画における一番の見せ場である。いつもながらの山田洋次監督の巧みな技に、手もなく泣かされてしまう。
さて、最後に土を掘る映画を、ひとつ。
今村昌平監督「果てしなき欲望」である。
戦時中、陸軍の将校が、秘かに埋めたと言われる大量のモルヒネを掘りだそうと、欲に目のくらんだ男たちが集まり、穴を掘る。そこは人家が密集した場所なので、人に気づかれないように様々な偽装をしながら掘ってゆく。
欲呆けした男たちの必死な行動と、やがてやってくる愚かな破滅が、今村流の粘っこいリアリズムで面白おかしく描かれてゆく。
今村昌平は、土着的な共同体を舞台に、人間の愚かさやしぶとさ(特に女の強さ)を、タフな表現力で描いていくことが多い。
そのため「にっぽん昆虫記」「赤い殺意」「楢山節考」などのように、農家が舞台になることが多く、そういった意味でも、土と関わりが深い監督だと言えるだろう。
日の連想のはじめは、今井正監督の「また逢う日まで」である。
これは、戦争映画としても、純愛映画としても名作である。戦争によって無惨に引き裂かれ、命を絶たれてゆく若い男女の青春を、純粋な結晶のように描いた作品である。
黒澤明監督の「素晴らしき日曜日」も、若く貧しい男女の青春の一日を、深い共感を込めて描いている。貧しく、惨めだが、彼らには希望に燃えた未来がある。そして、そうした気分は、おそらく当時の時代の気分とも共通のものであったのだろう。
この映画は、全編ロケーションという黒澤監督にとっては、珍しい作品である。
その撮影によって、昭和二十二年という戦後間もない東京の街が、ドキュメンタリーフィルムのように写っており、当時の街並みを見ることが出来る貴重な資料にもなっている。
久松静児監督の「警察日記」も、まだ戦後の匂いを残した田舎町の警察を舞台にした人情喜劇である。
森繁久弥が人情に篤い素朴な巡査を、ほのぼのと演じており、忘れがたい。
貧しさの中に、暖かい人肌を感じさせるこのような時代が、つい数十年前に、あったということが信じられないほど時代は激変してしまった。
小津安二郎監督の「秋日和」や田坂具隆監督の「陽のあたる坂道」になれば、もうすでに戦後を感じさせない。
日本が高度成長に脚を踏み入れようとするこの時代、その象徴的な俳優である石原裕次郎が、この「陽のあたる坂道」や、同じく田坂監督作品の「乳母車」で、ともに明るく健康的な現代青年を演じ、新しい時代の到来を予感させてくれた。
藤田敏八監督の「陽の出の叫び」になると、そうした明るい未来とは無縁の、暗い雲が覆い始めた、やり場のない青春が現れてくる。
日から太陽を連想すると、題名からは「太陽の季節」や「太陽の墓場」が思い浮かぶ。
そして、太陽といえば、最後に、どうしても黒澤明の作品をあげなければならない。
まず「羅生門」の、太陽にカメラを向けての撮影がある。
それまでの常識では、カメラを太陽に向けるのは、タブーであり、フィルムが焼けてしまうと言われていた。しかし、敢えてそれに挑戦する事で、映画史に残る素晴らしい映像美を創り上げることが出来たのである。
この試みは、実は前年の作品「野良犬」でも、行われている。
若い刑事(三船敏郎)が、犯人捜索のため、復員兵に変装し、闇市をあてもなく彷徨うが、その時の夏の暑さを表現するために、日除けのヨシズ越しに太陽を撮影している。
このショットは移動撮影で撮られている。
ヨシズから漏れる太陽光線の動きが、夏のうだるような暑さを見事に表現している。
そして、延々と続く犯人捜索の大変さが、それによって、なおいっそう強調されている。
「生きものの記録」のラスト・シーンにも、強烈な太陽が登場する。
原爆に対する恐怖から、精神に破綻をきたした主人公(三船敏郎)が 精神病院に入院させられるが、その入院室の窓から見える巨大な太陽を、彼は核爆発と思いこむ。
「燃えている!地球が燃えている!」老人の叫びが、空しく響く。
「デルス・ウザーラ」では、主人公デルスが、太陽を指さして、こう言う。
「あれ、いちばん偉い人」
向日性の黒澤明には、太陽がよく似合う。 |