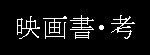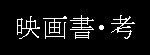「人は大切なことも忘れてしまうから 〜松竹大船撮影所物語」
昨年、松竹大船撮影所が売却されてスタジオが閉鎖された。
昭和11年に拠点を蒲田から大船に移し、以来半世紀以上にわたって映画を作り続けてきた伝統ある撮影所がこれで完全に姿を消してしまうことになる。
時代の流れに対応しきれなくなった結果と言ってしまえばそれまでだが、なんとも淋しい話である。
いち映画ファンとしてはいかにも残念という思いがする。
ましてやそこからさまざまな映画を送り出してきた関係者の感慨はいかばかりだろうと想像してしまうのである。
こうした事態を予想していたというわけでもなかろうが、くしくも今から4年前に松竹大船撮影所の思い出をまとめた一冊の本が出版されている。
「人は大切なことも忘れてしまうから」という題名の本書がそれである。
これはかって大船撮影所で助監督やカメラマン助手として働いていた山田太一以下6名の人たちが3年半にわたってさまざまな人たちから聞き書きしたものをまとめたものである。
主な顔ぶれをあげてみると、篠田正浩、大島渚、山田洋次、西河克己、大庭秀雄、木下恵介、といった監督たち、また厚田雄春、川又昂、高羽哲夫等のカメラマン、さらには照明、美術、小道具、大道具、製作、スチール、脚本、編集、録音、音楽といったあらゆるジャンルのスタッフたち、そして岸恵子、加賀まりこ、笠智衆、津川雅彦といったキャストにいたるまで、総勢30名以上にわたっている。
そのどれもが興味深く、面白い話ばかりである。
そして多彩な個性の持ち主たちがお互いにぶつかり合い、協力し合っていくなかから映画が生まれていく現場の様子がリアルに伝わってくる。
こうしたさまざまな人たちの努力や情熱、さらには培われた技術によって多くの名作が世に送りだされてきたのだというごく当たり前のことがいまさらながらに実感されてくる。
映画がもっとも輝いていた時代、映画が好きで仕方がない人たちが夢中になって働く様子から映画がもつ限りない魅力を感じとることができるのだ。
同時に時代の文化を支えた自信と矜持もそこに見ることができる。
ここで話される撮影所の話はそのほとんどが映画が全盛だった昭和30年代のものが中心になっている。
今からはるか30年以上も昔のことである。
そうした時代の記憶というものはそのままにしておくだけでは、多くは消え去ってしまうものである。
まさに「人は大切なことも忘れてしまうから」なのだ。
だがそれではあまりに惜しい。そうやって朽ち果ててしまうものをただ黙って見ているだけで果たしていいのだろうか、そうした素朴な問いかけから出発したものが、この一冊の見事な本となって結実したのである。
それだけにここには映画と映画をともに作った人々への限りない共感があふれており、また単なる懐かしさだけではない貴重な記録ともなっている。
そしてこうして大船撮影所が閉鎖されてしまった今となっては、なおさらその存在が価値あるものとして光って見えるのである。
これは映画を愛し、映画と共にあった人々のまさに青春の記録なのである。
著者=山田太一/斉藤正夫/田中康義/宮川昭司/吉田剛/渡辺浩
発行所=マガジンハウス
発行=1995年12月21日
|