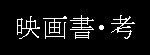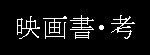|
「勝手に映画書・考」(重政隆文・著)
著者は45歳の大坂芸大芸術学部の助教授である。
残念ながら、私はこの本を読むまで著者のことを知らなかった。
この本は、今は休刊している「くまもと映画手帳」という雑誌および「銀幕」という雑誌に連載されたものをまとめたものである。
一般的にあまり知られていない地方誌であり、その存在を知ることはほとんどないと思われるような出版物での連載と云うことで、この本によって初めて目にしたわけだが、そんなローカルさを越えて内容は濃く、示唆に富んだものである。
そのおもしろさに一気に読んでしまった。
著者は頑固なまでの「映画館主義者」である。
映画は映画館で観るものという考えを頑なに守り続けており、いまだにビデオを持たない生活をしている。
そんな著者がここ10年間に出版された映画関係の書籍と映画について書きつづった文章をまとめたのが、この本である。
ここで取り上げられた映画の本はぜんぶで253冊にのぼる。それだけの数の映画書を読んで内容を批評するということも驚きだが、こんなにも多くの映画書が次々に出版されているということにもあらためてびっくりさせられる。
著者も書いているが、「映画書がさかんに出版される時代というのは映画があまり観られなくなった時代だからこそなのだ」というのはなんとも皮肉な現象といえよう。
ひと昔前に映画ファンだった人たちが、様々な理由で今は映画を観なくなっており、せめてわずかでも映画との関わりを持ち続けようとして映画書を読む。
そんなことも映画書が多く出版される(売れる)理由のひとつになっているのではないかと分析している。
なるほど、そういうこともあるかもしれないなという気がする。
映画館で観る映画しか映画として認めないという「映画館主義」を表明する著者は、そのこだわりと同様、映画と映画書に対する批評も辛辣で容赦がない。
その斬り口の見事さに思わず納得させられてしまうこともしばしばである。
相手が誰であろうと言うべき事は言うといった潔さがあり、そしてそれが実に小気味いい。
彼はそういう批評態度を堅持するためにどの映画関係者とも一定の距離を保とうとしている。
批評家の陥りやすい例として、親しくなったが故に批評の矛先が鈍るということがあり、そうした態度を見逃さず辛辣に批判をする。
「観る前からほめたたえようと構えている批評家の群」がおり、これは「同じく映画完成以前から馬鹿にし、観る時もアラ探しに徹するような批評家の群と同様非難されるべき」であるとして、こうした安易な批評の欺瞞性を強く批判する。
そして「駄目な作品を駄目といわない批評家は一切信用しなくていい」と言い切る。
だから試写会で映画を観ずに、あくまでも普通の映画館で観るという姿勢のなかには、彼自身がそのような批評に陥らないためということも含まれているのである。
あくまでも自由な発言ができる立場に立とうとする。
確かに「映画館主義」という考えは正論で、それに対しては素直に頷くしかないが、地方に住む映画ファンとして言うならば、大いにビデオに助けられているということも無視できない事実なのである。
私の場合を例にとれば、東京に住んでいる時には、マイナーな映画も自由に観ることができたが、弘前に移り住んで以降はほとんど不可能になってしまった。
移り住んだ当初の数年間はまだビデオもほとんど普及しておらず、また新しい環境や仕事に慣れることに精一杯で、映画ファンとしては全くの空白期間になっている。
映画館にも行かず、わずかにテレビ放映される映画を見るだけという生活を数年間続けている。
しかしその後のビデオデッキやレンタルビデオの急激な普及によって、数年間の空白を埋めるとともに、今まで見ることのできなかった数々の名作も観ることができるようになってきた。
これはかって名作を求めて通った名画座と呼ばれた映画館の機能に変わるものであり、東京一極集中型の文化構造をもった現在の日本における私のような地方在住者にとっては非常にありがたいメディアなのである。
そして不思議なもので、ビデオで映画を見始めると映画館に足を運ぶ機会も自然と増えてきたということである。
ビデオというメディアの普及は私の映画環境を一変させ、再び映画との親密な関係を築いてくれたのである。
今は手軽に名作を家で観れる幸せをかみしめている。
もちろん著者の云う「映画館主義」は映画を観る態度として正しく、本来そうあらねばならない態度である。
映画館の暗闇という非日常の世界でしか味わえない映画体験こそ映画本来の真摯な鑑賞であることには異をさしはさまない。
そしてそれを実践し守り通していることには深く敬意を払う。
私自身も映画ファンとして努めてそうあらねばならぬと自戒をこめて思う。
しかし、裏返して考えてみると著者がそういった考えに頑なにこだわらなければならないほど、現在の映画館の置かれた状況が厳しいものだということであろう。
そしてその衰退にビデオが大きく影響していることも動かせない事実である。
私のようにビデオによって映画と再び出会うものがいる一方で、映画館から足を遠ざかせる役目をはたしていることも無視できない事実である。
ビデオの功罪相半ばするところである。
しかしながら、ビデオの普及するずっと以前から映画産業の凋落があったのも事実ではある。
映画館とビデオといった二元論だけで語られるほど簡単な問題でないのはもちろんのことである。
だがこのように声を大にして叫び続けることで映画館という滅びゆく文化を守り続けようとする著者の決意は貴重なものだし、大事なことであろう。
そしてその思いには共感するところも多い。
また、著者自身、この「映画館主義」を偏った考えであることを承知の上でなおかつその主張をしているわけで、頑なに我を通すことで自分の立場を鮮明にし、そこから映画書及び映画の批評を繰り広げていこうとしているのである。
教えられることの多い本である。
著者=重政隆文
発行所=松本工房
発行=1997年9月1日
|