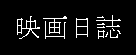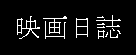結婚に敗れて故郷に帰りついたサンドラ・ブロックがそこで発見したものは色褪せてしまった自分の姿である。
学園の女王として溌剌としていたかつての面影はすでになく、今はただ生活に疲れただけの目立たないひとりの女性でしかないのである。
そんな無惨な現実と向き合わなければならなくなったサンドラ・ブロックは失望と苛立ちのなかで本来の自分を見失ってしまうのだ。
そして幼い娘の敏感な心はそれを本能的に察知して、母親からも心が離れてしまう。
そんな四面楚歌の状態の中で次第に彼女が癒されていき、自立への道を踏み出していく姿を淡々と描いている。
時間は人間をどのようにでも変えていく。
ただそうした変化というものが普段の生活のなかではなかなか見ることができないだけに、ほとんど気にとめずに過ごしているだけなのだ。
だが長い時間を経た後に、いつもの日常から少しばかり離れたところに置かれたときに初めて意識するということになる。
そんな状態になったとき、初めて自分の歩いてきた道が見えてくる。
サンドラ・ブロックが今の自分の生活を変えようと仕事探しのために就職斡旋業者のもとを訪れるシーンでそんな心境がさりげなく描かれる。
そこの責任者の女性が実はかってのクラス・メイトであったということがわかるのだが、サンドラ・ブロックはその女性のことは思い出せず、昔のあだ名を聞かされて初めてその人だと判るという場面である。
昔はデブでブスの女生徒だったそのクラスメイトが今はその面影とはまったく違った溌剌とした美人のキャリア・ウーマンになっており、彼女はそのことに少なからずショックを受けるのである。
そこでのサンドラ・ブロックは相手に合わせて懐かしさにはしゃぐといった態度をとってはいるが、その実、打ちのめされた気分がありありと伝わってくる。
そしてそれに引き比べて現在の自分の生気のなさに改めて愕然としてしまうのだ。
学園の女王として彼らの憧れの的であったサンドラ・ブロックとそのクラス・メイトは今では完全に立場が逆転してしまったのである。
そうした惨めさが彼女の笑顔のなかから見えてくる。
彼女はますます落ち込んでいってしまう。
だがこうしたショックが引き金となって初めて新しい生活や新しい自分への第一歩を踏み出す決意が生まれてくるというのもまた事実なのである。
こうした経緯をどう納得させながら見せていくかということがこうした映画の見せどころであり、泣かせどころでもあるのだが、そのへんが一応きめ細かく描かれており、まずまずの出来である。
そしてこうした時に力になるのはやはり家族ということになってくるわけで、数少ない家族のひとりである母親をジーナ・ローランズが好演しており目をひく。
ちょっと変わり者で、だからこそ常識的な親とはひと味違ったアドバイスや指針を示すことができるといった、人生の先達としての貫禄を見せている。
先日観た「マイ・フレンド・メモリー」に続いての似たような役柄ではあるが、やはり彼女がやるとピリッとした存在感があって、映画が引き締まる。
これがキャリアというものであろう。
さらに彼女に負けず劣らず目をひくのが眼鏡をかけたおしゃまな娘を演じるメイ・ホイットマンの可愛さである。
転校先の学校で、いじめにあいながらも彼女なりに頑張っていこうとする健気さや母親を見る目のシビアさなど、こましゃくれてはいても納得させられる。
といったぐあいに3人がいいアンサンブルを見せているのだ。
こういった映画を観ながらついでに自分の人生のことなども振り返って見るというのも悪くはない。
製作総指揮:メリー・マクラグレン/サンドラ・ブロック 監督:フォレスト・ウィテカー
製作・脚本:リンダ・オブスト 撮影: カレブ・デシャネル 音楽:デイブ・グルーシン
出演:サンドラ・ブロック/ハリー・コニック・ジュニア/ジーナ・ローランス
メイ・ホイットマン/マイケル・パレ/キャメロン・フィンレイ
|