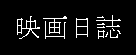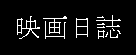「キリコの風景」ときて最初に連想したのはシュール・レアリズムの画家、ジョルジュ・デ・キリコの名前と作品である。
「キリコの風景」ときて最初に連想したのはシュール・レアリズムの画家、ジョルジュ・デ・キリコの名前と作品である。
現実の風景のようにも見えるが、どこか歪んだ現実にはありえない夢のような世界。
そんな作品のイメージをもちながらこの映画を観た。
シナリオが森田芳光、監督が明石知幸という「免許がない」のコンビである。
ジョルジュ・デ・キリコ、森田芳光、そして舞台となる函館の街とつなげてくると次第にあるイメージを指し示し始める。
現実のようで現実でない世界、安定感の欠けた浮遊する感覚、そういったイメージがおぼろげに浮かんでくる。
そう、この映画はまさにそうしたイメージの世界の物語なのである。
函館空港に降り立ったひとりの男(杉本哲太)がタクシー待ちの列に並んでいる。
次々と来るタクシーが客を乗せていくが、この男はなぜか自分の順番が来てもタクシーには乗らず後の客にタクシーを譲っていく。
そしてあるタクシーがやってくるとそれを待っていたかのように今度はそのタクシーに乗り込んでいく。
彼はそのタクシーの運転手(勝村政信)に奇妙な話を持ちかける。
タクシーを一日貸し切って函館のマンションを見て回りたいというのだ。
運転手は承諾して、知り合いの不動産屋(利重剛)を紹介することになる。
こうして3人連れだってのマンション巡りが始まるのだが、この男、村石はマンションを訪ねると奇妙な行動を開始する。
入り口に並んだ郵便受けを探るような目つきで凝視する。
そして何かを感じたような態度でそのなかの一軒を訪れるとそこの住人の悩み事や隠し事を言い当てて、彼らの生活態度を改めるように諭すのである。
諭された住人たちは一様に素直にその言葉に従おうとする。ある者は彼のような人間が現れるのをひそかに待ち望んでさえいたのだ。
そんな不思議なマンション巡りが続いていく。
連れだったふたりは次第に村石の神がかった態度に魅了されていく。そして・・・・
と、こう書いていくと超能力者のSF的な話かと思ってしまうのだが、そうではなくて実は村石は過去にインチキな消火器セールスの詐欺事件を起こし、それがもとで妻は彼のもとを去ってしまったのだが、もういちど彼女を捜し出してやり直そうとしている男なのである。
不思議な力は服役中に自分の罪を悔い改めようと精神を集中していた際に偶然身につけたものだというのである。
浮き世離れした不思議な街歩きがなにを意味するものなのか結局のところよくはわからないのだが、こうした行動がこの映画に独特の浮遊感覚をもたらしており、まさに「キリコ」的な意味不明の世界に紛れこんでしまうことになるのだ。
さらに捜していた妻、キリコ(小林聡美)が登場するや、村石の超能力はとたんに力を失い、それまでの謎めいて毅然としていた態度が急にしぼんで、ひとりの情けない中年男になってしまうのである。
彼はなんとかその能力を彼女に解らせようと試みるが、彼女に簡単に鼻であしらわれて能力を発揮することが出来ない。
この辺の落差はなかなか笑えるところである。
また元夫婦であったふたりの会話も慣れ親しんだ者同士の近しさと適度の距離を感じさせてなかなか微妙な味わいがあり、そこはかとない哀歓を感じさせるのだ。
なにかが起こりそうな予感はあるものの特別なにも起こらず、村石の超能力も本当のところは何だったのか、あるいは超能力など最初から存在しなかったのでは、などといった不思議な謎と余韻を残して映画は終わることになる。
言葉ではなかなか表現しにくいこうした気分の映画はけっこう好きである。
そしてこのような種類の余韻というのは意外と長く後をひきそうな気がするのである。
監督 明石知幸 脚本 森田芳光 撮影 高瀬比呂志 音楽 木根尚登
出演 杉本哲太/小林聡美/勝村政信/利重 剛
|