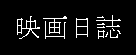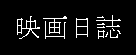新宿警察の不良刑事、中山(岸谷五朗)と在日韓国人の情報屋、秀吉(大杉漣)そして中国人女性、桜花(冨樫真)のねじれた愛情と友情を飄々と描いた作品である。
新宿警察の不良刑事、中山(岸谷五朗)と在日韓国人の情報屋、秀吉(大杉漣)そして中国人女性、桜花(冨樫真)のねじれた愛情と友情を飄々と描いた作品である。
原案は丸山昇一が故松田優作のために書いた「ドッグレース」で、それを崔洋一と鄭義信が新たに書き直したものである。
舞台は新宿、歌舞伎町。ここを根城に生きるやくざや刑事、さらには不法入国の中国人や在日韓国人等の生態を描きながら彼らのしぶとい生き様を乾いた笑いを交えながら描いていく。
あたかも治外法権化したような欲望渦巻く街、新宿歌舞伎町は独特のオーラを放っており、表現者たちの創作意欲を刺激するようである。
ここを舞台に様々な作品が生み出されている。
最近の作品でも「不夜城」「ラブレター」などがあり、いずれもこの街に生息するヤクザやアジア人たちが主人公になっている。
さらに少し前の作品だと「眠らない街/新宿鮫」「われに撃つ用意あり」「新宿黒社会 チャイナ・マフィア戦争」といった作品もあった。
新宿歌舞伎町の無国籍性は香港などのアジアの都市の混沌さと通じるものがあり、最近のアジア映画の隆盛とどこかリンクするものがあるようだ。
この作品でもそういった歌舞伎町の得体の知れなさがよく表現されており、規格外れの主人公3人のキャラクターがいかにもありそうに思えてくる。
「蒲田行進曲」の銀チャンとヤスのような加虐と被虐のねじれた友情がごく自然に受け止められるのだ。
評価の高かった「月はどっちに出ている」よりもこちらの映画のほうが数段楽しめた。
監督・脚本:崔洋一 脚本:鄭義信
原案:丸山昇一 撮影:藤澤順一 音楽:鈴木茂
出演:岸谷五朗/冨樫真/香川照之/遠藤憲一/大杉漣
絵沢萌子/岩松了/國村隼
|