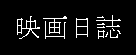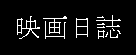「サタデー・ナイト・ライブ」出身の3人とジョン・ランディスが組んで「七人の侍」をベースにしたようなハチャメチャな西部劇をけっこう楽しんで作っている。
「サタデー・ナイト・ライブ」出身の3人とジョン・ランディスが組んで「七人の侍」をベースにしたようなハチャメチャな西部劇をけっこう楽しんで作っている。
3人のお笑い競争といった趣の映画である。
こういった映画の現場はおそらくとてつもなく愉快なものに違いない。
ひょっとすると映画よりもそちらのほうが何倍もおもしろいのかもしれないなどと想像してしまう。
映画では見られないライブ感や即興のおもしろさ、掛け合い漫才のような笑いのやりとりが充満しているのではなかろうか。
そう思ってしまうのも、映画自体の笑いがいまひとつはじけないといううらみがあるためだ。
おかしいことは確かだが、腹を抱えて笑うというふうではないのである。
この3人であればどうしてもそこまでの笑いを期待してしまうのだ。
それだけの芸をもったコメディアンであるはずで、それが十分に発揮されていないのがいささか惜しまれる。
製作総指揮・脚本 スティーブ・マーチン
製作 ローン・マイケルズ/ジョージ・フォルシーJr
監督 ジョン・ランディス 脚本 ローラン・マイルズ/ランディ・ニューマン
撮影 ロナルド・W・ブラウン 音楽 エルマー・バーンスタイン
出演 スティーブン・マーチン/チェビー・チェイス/マーチン・ショート
|