寺山修司は十代で俳句、短歌に特異な才能を発揮した早熟の天才であった。
昭和二十九年、「チェホフ祭」五十首により十八歳で、短歌研究新人賞を受賞。
一躍脚光を浴びる。その後、ネフローゼを発病、二十二歳までの四年間、病床にありながら精力的に作歌、「空には本」「血と麦」「田園に死す」の三冊の歌集を刊行する。
こうした若く鮮烈な活躍はアルチュール・ランボーを連想させるものがあるが、彼はランボーのように若くして筆を折ることはせず、むしろ表現の場を次第に拡げてゆき、詩、評論、戯曲、演劇、映画と、芸術のあらゆる方面において活躍した。
どのジャンルの作品にも寺山修司の色が明確に表現されており、寺山以外の何者でもない個性の強い世界が構築されている。
彼は常々「職業は寺山修司である」と言っていたように、すべての表現が寺山個人への強いこだわりによって作られている。
自分自身へのこだわりが生涯を通じてのテーマであり、そのアイデンティティーを求める旅が彼の人生のすべてであったといえよう。
その自己発見の手法は虚実入り交じった複雑怪奇なものであり、自己の現実を巧みに虚構化し、そこに現れる本質を見事な技で取り出してみせる。
そうした手法で書かれた彼の自叙伝とも云える「誰か故郷を思わざる」には、彼の複雑な生い立ちが書かれており、故郷と母親に対する屈折した心情が様々なエピソードによって語られている。
彼の赤裸々な体験の告白という形になっており、どこからが事実で、どこまでがフィクションなのか判然としないものではあるが、己の恥部をスキャンダラスにさらけだし、自らの肉体の血を流すようなアイデンティティーの検証を行っている。
その執拗な自分さがしには寺山の哀切なまでのこだわりをみることができる。
そして、それは母親に対する愛情と怨みという引き裂かれた感情によって彩られている。
早くに父親を亡くし、母ひとり子ひとりの生活のなかで、自意識が強く、空想癖のある少年がどういった精神形成をしていくのかという典型的な例がここにみられる。
そして、早くに母親と別れて暮らさなければならなかったという事情がそれをさらに複雑なものにしている。
愛情を求めても、側に母親はいないという状況のなかで、彼はひたすら空想の世界に遊ぶようになる。
母親の愛情を手にすることができない不満を、空想の世界で現実をジグゾーパズルのように並び替え、再構築することで解消していこうとする。
「実際に体験しなかったことも、思い出のうちである」と彼は言う。
事実を組み替えたり、起こらなかったことをあたかも起こったことのように妄想することのなかでやり場のない愛情の矛先を鎮めようとする少年の悲しく孤独な浄化作業である。
 こうした愛情欠損児童の性癖が次第に芸術の世界に足を踏み込ませることになる。 こうした愛情欠損児童の性癖が次第に芸術の世界に足を踏み込ませることになる。
そして、その表現は、彼が育った津軽というきわめて特殊な閉鎖社会を背景に語られることで、その暗い情念がよりいっそう増幅されることになる。
彼の第三歌集「田園に死す」はこうした津軽の泥臭い生活や土俗的な信仰を身に纏って、寺山自身を歌った歌集であった。
さいの河原の物語に形を借りた地獄めぐりである。それは故郷という地獄である。
兎追ふこともなかりき故里の銭湯地獄の壁の絵の山
間引かれしゆゑに一生欠席する学校地獄のおとうとの椅子
夏蝶の屍ひそかにかくし来し本屋地獄の中の一冊
また、この歌集には「寺山セツの伝記」として母親を歌った十首の歌も歌われている。
亡き母の真赤な櫛で梳きやれば山鳩の羽毛抜けやまぬなり
亡き母の位牌の裏のわが指紋さみしくほぐれゆく夜ならむ
子守唄義歯もて唄ひくれし母死して炉辺に義歯のこせり
ここでは母親を死なせ(殺し)ている。
不幸な少年がさらに不幸な虚構のなかに自分を追い込むことで心の傷を癒そうとしている。
この歌集のあとがきで彼は次のように書いている。
「これは私の「記録」である。自分の原体験を立ちどまって反芻してみることで、私が一体どこから来て、どこへ行こうとしているのかを考えてみることは意味のないことではなかったと思う。もしかしたら、私は憎むほど故郷を愛していたのかも知れない。」
こうして語られた地獄めぐりが、さらに華麗なイメージの集積として映画「田園に死す」に移し替えられていく。
この映画は、母親から愛情の押し売りをされる少年が、その母親の呪縛から逃れようと様々に夢想する様子が幻想的なイメージの積み重ねのなかで描かれていく。
荒涼たる田園に置かれた仏壇や鏡台といった古い家具類、また逆に家のなかで畳をはがすとそこには恐山があるといった映像。家の内と外のこうした倒錯したイメージ。
突然、川を流れてくる大きな雛壇。その意表を突いた詩的な映像。
黒い衣装を着て顔を白塗りした老婆たちが全員右目に黒い眼帯をして立っている映像の不気味さ。そして、主人公の少年も仮面を被ったような形の白塗りの顔で登場してくる。 この仮面劇を思わせる表情のない少年が荒涼とした恐山のなかに立つ姿は、深く自閉した孤独を感じさせて、悲しい。
彼は母親の愛情に絡め取られて社会との正常な関係が持てないでいる。
そんな母親からの逃亡を夢みており、憧れている隣の嫁さんとの逃避行を夢想したりするが、現実にはなにも果たせないでいる。
そして、時間が錯綜し、そうした過去の自分が現在の映画監督である私を深く悩ませる。 過去を美化するのか、現在を正当化するのか現在の私は思い悩む。
過去の少年と現在の映画監督の対立によって記憶の修正、再構築がなされていく。
ここには寺山が繰り返し引用するシュペングラー「西洋の没落」の一節「去りゆくいっさいのものは比喩にすぎない」という考えがいみじくも流れている。
映画「書を捨てよ町に出よう」に登場する私もいつも家を出ることを夢想する青年である。この映画では母親は亡くなっており、母親の一方的な愛情の押し売りからは自由であるが、かわりに万引き常習犯の祖母、のぞき常習者の父親、人間嫌いで兎を偏愛する妹という家族があり、ひたすらそこからの脱出を考えている。
そして、飛ぶことのない人力飛行機に乗って飛び立つことを夢想する。
人力飛行機の飛翔のイメージが繰り返し現れる。
「北国の暗い空、貧しい母子家庭、そして汽笛を聞くとこみ上げてくる『ここではないほかの土地』への憧れ」これは寺山が同郷の連続射殺犯、永山則夫について語った言葉である。それはそのまま寺山の心情に重なっており、他人事とは思えない永山に対する強いシンパシーを表している。
だが、結局はこの『ここではないほかの土地』にも裏切られることになるわけで、この引き裂かれた感情が寺山を永遠の逃亡者として規定することになる。
この人力飛行機の飛翔のイメージとともに寺山の作品で印象的に語られるイメージにこどもたちの「かくれんぼ」がある。
「誰か故郷を思わざる」のなかにも「かくれんぼ」についての記述がでてくる。
「母がベースキャンプに働きに出るようになってから、私はどういうものか『かくれんぼ』という遊びが好きになった。」
鬼になって目隠しをしてるうちに居眠りをしてしまい、眼が覚めたときはもう何年も時が過ぎており、目隠しをとると、隠れた子供たちがいつのまにか大人になっている。
背広を着たり、赤児を抱いたりして、子供の私を見て笑っているという幻想が現れてくる。
かくれんぼの鬼とかれざるまま老いて誰をさがしにくる村祭 「田園に死す・捨子海峡」
こうしたイメージに寺山はこだわり続ける。
打ち捨てられ、ひとりだけ置き去りにされた心さみしい孤独な自我の戸惑いの声が聞こえてくる。
寺山には、この「かくれんぼ」をして暗闇にじっと隠れ続ける少年のイメージがある。
そして、その暗闇から息をひそめてそーっと他人の人生をうかがっている。
いや、自分の人生さえも万華鏡やのぞきからくりを見るようにうかがっているのである。
 彼は永遠に少年のままで生きようとしている。 彼は永遠に少年のままで生きようとしている。
こうした退行していくイメージは、あたかも恵まれなかった少年時代をもう一度取り戻そうとする作業のようにも見える。
人力飛行機によって飛び立ち、目指す「ここではない他の土地」とは幻想の少年の王国なのかも知れない。
結局、人力飛行機の着陸地点は彼がひたすら逃避しようとした場所にブーメランのように戻ってくることになるのである。
こうして自分さがしの旅が果てしのない地獄めぐりのように続いていくことになるが、その閉じられた世界をのぞきからくりとして見ることであるいは寺山修司は充足していたのかもしれない。 |
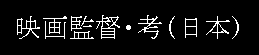
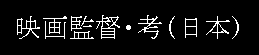

 こうした愛情欠損児童の性癖が次第に芸術の世界に足を踏み込ませることになる。
こうした愛情欠損児童の性癖が次第に芸術の世界に足を踏み込ませることになる。
