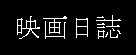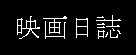4/1 ロング・キス・グッド・ナイト
(97アメリカ)

「カットスロート・アイランド」に続いてレニー・ハーリンが妻であるジーナ・ディビスを主役に撮ったアクション映画。
女だてらに派手なアクションに果断に挑んで楽しませてくれるが、やはり腕っ節の強さは女性には似合わないということを改めて思わせられる。
いくら超ハードなアクションを展開してもいまひとつ心が躍らない。
女でも男に負けないアクションができるのだというジーナ・ディビスの心意気は解らぬでもないが、(そしてその奮闘ぶりはなかなか見事だとは思うが)やはりいまひとつ乗り切れないものが残る。
ジーナ・デイビスという女優は急進的なフェミニストのようで、最近出演の映画の役柄はほとんどが男勝りの女性ばかりだ。
「テルマ・アンド・ルイーズ」「プリティー・リーグ」「カットスロート・アイランド」そして今回の「ロング・キス・グッド・ナイト」とすべて男を向こうにまわして一歩もひけをとらないという役ばかりである。
これは最近のデミ・ムーアなどにも共通する傾向のようで好んでこうした役柄を選ぶようだ。
時代の流れがそうしたものを支持する方向にあるということだろうが、どうも私の好みではない。
古いと言われるかも知れないがやはり女性は優しく可愛いほうが好感が持てる。
そのうえで主張するところは主張し、いざというときは女性らしい強さを発揮するというほうが好ましく思える。
女性が超人的な強さで男たちをなぎ倒していくというような設定はどうにも無理がありすぎて不自然だ。
だから彼女たちがどんなに活躍しようといっこうに格好良く思えない。
とここまで書いてきてなぜか妙にすっきりとしないものを感じてしまうのだ。
どうも書いていることに違和感がある。
そこでもういちどじっくりと考え直してみると、やはりいささか思い違いをしていることに気がついたのである。
女性が男性と対等に活躍するアクション映画をけっして嫌いなわけではなかったということだ。
というよりも女性が理不尽な敵に敢然と立ち向かっていくというような設定の映画はむしろ好きなジャンルの映画であったということだ。
その活躍する勇姿に常々痛快なものを感じていたというのが本当のところなのである。
例えば古くはジーナ・ローランズがマフィアを相手にひとり闘う「グロリア」の颯爽とした私立探偵ぶりなどは強く印象に残っているもののひとつである。
また「私がウオッシャウスキー」のキャスリン・ターナーの私立探偵ぶりも同様である。
主人公の女だてらのハードボイルドぶりにはうならせるものがあった。
「羊たちの沈黙」のジョディ・フォスター演じるFBI訓練生の活躍も印象が深い。
「ブルースチール」のジェイミー・リー・カーチスのNY市警役も忘れがたい。
NY市警の制服姿がよく似合っており、妙に色っぽくて目に鮮やかだった。
猟奇殺人犯とのめげることのない闘いは女性ならではのしぶとさを発揮したものであり、挫けそうになる自分を奮い立たせようとする姿はまことに健気であった。
「ニキータ」のアンヌ・パリロー演じる女殺し屋もカッコいいキャラクターで、その強さに不自然さを感じることはまったくなかった。
さらにそのリメーク版である「アサシン」のブリジット・フォンダも同様である。
またこれぞ真打ちとも言うべき「エイリアン」の女性航海士リプリー(シガニー・ウィーバー)の場合になればどんなマッチョな男もとうてい敵わないのではないかと思わせられる強さである。
その強靱な肉体と精神はどんなものも受け入れてしまう女性特有の柔らかさを備えた強さといえよう。
得体の知れない怪物エイリアンを向こうにまわし、ひとりで敢然と闘いを挑むリプリーの強さは映画史上最強のものに違いない。
そしてその強さ、次々と降りかかってくる難関を必死にかいくぐって進んでいくファイティング・スピリット、ネバー・ギブアップの精神は実に自然でリアルに感じられるものであった。
「まさか女性がここまでやれるのか?」といった疑問を差し挟む余地はない。
むしろ「彼女のタフさをもってすればどんな窮地だろうと必ずや抜け出すことができるに違いない」という信頼感に満ちている。
タフな男性ヒーローと肩を並べても遜色がない。
このように考えてくると、「ロング・キス・グッドナイト」に感じる違和感とはいったい何なのか。
ただ主人公が女性だからというだけの理由ではなさそうだ。
いろいろな原因があるのだろうが、もっとも大きなものはおそらくジーナ・ディビスに対する違和感であろう。
例えば彼女がふと見せる表情のなかに見えてくる間の抜けた気配。
鋭さがないというか、ドスがきいていないというか、緊張感のない弛緩した気配を感じてしまう。
その印象のせいでいっこうに強そうに見えないのである。
彼女の現実離れした活躍もリアリティが感じられず、どうしても不自然なものに感じてしまう。
大量の火薬を使った爆発シーンやハラハラドキドキというスタント・シーンがこれでもかというふうに登場してくるがいまひとつ乗り切れない。
これは前作「カットスロート・アイランド」のときにも感じたことである。
あえて 言い切ってしまえば、ジーナ・ディビスは大味な女優だということだ。
先に挙げた女優たちがもつ微妙なバランス、強さと優しさ、さらには自分の弱さを克服して生き抜いていこうとする人間的な苦悩や葛藤といったものがジーナ・ディビスには稀薄なのである。
作り物の嘘臭さがどうしても拭い去れない。
またレニー・ハーリンの演出にも「ダイ・ハード2」の頃の切れ味が感じられないといったこともあっていまひとつ乗り切れない映画であった。
製作 ステファニー・オースティン 製作・監督 レニー・ハーリン
製作・脚本 シェーン・ブラック 撮影 ギレルモ・ナバロ 音楽アラン・シルベストリ
出演 ジーナ・ディビス/サミュエル・L・ジャクソン/パトリック・マラハイド/デビッド・モース
|